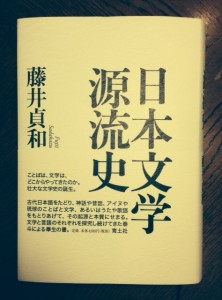『日本文学源流史』 青土社
藤井貞和氏は畸人である。奇人でも変人でもない。『荘子(そうじ)』大宗師(だいそうし)篇にいわく、「畸人は、人に畸なれども天に侔(ひと)し(肩を並べる)」と。畸人とは、普通の人間には偏倚と思われるが、本当は俗眼俗耳が見もせず聞きもしないことを感じ取り、天と対話している人だというのである。
五十年ほど前の学生時分、氏は日頃から伝説にくるまれていた。事の真偽は知らないが、たとえばこんな調子である。いつも電話に出る時、「もしもしもし」と三声で応じる。なぜかは誰も知らなかった。また、試験答案やレポートを提出した時、きまって独特な文章で教官諸氏を悩ませる。通常「~しただろう」とある所を「~ダロウデアッタ」と書いたそうなのだ。古代日本語では「断定」の助動詞は必ず「推量」の後に接続し、その順序が乱れることはない。きっと彼は頭の中では古代語で考えているに違いないと、友人たちは噂しあった。
氏の近著『日本文学源流史』は、この野心的なタイトルが暗示しているように、日本文学の成り立ちをその始原にまでさかのぼって再構築しようという雄大な構想をそなえた労作である。「始原」とはたんなる「過去」ではない。「現在」の瞬間をすっぱり断ち切っても、その断面にいつも伏在して、全過程を深層から規定し続ける初期条件である。たとえていうなら、かつて氏自身が古代日本語の「時の助動詞」の成立を論じた文章を借りて説明しよう。
かつて日本語の「時の助動詞」(き、けり、ぬ、つ、たり、り)には動詞・形容詞・動詞などの自立語だった独立時代があった、というのが藤井氏の立てた仮説というよりむしろ先天的な記憶である。たとえば「き」には「来(く)」の、「ぬ」には「往(い)ぬ」の、「つ」には「果つ」の残響があるといったように。それがやがて時制表現を死活的に必要とした古代人によって非自立語化されて助動詞になったとされるのだ。現代日本語には過去の助動詞としては「た」一語しかない。「た」は、現在言葉の表面には現れず、前言語的に複合し屈折している思考・感覚・色調・陰影等の表現をいわば兼業しているのである。(『日本語と時間』参照)
日本文学の源流を探ろうとする仕事を貫いているのは、右のように特異な思索の軌跡である。源流はただの上流ではないし、源泉でもない。水流は現在も流れ続けているのであり、氏が文学の過去にこだわることはそのまま現代の問題領域に分け入ることなのだ。こうして始点と現時点とをいつも同一視野に置く独特のパースペクティヴを見るために、独創的な《時代区分》に注目しよう。読者はまずその構想力に驚かされる。
1 神話紀 (ほぼ縄文時代)
2 昔話紀 (ほぼ弥生時代)
3 フルコト紀 (ほぼ古墳時代)
4 物語紀 (7,8世紀~13,14世紀)
5 ファンタジー紀orポスト物語紀 (14、15世紀~ほぼ現代)
これらの5紀はそれぞれ幾世紀かの質量をもってただ逐次的に累積するのでなく、重層しかつスペクトル的に連続している。幾十世紀もの間、水流が沈澱させることなく、ひたすら今日まで押し流して来たものが、現代において一挙に浮かび出るのだ。そうした一種の永久運動性が日本文学の歴史を特徴づける。氏が1972年に書いた文章を借りれば、「日本の神々が、変動の時代あるいは変革期になると生きてあらわれ、変動の時代あるいは変革期が過ぎると傷つくか、死ぬかしてゆくという特徴」(「物語のために」)なのである
拙老は、1~3紀までの記述が琉球語やアイヌ語の知見に視界を広げた口承文学の世界に踏み込んでいる部分に関しては、論評を敬遠する。また、5紀の近世(江戸時代)に関する記述については、氏の想像力の飛翔について行けるかどうか心もとないので評判にわたらない。ここで熟読の焦点とし、積極的に紹介したいと思うのは、物語文学論である。何をおいてもまず、以前に氏が下した《ものがたり》の定義に眼を向けよう。この定義はいわば氏の初心である。
《「ものがたり」とは、正史に属する語りに対立する、正史でない語りだったのではないかと思われる。語られるべきは正史なのだ。その語りであるという正史の限定を取り去ったとき、それが「ものがたり」ではなかったか(……)カミ(神霊)になることのできなかった、劣位の霊魂がモノであることは、大方の意見の一致するところであった。非正統の存在として、歴史の背面へ埋没させられてゆく運命を持つ、いわば二流の霊魂がモノと呼ばれる。》(「物語の発生する機制」)
今この『日本文学源流史』にあっても、この初心が揺らぐことはない。物語をモノのカタリとしてカミのカタリへの対抗軸に置き、それが「霊(モノ)ガタリ」として、どこまでも「劣位の」「二流の」モノによる語りであったとする物語起源論を基礎的な構図とする原理はいささかも変更されていない。この卑下に見えて実は確信に満ちた所論は、氏が民俗学者折口信夫(おりぐちしのぶ)の物語発生論を読み解き、読み破って血肉化したものに他ならない。この欄で1月23日に取り上げた『ゲンロン』創刊号で、福嶋亮大氏が「日本文学をいかに批評するか」で折口の『日本文学研究序説』を引用し、「今日のほとんどの批評家」は「参照すべき歴史的文脈の構築には無頓着であった」といているが、この場合藤井貞和氏の仕事を見落とすべきではなかった。
この『日本文学源流史』は、さすがにいつまでも、《カミガタリ vs. モノガタリ》の図式にこだわっていない。代わって提出されるのが《フルコトvs. モノガタリ》とでも公式化できそうな、新しい対立軸だ。フルコトが正史の「正統的な語り」であるのに対して、モノガタリは「非正統的で自由な語り」である。表現字句上の些細な違いに見えるかもしれない。しかし、この微妙な修正は大規模な比重の移動を伴っていると思う。たとえば「室町物語」というような境界例も見られるように、物語は「かならずしも完結しない物語性」あるいはポスト物語性を孕み始めるとされる。
本書のこのあたりの行文はまだ熟し切っているとは言い難く、文章の晦渋さが気になるが、それにしても、氏が「14,15世紀~ほぼ現代」とかなり長めに――つまり、全期間の等質性をいわなくてはならない――設定した一時期を「ファンタジー紀」あるいは「ポスト物語紀」と名づけ、そこに生起した文学的事件の当事者たちを一連の系譜で捉えようとした視界の深さ、膂力(りょりょく)の強さには驚かされる。氏の構想の中に強力な磁場が形成されたとでもいった具合に、その系譜に連なる人々を磁界に引き寄せるのである。芸能民、隠者、浪人、戯作者、遊民・・・ひいては文学者、と辿られる非定住者の系列だ。そして「次代を作るべきアーティストは人生のどこかで隠者であることを経験する」と氏が書く時、氏には自身がその系列に連なるという自覚がたっぷりある。そしてそうした確信は間違いなく、氏が自身の学問の「参考項目」とする折口学のあの周知の命題:「隠者は、古来、社会の制外者である」(「女房文学から隠者文学へ」)に励まされている。
しかし、使徒は常に師が知らなかった新しい時代に直面しなくてはならない。非定住の地点を文学者の居場所と見きわめるにしても、現代には神話や民俗伝承が積み残してきた幾多の問題が存続しているはずだ。ほんの一例を挙げれば、民俗学が人類の過去に存在したことを確認し、現代にも痕跡を留めている人身供犠の問題。なまの人間を犠牲にすることを止めて動物を犠牲にするようになったことが文明の進歩と見なされているが、果たしてそうか、現代人の魂の内部には民俗的暗がりに回帰する通路が見出されるのではないか。氏が「人身供犠」というテーマを手がかりにして「死刑」「戦争死」「差別」「いじめ」等々のホットな問題群ににじり寄り、民俗学の射程に引き込んで行く論調は鋭い。
1969年の藤井貞和氏は、文学者であることについて、「文学は徹頭徹尾、社会的には無効であること、無効でなければならないことを、いやおうなく知らされてきた」(「バリケードの中の源氏物語」)とぼやいていた。しかるに今、『日本文学源流史』を結ぶこんな一文には、何かもっと確信に満ちたトーンが感じ取れないか。原発事故の問題に多くの文学者が取り組んだことについて氏はいう「技術の暴走を文系が鎮めてまわるというようなことか、だれが知ろうか。」