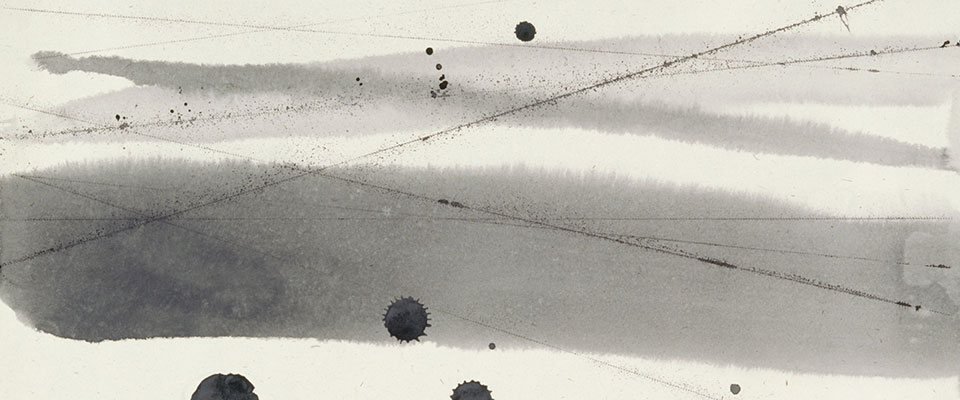[皆さんの声をお聞かせ下さい――コメント欄の見つけ方]
今度から『野口武彦公式サイト』は、皆さんの御意見が直接読めるようになりました。ブログごとに付いている「コメント欄」に書き込んでいただくわけですが、
同欄は次のような手順で出します。
トップページの「野口武彦公式サイト」という題字の下に並ぶ「ホーム、お知らせ、著作一覧、桃叟だより」の4カテゴリーのうち、「桃叟だより」を開き、右側サイドメニューの「最新記事」にある記事タイトルをどれでもダブルクリックすれば、その末尾に「コメント欄」が現れます。
そこへ御自由に書き込んでいただければ、読者が皆でシェアできることになっています。ただし、記入者のメールアドレス書き込みは必須ではありません。内容はその時々のブログ内容に関するものでなくても結構です。
ぼくとしては、どういう人々がわがブログを読んで下さっているのか、できるだけ知っておきたいので、よろしくお願いする次第です。以上
このところ世の中は舛添東京都知事の金銭スキャンダルの報道で持ちきりです。折から伊勢志摩のサミット会議、来日したオバマ米国大統領の広島訪問と重大ニュースはいろいろあるはずなのですが、なぜか人々の面白がり方ではこちらの方が押しています。次々と、新たな「不祥事」が発覚するたびに、皆さん明らかに楽しんでおいでのように拝見されます。
この「面白がる」という反応にこそ、一つの《社会現象性》が見て取れるのではないでしょうか。
「人の不幸は蜜の味」という言葉がありますが、一般に、有名人の没落やエリートの失敗ほど民衆を喜ばせる話題はありません。拙老などもその最たる者で、昔一時アメリカにいた時分、いつも東大の英文科の先生に「オマエの英語の発音じゃとても通じないよ」と言われてシュンとしていたのを思い出します。しかしある時レストランでくだんの先生がスパゲッティを注文したら紅茶(ティー)を持って来られて目を白黒されたのを見た日は一日中シアワセでした。
東京都知事のポストは最近どうやらケチが付きっきりのようです。猪瀬前知事の突然の辞任は金銭疑惑がらみだったし、今回の騒ぎもまだ結末は分かりませんが、似たような匂いがします。問題は、この種のスキャンダルが、①なぜ東京の首長というポストに、②猪瀬・舛添といったインテリ文化人に集中して起きたかということです。大坂はちょっと微妙ですが、東京都の知事があまたある道府県の首長と違うのは、行政権限や財政規模の大きさは別として、選出に当たって都市知識人の世論が大きく反映することにあると思います。たんに目先の経済利害だけにこだわらない思考ができる人口部分です。
この人口部分は、おおむねいわゆる中間階層に属します。有名なピケティ理論による世界普遍的な公式――「r>ɡ」(株や不動産など資産の収益率は経済成長率を上廻る)という不等式――をあてはめれば、いつも全社会的な富が偏在すること(永久に不等式の右辺にいなくちゃならない)のワリを喰わされていながら、自分たちは最下層ではないと思っていられる階層です。昇給の機会を窺い、失業の脅威にあたふたする流動常なき人口部分です。この階層から政治家が出るとしたら、ウエーバーのいう「職業政治の二種類」のうち第二の「政治に《よって》生活するタイプ」に属することになりましょう。
ここから、猪瀬・舛添御両人に共通する一連の悲喜劇が生じます。猪瀬さんはかつて信州大学の全共闘議長でした。それなりの理想に燃えてらしたと思います。それともこの時代、氏が身に付けたのは駆け引きと人心統合術だけだったのでしょうか。舛添さんは最高学府で成績はいつも上、それ以来ずっとエリートコースをたどって来られました。そして二人とも《職業政治家》の道を選ばれました。衆目が集まるのも当然です。
ところで、政治家の世界には、これまた世界普遍的な公式があります。さきほどのピケティの不等式のひそみに倣うなら、「公>私」とでも表記できましょう。オオヤケをいつもワタクシに優先しなくてはならないのです。そういうものなのです。今度のことでも、「公私混同」が取り沙汰されているのも偶然ではありません。「わしゃ断乎として公益より私利を追及する」と公約した政治家を聞いたことはありません。正直かもしれませんが、当選する見込はありません。政治はそういうタテマエになっていないのです。
古語に「公は私に背く(『韓非子』)」という言葉があります。「公」は「八」と「ム」の会意。ムは「私」の古字、一説に「八」は「背」の古形。 八を左右に背く形と解するのだそうです。どうも昔から、公と私は折り合いが悪かったみたいです。むしろ利害背反的だったのかも。本当は「公<私」なのだがタテマエ上「公>私」ということにしておくのでしょうけれど。
わが国の現行政治制度はデモクラシーということになっています。タテマエとしては、身分・階級・性別・年齢・財産の差異に関係なく、政治家になれることになっています。しかし現実には決してタテマエ通りにはいきません。誰にでも生活時間を全部政治にふり向ける余裕があるとは限らないからです。政治家にもどうしたって格差ができます。その事実に目をつぶって、政治家は「公>私」の看板を掲げますし、被治者の民衆もそれを期待します。
それだから余計、民衆が失望した時の反応は辛辣(しんらつ)なのです。19世紀フランスの政治思想家トクヴィルはこんなことを言っています:「偶然によって権力の地位に上がった者の腐敗にはなにかしら粗野で下卑たところがあり、そのために一般大衆もまたその腐敗に染まってしまう」「公金を横領したり、国家の恩典を金で売ることならば、極貧の民でもよく分かり、次は自分の番だと期待することができる。(『アメリカのデモクラシー』、松本令二訳)」。21世紀の日本のこととして、東京都知事の公私混淆が人々の笑い物になっているのは日本のデモクラシーがまだ健康である証拠とはいえないでしょうか。少なくとも皆がわれもわれもと「次は自分の番だ」と期待してはいないようですから。(野口武彦記)
このところ連日、舛添東京都知事を俎上(そじょう)に乗せるニュースがテレビの画面を賑わせています。殊に、拙老が見ているのは関西のテレビ局製作の番組ですから、製作者も視聴者も「東京憎し」のアンダートーンで盛り上がり、舛添さんが苦しい答弁を繰り返すたびに大いにはしゃいでいるように見受けられます。
拙老はかねてから世は末造(まつぞう)の時代と達観していますから、東京も大坂も眼中にありません。日本中どこででも、中央でも地方でも、現在「政治家」と呼ばれる人々、そう称する人々にとっての共通の問題を取り上げようと思います。
末造期を生きる政治家とはどういう人々なのでしょうか。「末造」という言葉はあまりなじみはないでしょうが、元は『礼記(らいき)』に「諸侯の冠礼あるは夏(か)の末造なり(諸侯が元服で冠を付けるようになったのは、夏王朝の末期からである)」とある典拠から出た言葉で、王朝末期ということです。これを今は「政体末期」というぐらいの意味で使っています。政権末期よりは一つ大きい単位です。「終末期」というと変にユダヤ=キリスト教臭いし、「末法時代」というと佛教臭いし、「末日」というとモルモン教か エホバ教臭いので、まったくニュートラルに「末造期」という無味無臭の言葉を選びます。
政治家といえば、マックス・ウエーバーの古典的な名著に『職業としての政治』というのがあります。原題は Politik als Beruf です。今更めいて気が引ける次第ですが、このBeuf なる語はberufen(英語ではcall)の名詞形であり、原義にはrufen「呼ぶ」「呼び寄せる」「召す」などの語意が生きていて。「任命」「使命」「呼集」といった訳語があてられます。中でもいちばんよく知られているのは、「召命」というキリスト教用語でしょう。信徒になるべく、神が人間個人に呼びかけるという意味です。この語義がつねに基層にありますから、ウエーバーの著書もせめて『使命としての政治』とでも訳しておけばよかったのです。それを『職業としての…』とやったものだから、後の混乱が始まったというわけです。もちろん Beruf には「天職」という訳語もあり、「天が与えた職」という考えを仲介にして「職業」という語義が派生します。不幸なことにこっちの方が世に流布してしまったのですね。
ヘボンの『和英語林集成』は慶応3年(1867)に初版を発行し、その後、続々と見出し語を35618語に増やし、明治日本も基本的語彙を収めた三版は明治19年(1866)に刊行されました。「職業」という日本語に対応する英語の名詞には、business,avocation,occupation,pursuit,employment,work,duty,tradeと、都合8語が列挙されています。ドイツ語の(というよりウエーバーの)Beruf と英語の(ヘボンの)business とではだいぶ違います。Avocation(副業)はまさか vocation(天職)の誤りではないと思われますから、そうすればよけいに、明治の「職業」は宗教性を脱色していることになります。Business はなるほど天から与えられた使命(天職)ではありませんが、人と人の間の契約に基づくものなのです。
一方、「職」という漢字にも長い歴史があります。原義には「しるし」という意味の底層があり、耳扁(へん)がついているのは、白川静(しらかわしずか)説では、昔、戦功の証拠に敵の左耳を切ってしるしにしたからだそうです。「しるしのある物」から「唯一の」「占有の」「ひたすら」「もっぱら」等の語義が派生しました。荻生徂徠もある仕事に専念することを「職として」事にあたると表現しています。徂徠学には「天命」の概念がすでにありましたから、幕末・明治の漢学的知識人たちは Beruf といった言葉に出会っても別に驚かなかったのです。
しかし、21世紀の日本での「職業としての政治」は、横文字でいうならさしずめ Politics as job とでも表現するのが適当なように思われます。いっそ「商売としての政治」といった方がすっきりするかもしれません。「商売としての」という言い方ががドギツイならば「生計のための政治」としてもよいです。じつはウエーバー自身もすでに同書中の「職業政治の二種類」という段落で、職業政治家を①政治の「ために」生活するタイプ、②政治に「よって」生活するタイプの二つに分類しています。つまり、国家および市町村の議員、知事・市町村長、閣僚ならびに高級官僚などの俸給生活者のおおむねがこの②のグループに所属すると見てよいでしょう。シビリアン・コントロールが優勢な現代では特に、選挙で選ばれた政治家が行政府の「役人」を動かすシステムが出来上がっていますから、政治家商売も大繁盛のようです。
昨年、公金を私的な旅行に注ぎ込んだのを県議会で追及されて、「せっかく県会議員になれたのにイ」と号泣してすっかり有名になった野々村さんという人物がいました。今度の舛添さんのケースも、「せっかく東京都知事になれたのに」という点でまさに同格と申せましょう。でも、高校生の時は模擬大学入試で毎年全国2,3位を争い、大学ではつねに優等生であり、東大教授をやめて政界入りをしたようなヒトは、普通こんなことは言わないものです。そういうヒトが政治の大道を歩むところにこそ、現代の「末造期」たるゆえんがあるのでしょう。ウエーバーも言ってます:「彼(職業政治家)の収入は、彼が常に彼の労働力と彼の思考力とを、完全に、またははるかに圧倒的に、彼の収入を獲得する勤務におくということに依存してはいけないということであります」(西島芳二訳)と。よく分からない訳文ですが、要するに、政治家は自分の給料だけじゃやっちゃいけまいということらしいです。 (野口武彦)

宮川河口の白鷺
この写真は、宮川の河口附近で餌をあさっているシラサギをヘルパーさんに撮ってきてもらったものです。歩行中です。運動感があります。水中の石をしっかりと踏みしめて嘴を伸ばし、じっと魚を狙っているようですが、何の魚かはわかりません。宮川は、つい最近までは大きな溝川みたいな流れでしたが、芦屋浜埋立てと共に、川筋が延長され、護岸工事も施されて芦屋川ほどではないが、いっぱしの川になりました。新しい河口から海水がさかのぼって淡水と入りまじり、独特の汽水域が広がってボラやマハゼが繁殖します。シラサギが探しているのもこういう種類の魚なのだろうと思います。
自分が魚になって鷺についばまれる話が泉鏡花の小説にあります。
「――頭からゾッとして、首筋を硬く振り向くと、座敷に、白鷺かと思う女の後姿(うしろすがた)の頚脚(えりあし)がスッと白い」(『眉かくしの霊』)。
鏡花の小説には「鷺」が何度も登場します。この作家の血肉にまで食い入っている個人神話の象徴体系の内部で、「鷺」は特定の意味作用を持っているのです。「鷺」はつねに妖艶な女性との二重像として出現し、男に死の恐怖をもたらします。鏡花はこれを原画としてそのいくつかの変奏を『青鷺』『白鷺』『鷺の灯』『神鷺の巻』で描いています。中でも傑作は、上に引用した一文のある『眉かくしの霊』でしょう。語り手が温泉宿の一室で美しい芸者の幽霊を見る場面ですが、その直前の夢の中で、語り手は魚になって鷺の嘴にくわえられて空を飛び、池に落とされるのです。
だいたい鏡花にあっては、基本的に、サギとは美しくて男を恐怖させたり戦慄させたりし、また自分も殺されてしまったりする妙にマゾヒスト的な女性です。拙老がイメージするサギはちょっと違います。鋭い嘴で小魚や蛙をつついて喜ぶサドっぽいサギなのです。それも可愛らしく、丸いお尻をした雌のカエルが好きなようです。なぜ唐突にカエルの話が出て来るのかと申しますと、今から20年前も拙老が住んでいたこの辺一帯にはのどかなサギとカエルの楽園があったからなのです。
その頃でも異例の眺めだったと申せましょう。土地開発のラッシュの中で、奇跡のようにただ一ヶ所、ネコの額よりも狭い池の水面が残っていたのです。 毎年夏が近づいてくると、この池ではウシガエルがいっせいに野太い声で鳴き立て、渾身の大合唱があたり一面に響き渡りました。安眠妨害になるから池を埋めろという近隣住民の声も高かったのですが、地主は頑として聞き入れず、水草が茂り、トンボが舞う貴重な水面が守られていました。時にはみごとなアオサギが蛙を捕りに飛んできた。バサバサッと羽音を立てて頭上すれすれに飛びました。
その池が思わぬ役に立ったのは、1995年の大地震の後でした。災厄はいろいろあったが、水道が止まったのには皆が困りました。飲料水もさることながら、トイレが流せないのにはいちばん参りました。方々から人々が集まってきて池の水を汲んでいきました。衆の力は恐ろしいものです。しばらく経ったら池は完全に干上がってしまいました。そしてこの年ばかりは、さしも喧しかった蛙の声がまったく聞こえてきませんでした。みんなカエルは絶滅したと思っていました。
ところが、自然には不思議な回復力がありました。池の水源は六甲山系の地下水だったらしく、どこからともなく水が湧き出して、池はいつのまにか元のように水を湛え、浮草が青々と水面を覆いました。ミズスマシもまた泳ぎ始めました。そして翌年の春、思いがけなくギコギコゲコゲコと聞き慣れた声が響いてきました。カエルたちは無事に戻ってきたのです。あの時ほど嬉しかったことはありません。
地震から何年も経ってから、池はなくなり、カエルも姿を消しました。カエルの歌もピタリと聞こえなくなりました。災害の記憶が薄れるにつれて、今度は「耐震保証付き」とやらで再び住宅建設が盛んになったのです。池は埋められ、その跡にこじんまりしたアパートが建ちました。住人は家の下の地面が以前は池だったことを知りません。わざわざ教えることでもないので黙っています。
土地造成が始まる前に、近所の子供たちが蛙をかわいそうに思い、できるだけたくさんの数を捕まえて奥山の池に運んでいったと聞きました。日本古来の言い伝えでは、蛙は自分が生まれた場所に帰る習性があるそうですから、新しい池になじめなかったり、先住の蛙たちにいじめられたりして、また群をなして古巣に戻って来ようとしたことも充分にありえます。きっとリーダーの年かさのカエルに率いられてぞろぞろ隊伍を組んで行列したのでしょう。
山道をたどり、丘を越えて帰ってはきたが、もうどこにも昔の水面はありません。消え失せた故郷の池を求めて夜道をうろうろし、人間に化けて道をたずねるカエルたちの恰好(かっこう)が目に見えるようです。このことは別に新聞にも載りませんでしたから、全員ひっそりと途中で干からびてしまったものと思われます。
池のカエルを求めて飛んで来ていたサギの姿も見かけなくなりました。サギは山の方にいくらでも群生地がありますから、絶滅はしてないでしょうが、身近に見られないのは淋しい限りです。写真のサギは、池に来たお仲間よりは何世代も若いと思いますが、もしここにカエルがいたら――塩水中に住むカエルというのは聞いたことがありません――やっぱり食べるのではないでしょうか。また、食べられはするもののカエルの方でもサギが好きだったのではないかと思います。水面に浮かんだお尻を嘴でつっつかれのが快感だという不思議な相思相愛の世界があったのでは? (野口武彦)

岩園天神鳥居

岩園古墳跡
あれはたしか昭和30年(1955)のことだったから、もうかれこれ60年も前の話になります。その頃まだ高校生だった拙生は、けなげにも詩人になろうという大それた野望を抱き、果敢かつ大胆不敵また厚顔無恥にも、ある日詩稿を『ユリイカ』の伊達得夫(だてとくお)氏のところへ持ち込んだことがあります。お宅は当時柏木1丁目という地名だった今の北新宿にありました。美人の奥さんが紅茶を御馳走してくれたのですが、当の伊達氏は拙作に目を通して苦笑されるばかり。さぞ当惑されたことだろうと思いますが、こちらの方も冷や汗びっしょりでした。詩稿が全部ボツになったことはいうまでもありません。
その時分拙生は、西脇順三郎にあらずんば詩人にあらずと思い込むほど西脇一辺倒で、自分が作る詩(?)も、体言で行を替え、助詞は行頭に置く等々何から何まで西脇を模倣するありさまでしたから、相手にされなくて当然だったのですが、その冒頭の1編だけは満更でもない出来だったろうと今でも性懲りもなく思っています。こういう詩です。
祠の奥の鏡
に数珠玉の実が
映って揺れる
俺の魂と思った
他のは全部クズでしたが、この作にだけは未だに何か捨てがたいものを感じています。わずか4行の詩句が喚起する情景に、《魂の小景》とでも呼びたくなるものが垣間見えているような気がします。この詩作以来、拙老の外界受容器官にはいつもあらかじめこれが原画として仕込まれていて、外の景色が二重写しにされるような塩梅です。もう80年近く生きていますが、この二重写しに遭遇する機会はほんのたまさかにしか訪れません。この前、それがやって来た時は一種の不意打ちでした。
2010年に大病を発する直前、筆者はこの稀有な体験に遭遇したのです。
今回、巻頭に掲げたのは,芦屋市の北東部、隣接する西宮市とは山続きの土地にある岩園天神社の正面鳥居と境内の古墳跡の写真です。この天神社は下方の打出天神社と違って、廃社でこそないがひどく荒れ果て、今では神主も常住していないそうです。境内の森の中に古墳の跡と思しい岩むらが二つあります。昔はすぐ近くにある八十塚(やそづか)古墳群の一部だったのでしょう。このあたり一帯は先史時代に巨石文化が栄えた地域であり、もっとさかのぼれば旧石器時代の縄文人が古大坂湾の海進を避けてこの高みに暮らしていたのかもしれません。現在ではもう骨も土器も見つかりませんが、剥き出しに転がる岩石の群が無言でいろいろな記憶を語り掛けてきます。
岩園天神社の岩むらは、古い時代に崩壊した古墳の石室の遺跡と見られます。市内の芦屋神社には洞窟状の石室がありますし、西宮の甑岩(こしきいわ)神社には名の由来になった巨大な陰陽石と立派な磐座(いわくら)があります。両方とも、天井や壁があるのでいかにも古墳らしく見えるのですが、これはただたんなる岩石の雑多な積み重ねです。みごとに何にもなくなっています。
前世紀の1980年代に「路上観察学」という趣向が大いに流行(はや)りました。「絶対トンネル」だの「純粋階段」だの「無用門」だの当時「トマソン」――巨人軍にいた元大リーガーで、三振ばかりするのにずっと4番打者に据えられていた選手です。さっそく《大事に保存される無用の長物》の代名詞になりました――と呼ばれた珍妙ながら楽しい概念を次々といろいろ発見したものです。写真集も出ました。
その語法でゆくなら、この岩むらなどはさしずめ「抽象古墳」というところでしょう。実在の古墳を古墳たらしめる具体的要件――誰かを葬祭したしるしである内部空間(玄室)とか築山などの外郭(たとえば芦屋市内の親王塚)――のたぐいはきれいに消失し、ただ簡略な輪郭が残っているだけなのですから。
遺跡跡に積まれた石組の間の空隙には何もありません。何も見えないのではなくて何もないのです。でもそうはいっても、ここにはかつて何かがあったという記憶が残存し、縦横奥の三つの次元による区切りがこの場所は占有されていることを明示していますから、この間隙にはいわば「時空それ自体」が充満しているといえましょう。ここには存在の芳烈な残り香が漂っています。もしこちらの身がフィルムだったとしたら、すぐに感光してしまうくらい強力な自然放射能のようなものを発散しています。拙老はその放射根源の方に目を向けました。と、先方からも同じ強度で視線が返されて来ました。あの岩の隙間から何ものかに見られていると感じたのです。岩園天神社に足を向けた日、拙老はそうした被視感を心の皮膚でぴりぴり知覚しながら境内の森をを歩きました。
天神社の鳥居は南向きで、神域の西側から東に向かって一筋の谷川が流れています。流れに沿って歩行路が付いています。その時なぜかその細径を辿って下界へ降りてみようという気が兆したのです。もしかしたら、あの岩むらの空所から何かがするりと抜け出して拙老の小紀行に同行したのかも。谷川道を下ってゆく拙老のまわりだけ、にわかに空気の成分が変わったような気がしました。山側の崖から傾いてきて道を塞いでいる倒木や竹の幹を踏み越え、潜り抜けてゆくと、さしかける日の光もは薄くなり、聞き慣れない小鳥の囀りが耳に近く響き、地味な模様のヒョウモン蝶が舞い、谷水ひたひたの低所を真っ黒な翅(はね)のトオセミトンボが飛んでいました。そこは一種の異空間なのでした。両岸に繁茂する広葉樹林の梢越しにマンションの棟が見えましたが、その眺めは遠く隔絶された日常世界というより、無理に次元をくっつけた合成写真のようでした。
だがなおも歩いている内に、だんだん流れは谷川らしくなくなり、ただの溝川になり、やがて町中を流れる通常河川に合流しました。後で聞けば、夙川(しゅくがわ)につながる支流だそうです。下界はもう西宮市になっていました。タクシーを停め、 岩園トンネルをくぐって家に帰りました。それからしばらくして拙老は髄膜炎を発病。病源は長らく不明でしたが、病院では、昔感染したきりずっと遊眠状態だった結核菌が目を覚ましたのだろうと結論を出したそうです。しかし、拙老はあの岩むらに何万年も眠っていた何ものか――たぶんわが地霊――の不死のヴィールスが、「時を得たり」とばかり、拙老という人間に安住の地を見出して棲みついたことを信じて疑いません。とはいっても、うちの荊妻はこの意見を頭から撥ね付けますけれども。(野口武彦)

西川照子『金太郎の母を探ねて』 講談社選書メチエ
今でも残党はいるのかいないのか、あれはたしかバブルがはじけてからしばらく経った頃、「山姥(やまうば)」と呼ばれる若い娘たちの出現が社会的な話題になったことがある。身なりはサイケデリックで、けっこう露出的なのもいたが、顔を真っ黒に塗り立てるという異様な風体で盛り場によく屯(たむろ)していた。まわりに人を寄せ付けない断固とした雰囲気だったが、その心底は意外に自己防衛的であり、鬼面人を驚かすガングロの裏には、やたらなオトコの接近を拒む可憐な純潔さが潜んでいるらしかった。
西川照子氏の近著『金太郎の母を探(たず)ねて』は、日本文化の根底を流れる「母子神信仰」の姿に光を当て、その原型を「母」としての山姥・「子」としての金太郎に求めて、この伝承の現代的な意味を探ろうとした労作である。著者が本書に盛り込もうとした内容は多様かつ多端であり、論旨の展開に沿って論評するのはなかなか難しい。私見では、本書には外向きに話題と素材を拡張する方向に働く力と、著者自身の内側に向かって屈曲してゆく自己凝視の方位へ引かれる力という二つの力学が作用していると思われる。
21世紀になると共に、「中世日本紀」という新しい学問分野が出現している。中世に成立した『日本書紀』の注釈を中心に――『日本書紀』ばかりではない――歌学注釈書・神道書・寺社縁起・本地物語などに断片的に書き連ねられている諸伝承を統合して、古代以来の記紀神話に拮抗しうるもう一つの神話を構成しようという学問構想だ。これらを今「中世神話」と総称しよう。著者はまずこの世界の逍遙からスタートするのである。
さて、著者がまず踏み入るのは金太郎の母の原像である。第一に、室町時代に成立した御伽草子の1篇である『熊野の本地』。この本地物は《神仏の人間時代の物語》という原則通り、天竺の「せんさいおう」という大王と「御すいでん」の女御(「せんこうの女御」)が試練の末に、日本の熊野の地に来て、熊野権現として鎮座したというストーリーである。しかし著者は、もっぱらこれを女御が山中で首を斬り落とされて死ぬが、首なし死体の乳房から3年の間乳を出し、連れていた赤子(王子)を養い続けたという「母子哀話」として読む。そこから「山中赤子誕生譚」というモチーフ(主題領域)を見出し、次々に連想を拡げる。
第2は、謡曲・幸若舞(こうわかまい)および古浄瑠璃の『山中常盤(やまなかときわ)』――むしろ、盗賊どもが常盤の白い肌を引ん剥いて刀で突き刺す残酷シーンを描いた岩佐又兵衛の絵巻で有名だ――。作中の常盤は山中で出産はしない。奥州にわが子牛若丸を訪ねてゆく途中である。しかし、著者は想念裡に《山中で生むべかりし》赤子と英雄児牛若(後の義経)とを合体させる。著者の想念では牛若丸イコール山中出産児である。ゆえに、常盤=牛若の母=山中出産児の母。この等式と《金太郎の母=山中出産児の母=山姥》という等式とは緊密に照応している。著者はいう。「牛若を助けんとする母の執着」によって常盤は「妖怪となった」と。山姥は固有名詞ではないが、わが子への「異常なまでの深い愛情」によって妖怪になった母である。金太郎の母と常盤とはいわば同位元素の関係にある。

岩佐又兵衛:山中常盤物語絵巻より。MOA美術館蔵
https://www.google.co.jp/search?q

喜多川歌麿による山姥と金太郎
https://ja.wikipedia.org/wiki/山姥
そして著者がいよいよ深く中世神話の世界に参入するのは、古代の神功皇后伝承以前の八幡信仰の形を伝えるという『八幡宇佐宮御託宣集(はちまんうさぐうごたくせんしゅう)』(正和2年1313撰)によってである。撰者は神吽(しんうん)という宇佐弥勒寺の学頭僧。多くの記録や伝承を網羅して八幡=応神天皇説――柳田國男の『玉依姫考(たまよりひめこう)』は、その成立を弘仁11年(820)の神託以後としている――を骨格とする伝統権威に対して、毘盧遮那(ビルシャナ)仏を助ける役割を果たす天神地祇に位置づける解釈がむしろ正統だったとする教説をうちたてた。八幡神は佛教との習合の結果、「八幡大菩薩」の色彩を濃くしたといえよう(桜井好朗さくらいよしろう「八幡縁起の展開」参照)。
西川氏が主として関心を向けるのは、『八幡宇佐宮御託宣集』の中で、神功皇后すなわちオオタラシヒメと竜宮との深い関係について語った箇所に「大帯姫(オオタラシヒメ)は吾が(応神天皇の)母にして則ち娑竭羅(シャガラ)竜王の夫人なり」とある一文だ。奇々怪々な文章だ。それなら応神天皇は竜王の息子なのか? しかし著者は細かな記述の混乱には目もくれず、「原応神天皇」ともいうべき御子神が海で生まれたという記述に注目する。著者もいうように、「海を渡らねば、神の子は生まれない。“海”である。ウミである」からである。思うに「産み」の語呂合わせであろう。
もしも「神の子」が海を介することなしには生まれないとしたら、本書によって読者を、金太郎を「神の子」とする論旨に誘導しようとする筆者の意図は一頓挫 せざるをえない。金太郎の母は山姥であり、山姥は山の妖怪――零落した「山の神」だかからである。山の神は海の神ではない。だが著者はその同一性を論証しなくてはならない。
そこで西川氏の資料博捜、伝承渉猟が始まる。結論から先にいえば、著者はまず、お伽話に登場する金太郎・桃太郎・浦島太郎の「三太郎」は「同一人物ではないのか」と断じ、それから個々の考証に取りかかるのだ。①金太郎の神話原型――『古事記』の天津魔羅(あまつまら)・『播磨国風土記』の天目一命(あめのまひとつのみこと)・『山城国風土記』逸文の別雷神(わけいかずちのかみ)。②桃太郎誕生の神事――『本朝月令』の「秦(はた)氏本系帳」が記録する松尾大社の伝承。③浦島太郎の神話的出自――『日本書紀』雄略22年。浦島太郎は「竜宮童子」のイメージを背負っている。また「太郎」は総じて「神の童名」であるとして「タロウ→タロ→タレ→タレル。垂れる。つまり神がこの世にそのお姿を現わすことを言う。だから神功皇后のオキナガタラシヒメの『タラシ』も『太郎』なのである」と論点を補強してもいる。
金太郎の母の山姥は、源頼光に「この子の父は誰か?」と聞かれた時こう答える:「居眠りをしていたら、夢に赤い竜が現れて、雷が轟きました。その時、この子を身篭もったのです」。赤い流というのは容易に察されるように電光――雷神である。柳田國男の「かつて我々の天つ神は、紫電金線の光をもって降り臨み、竜蛇の形をもってこの世に留まり給う」(『雷神思想の変遷』)という一文を思い出すまでもなく、この夢は神聖受胎の告知であった。別の柳田学用語でいえば、「神父人母(しんぷじんぼ)の神話」(同前書)である。そして西川氏はこの神聖受胎ないしは神婚を「処女懐胎」と読み替える。
著者が特に心を篭めるのは「母子一緒に生き埋めにされる」形での人柱伝承である。例に挙げるのが大分県中津市の八幡鶴市神社に残る、母は鶴、子は市太郎と名の知られる伝承だ。民俗学では有名な話で柳田は『妹の力』で、文化人類学者の石田英一郎が『桃太郎の母』で取り上げている。西川氏は二人の意見を、「柳田も石田もともに市太郎を『父無し子』と見て、『処女懐胎説話』を挟み、母子を八幡神と結び付けている」と要約する。
しかし問題は、柳田が本当に「処女懐胎説話を挟」んでいただろうかということだ。柳田が言っているのは「市太郎の父は誰であったとも知れぬ」というだけのことであって、父親の分からない子が生まれた事実が「神父人母」婚と結び付けられたことを言っているまでである。「処女懐胎」とは関係ない。この書評の初めの方で書評子は、本書には外向きの力と同時に「著者自身の内側に向かって屈曲してゆく自己凝視の方位へ引かれる力」も作用していると書いた。今言った「処女懐胎」もその一例である。本書の著者は「母の持つ子への異常なまでの深い愛情」に時たま目を曇らせかねないところがある。
『利己的な遺伝子』という本で評判になった生物学者リチャード・ドーキンスがこんなことを書いている。「私は、母親というものを、ある種の機械として取り扱っている。この機械の内部には、遺伝子が制御者として乗り込んでいる。そしてこの機械は、その遺伝子のコピーを増殖させるべく、能力の限りあらゆる努力を払うようにプログラムされているのである(『利己的な遺伝子』、日高敏隆他訳)」――およそ母子愛というものを考えるに当たっては、心の片隅に、世の中にはこんな考え方もあるのだと知っていた方がいいと思うのだが、どんなものだろうか。(野口武彦)


コブシ 葉コブシ
よく知られているように、コブシは毎年早春、サクラの花期よりも早く純白の花をたくさん咲かせる。葉が出るのに先立って、まず花だけ開くのもサクラに似ている。もっともサクラにはヤマザクラのような例外があって、昔は出っ歯の人を「山桜」といったものだ。「鼻より前に歯が出る」というシャレである。近頃は出っ歯そのものもあまり見かけなくなった。かつては小学校の1クラスに2,3人はかならずそうだったが。
だからコブシには花と葉をそろって付けるということがない。今回掲げた写真は、春先の花だけのコブシと、つい最近撮った葉コブシの両方である。同じ木がこうも違う外観になる。葉コブシの方は一見何もないように感じられるが、じつは葉の繁みの蔭にはスズメがじっと隠れている。やたら用心深いスズメたちは、米粒が撒かれるのをここでひそかに観察していて、撒き手がいなくなったと見きわめると一斉に姿を現して、米粒をついばみにかかる。警戒心は相当のものだ。
とはいっても、スズメの気質は棲みついた場所でいろいろらしい。聞いた話だが、さる旧家の老夫婦のところへ訪れるスズメはたいへん礼儀正しく、餌の米粒を食べた後、ベランダのガラスを嘴でコツコツつついて感謝の意を表してから飛び去るそうだ。ホントカネ。でも、最近世の変化は著しいから、スズメにもこういう突然変異種が出てもおかしくないかも。
わが家のコブシは、実をいえば二代目である。初代は、1995年の神戸大震災前の木だった。庭の土質が悪いせいか、植えてから何年経っても発育不良で、年にせいぜい十数輪の貧弱な花しか付けなかった。それが地震の翌年、見違えるような姿で満開になった。枝という枝に蕾が出て後から後から花が開き、最盛期には枝付き燭台から真っ白な炎が立ちのぼるような勢いで咲き誇ったのである。まったく溜め息が洩れるほど旺盛な生命力の謳歌だった。あの木が一世一代の晴れ姿を見せたのは、マグニチュード7の激震の影響だろうか。それとも、ありえないことだが、翌年、災害復興工事のためにり倒される運命を予感したからではないかと考えたくなる。
植物学者の説によると、木が一度にたくさんの花を付けるのは、自分という個体の消滅を察知して、種族保存のために多量の種子を残そうとするからだそうだ。最近は、リチャード・ドーキンスの『利己的な遺伝子』以来、生物の種族保存本能の存在へは疑問符が付けられているようだが、ともかくあの花の咲き方は尋常ではなかった。子孫を残そうという執念には凄味さえあった。コブシの木にはある種の予知力がそなわっていると信じたくなるほどだった。
その後、三田(さんだ)方面へ向かって芦有道路(ろゆうどうろ)を走っていた時、六甲山中にコブシの自生林があるのを見つけた。毎年、春先になるとその場所まで出かけて行って、まだ緑の若芽も生え揃わぬ遠見の山林の一部に純白のほの明かりが輝き出るのを見届けたものだ。
坂口安吾に『桜の花の満開の下』という美しい小説がある。その一節はこうだ。
「昔、鈴鹿峠には旅人が桜の森の花の下を通らなければならないような道になっていました。花の咲かない頃はよろしいのですが、花の季節になると、旅人はみんな森の花の下で気が変になりました。できるだけ早く花の下から逃げようと思って、青い木や枯れ木のある方へ一目散に走り出したものです。」
そして安吾は、この小説の主人公である変に淋しがりやの山賊のことを語りはじめる。この山賊は一人の美しい女を自分のものにするために女の夫を殺したほど残虐な男であるが、「こんな男でも桜の森の花の下へくるとやっぱり怖しくなって気が変になりました。そこで山賊はそれ以来花がきらいで、花というものは怖しいものだな、なんだか厭なものだ、そういう風に腹の中では呟いていました」と。
なぜ桜の花の下はそんなに怖いのか。男が桜の花の下でこの場所特有の「絶対の孤独」を感じるからである。くわしくは、野口武彦のエッセイ「花かげの鬼哭(きこく)」(筑摩書房『作家の方法』所収)を参照されたいが、この孤独感の根底には「桜の木の下には屍体が埋まっている」(梶井基次郎「檸檬(レモン)」)という感覚とも通い合う深層心理的な魂の断面が覗ける。やっぱり満開の桜の根本には、死体とか血染めの衣服とか骸骨とか、何か不気味なものが隠されているに違いない。
それにひきかえ、満開のコブシの下には何も不吉なものが埋められているような気がしない。もし何かが埋まっているとしたら、ごく平和的に何代も過ごしてきた先住民の土器ぐらいなものだろう。 (野口武彦)
3月26日の記事で「わが仮想読者」という小文を書いたところ、意外に反響があり、「『畸』の思想」と題したメールを頂きました。「思想」はちょっとオーバーのように思いますが、悪い気持はしません。メールを下さった方――「畸」のKにちなんで以下K氏と呼びましょう――は、「畸人」をもっぱら「半端者、異端者、余計者、社会不適格者」といった系列に連なる人種とお考えになっているようです。御本人はそうであるかも知れず、多少ヒトを巻き添えにしてくれるなという感じがしなくもありませんが、まあたしかに、「畸人」には「奇人」であるような一面がないとはいえませんから、これはこれでよしとしておきましょう。
少なくともK氏は、自分は「健全、正統、完全、無欠」であると思い込んで一生を自己満足して暮らす人々よりはまともに生きているわけです。拙老はどちらかといえば、一風変った人士の方にエールを送りたいタイプです。
しかし「畸」と「奇」とがごっちゃにされ、混同されるのも無理はありません。「畸」がもともと「田をいくら等分しても割り切れずに余る土地」を意味したことはすでに申しましたが、両字の根本的な意味成分になっているのは「奇」という声符であり、この形声で作られた文字に崎、倚、綺、錡、琦、寄、羈、剞、猗などがあります。どれにも共通して、「めずらしい、はみ出した、目立つ、不安定な、特別の」といった一連のニュアンスが含まれているといえます。同じ才能でも「奇才」と「英才」とではだいぶ扱われ方が違うのです。
そんなわけで、自他共に奮い立とうという趣旨から次の連作口吟を「畸のエロス」と名づけることにしました。「小序」付きです。K氏にも特に異存はありますまい。
《畸は奇にあらず。割っても割っても割り切れぬ余りの田をいう。ただの変わり者ではない。常識では間尺に合わぬ余計者なり。ひょっとして何か未曾有なものが育つ場所かも知れない。》
♥畸の者は哀れなるかな人らみな目をそばだてて袖を引き合う
♥畸の者ははれがましきぞ人らみな目を丸くして遠巻きに見る
若き日を思い出して
♥なりなりて余れるもののわれにあり人目つつしみいゆきはばかる
♥なりなりて余り出でたる悲しみにやすらい知らずいつも人恋う
♥割り割りて割りつくせりと思うにもなお余りあるわが身なりけり
畸の古訓はアラタなり
♥いかにせん畸の字のヨミは荒田なり余りて荒れしわが身なりけり
♥侘びぬれば荒田に憩う白鷺の姿よきにも涙こぼるる
ここまで書いたところに熊本地震のニュースが飛び込んで来ました。初めは、神戸の地震や東北大地震と比べて軽く見ていましたが、報道が続くにつれて、これはオオゴトだと本気で思うようになりました。余震がいつまでも連続するのは先例があることです。しかし、地震規模が逓減するどころか増大するのは異例です。尋常ではありません。案の定、初めのM6強の地震の後にM7・3のものが起こるに及んで、これを「本震」とすると判定が訂正されるに至りました。範囲も徐々に他県まで拡大しつつあります。被害箇所はすべて「別府‐島原地溝帯」の延長上だそうですが、われわれにはまた、日本列島についての常識が揺すぶられる時期が訪れたようです。
熊本城がテレビに映っていました。天守閣の瓦は落ち。石垣は崩れて惨憺たる姿でした。明治10年(1877)の西南戦争の時、西郷隆盛軍が攻め落とせなかった天下の名城も自然の威力には勝てなかったわけです。10年ほど前、取材に行ったのを思い出します。この城はまた、その前年の明治九年(1876)、神風連(しんぷうれん)の乱で主戦場となった場所です。神風連というのは、明治の文明開化に反対して蜂起した国粋主義者の一団です。その欧化主義ぎらいはまことに徹底していて、電線の下は頭に扇をかざさなければ通らなかったと言われますし、熊本城で師団兵と戦闘した時も夷狄(いてき)の武器である銃砲の使用を拒否して、そのためにほとんど全滅したほどです。この人々などは、正しく時代に畸なる者の代表格といえましょう。
ですが、拙老がもっと心を惹かれるのは、時代はちょっとだけ早く、明治3年(1870)に世を去りましたが、この神風連の精神の父と仰がれる林桜園(はやしおうえん)という人物です。桜園は間違いなく「畸人」です。その思想が異色であっただけでなく、容貌も魁偉(かいい、大きくて立派)だった。鼻が異様に高くて眼光鋭く、下唇が垂れ下がって頤(おとがい)を蔽っていたという異相でした。時々独り言をいうので、人々は先生が神と話をしているのだと噂したそうです。誰もがこんな風に一目でそれと知れる「畸人」であるとは限らず、一見すると平々凡々たる顔付きだがどこかヘンだという人もいます。
♥畸なるとは片ほにあらず真ほでな片端なれども片輪ではなし
♥畸なるとは世の常ならず世にそむき数まえられぬ身にぞありける
♥畸の人を変わり者とな見まがえそ世をうれたみて嘆く仁なり
♥畸の人はヘンコ片意地変わり種世を拗ねてこそ生くるなりけれ
♥畸の人は奇妙奇天烈(きみょうきてれつ)屁の河童世とさかさまにますぐなりけり
神風連のことは小説『天(あめ)の浮橋』に書きました。(『不平士族ものがたり』所収、2013、草思社)―――――野口武彦

カメカメハ王朝の盛衰
足が立たなくなってから、拙老の行動半径はほんとうに短くなりました。何年か前までは近所をよく歩いたものですが、最近はさっぱり外へ出なくなりました。それどころか、世界は手の届く所にある書物と眼の前のパソコン画面にしかありません。ロレツもうまく回らないものですから、電話も自粛しています。蔵書量は多い方だと思いますが 、書斎にも書庫にも歩くのが難儀なのでつい足が遠のきます。
そんなわけですから、今回の写真は、介護保険のおかげで我が家に来て下さるヘルパーさんに撮って来てもらったものです。ヘルパー派遣センターから我が家に来る道筋に、宮川の河口付近を通り掛かるとこういう風景が見られるそうです。写っているのは最近やたらに殖えたミドリガメで、日本固有種ではありませんが、旺盛な繁殖力を発揮してすっかり主人顔をしています。古来「亀は万年」というくらいですから、今後きっと長生きするでしょう。(ミドリガメの寿命は野性では3百年あるそうです。)
年を取ると不思議な能力が身に付きます。ただボケるだけではないようです。その一つが、古い記憶を鮮明に蘇らせることです。老人は昨日今日の出来事は端から忘れるけれども、幼時に起きたことを正確に思い出すと言います。それも未生以前の日々にさかのぼって記憶が再生できるのです。ちょうど近頃性能のよくなったドライブレコーダーが、事故が起きた時点より過去の時間のシーンを再現できるのと似た仕組みです。メカニズムはよくわかりませんが、それと同じ原理でしょう。未生以前の記憶のことですから、わが生誕の何年前、何十年前、何百何千年前の事象でも構わないわけです、写真の亀たちは1万年前を知りますまい。しかしこの原理によって、太古の昔、宮川がまだ現在の形でなかった頃の地形も非在の記憶として見えるはずです。錯視・幻視・妄誕のたぐいだと笑われるかも知れません。しかしこういう視像は老来拙老の身に付いてきた新しい光学装置であることは間違いのないところです。
芦屋に象が住んでいた頃――今から7万年前~1万年前の最終氷期すなわち更新世(かつては洪積世といった)終期――が終わり、完新世(沖積世)になると、今の阪神地方の山と海では大規模な地殻変動が起こりました。「六甲変動」と呼ばれる地形形成運動です。山の方では、六甲山地が隆起し、この高地から流れ下る住吉川・芦屋川・宮川などの河川群が山地を削り、山麓に扇状地を形成しました。海の方では、現在の芦屋市域北部にまで広がっていた古大坂湖が――縄文海進に伴って――紀淡海峡から海水が流れ込んで古大坂湾になりました。今は亀のいる現宮川もその時分にはいわば「古宮川」として盛んに暴れていたことでしょう。
宮川は、昔「打出川(うちでがわ)」「呉川(くれかわ)」などと呼ばれたこともあるそうです。今日打出天神に合祀(ごうし)されている金毘羅宮(こんぴらぐう)があったのでこの名が付いたとも、中流に芦屋神社があるからだともいい、説はいろいろあるようです。かれこれ40年ほど前、拙老がこの辺に住むようになった頃は、西から天井川(てんじょうがわ)・芦屋川・宮川・夙川(しゅくがわ)と順に並んで海(大坂湾)に向かって南流する川筋の一本であり、大雨の時など水面が膨れ上がりましたが、たいして荒れる川ではなく、まあごく普通の川でした。時には壊れた安楽椅子などが投げ込んでありました。この辺の海岸は、かつては白砂青松の海水浴場だったそうですが、拙老が芦屋の里に居を構えた時分にはもうそんな面影はありませんでした。阪神国道からちょっと南下すれば黒ずんだ砂浜にぶち当たったのを覚えています。
昭和44年(1969)に芦屋浜の埋立てが始まってから、様子がだいぶ変わりました。海が遠ざかって行ったのです。海とこれまでの海岸平地の間に芦屋浜シーサイドタウンやら芦屋中央公園やらが割り込んで陸がそれだけ広くなりました。宮川の川筋もつまりその分延長したわけです。この一帯には新しい人種のホームタウンが開けましたが、水辺の小動物たちにも新たな環境の出現でした。
写真で川岸の石を占拠しているミドリガメの本名はミシシッピーアカミミガメというそうです。外来種です。えらくのんびりしているようですが、水面下では在来種と激しい生存競争を繰り広げているのかも知れません。でも、宮川の写真を撮ったあたりは淡水と海水が入り混じる汽水域だそうですから、ミドリガメには最適の生存条件なのでしょう。河口ではボラも釣れます。新種生物のコロニーができたわけです。
写真のキャプションに使った「カメカメハ」という語句は、十九世紀にハワイを統一した「カメハメハ王朝」のたんなる語呂合わせです。日本で明治維新が実現した1686年にはカメハメハの後継者クラカウア王のもとでハワイ王国はまだ健在でした。
徳川旧幕臣の榎本武揚は艦隊を率いて江戸湾を脱走します。そして結局、北海道に「箱館共和国」を樹立して明治政府に抵抗するわけですが、その前に榎本艦隊がまだ仙台にいて奥羽越列藩同盟の敗色が濃くなっていた頃、徳川旧家臣団を連れてハワイに来ないかという話が持ち込まれたことがあります。榎本はそれを断って、北海道で開拓と北方警備に当たるというコースを選び、箱館に向かって北上したのです。こういう歴史の曲がり角では、歴史の「もしも」も決して抽象的な確率ではなく、麻雀でいえば国士無双で上がり損なったぐらいの惜しさで感じられます。武揚のチョイス一つでは面白い結果になっていたでしょう。日米関係も今日の姿ではなかったと思います。
アメリカザリガニ、セイタカアワダチソウ、シーバスなどの例のように、外来種が日本の生態系を変える度合いもかなり違っていたでしょう。

高橋敏『大坂落城異聞』 岩波書店
東京はいざ知らず、こちら関西の地では、「大坂落城」の悲劇はいまだに人々を感奮させてやまない情動的喚起力をそなえている。豊臣氏を滅ぼした徳川政権への憎悪は一種の遺伝形質として現代にまで持ち伝えられ、大阪人の東京嫌い・中央政府への根強い反感・地方主権主義・ポピュリズムの母胎になっている。「大坂落城」はそれら複合的な感情の象徴なのである。
かねて歴史の本道から一歩裏街道に踏み込んだ独特のスタンスで、『国定忠治』『清水次郎長と幕末維新』『小栗上野介忠順(おぐりこうずけのすけただまさ)と幕末維新』などの仕事に取り組み、幕末史に立体的な深みを与え続けている高橋敏(さとし)氏の近著『大坂落城異聞』は、江戸時代を通じて徳川政権から出版を禁止されながらも、「口承、伝承の非文学の世界に受け継がれ」てきた稗史(はいし)――正史が公認しない民間伝承による歴史――を読み起こした力作である。
では、正史から黙殺された「大坂落城」の稗史では、どのような事柄が語り継がれていたのだろうか。本書はそれを4つの章に分けて読みたどる。第1は、落城以後行方知れずになった大野治房(おおのはるふさ)のその後。第2に豊臣秀頼存生説。第3に大坂夏の陣の戦没者の慰霊さまざま。そして第4に、実録『厭蝕太平楽記(えんしょくたいへいらくき)』の世界で締めくくる。この「実録」は。じつをいえば、秀頼が後藤又兵衛・真田幸村・長宗我部盛親ら(現実にはいずれも討死したり刑死したりしている)に助けられて大坂城を退去し。島津義弘に身を寄せて捲土重来(けんどじゅうらい)を期するという架空の戦史である。
今は遠い昔になったが、半世紀も前の1960年代、東京には「かたばみ座」という小芝居の一座がまだあった。小芝居とは、江戸時代、中村・市村・森田の「江戸三座」と呼ばれた大劇場以外のいろいろな芝居小屋で演じられた歌舞伎劇の総称である。明治になってから大歌舞伎が「芸術」として洗練されたのに対して、小芝居の方は、江戸以来の庶民性を持ち伝え、他では見られない演(だ)し物や珍しい型を見せた。
「かたばみ座」には、板東竹若(たけじやく)・板東薪車(しんしや)・市川女猿(じよえん)・市川門三郎といった役者たちが生き残っていた。みんな相当な老優だったが、いずれも芸達者でしかも大車輪で熱演したから、観衆は滅多に見られないコッテリした芸風が楽しめた。たとえば『近江源氏先陣館(おうみげんじせんじんやかた)』の8段目、通称「盛綱陣屋」。戦国の習いで佐々木盛綱・高綱兄弟が敵味方に分かれて戦う悲劇である。
モデルは大坂夏の陣の当時豊臣方・徳川方に分かれた真田信之・信繁(のぶゆき・のぶしげ)兄弟である。(信繁は真田幸村の本名だ。)高綱は戦場で討たれたと見せかけて味方を欺こうとする。陣屋に持ってこられた高綱の首は贋首だったが、囚われていた高綱の実子小四郎は、敵を欺いて本物と思わせようと刀を腹に突き立てる。子役が腸を掴んで苦悶する姿は残酷なまでにリアルだったし、それを見て高綱の謀略を見破りながらも骨肉の情に引き裂かれて苦悩する盛綱の思い入れが凄かった。あんな風に顔面筋肉を総動員する表情作りは、お上品な大歌舞伎ではゼッタイに見られない芸だった。残酷と血まみれの表現主義そのものの舞台だった。
そこでは自己の悲惨さ、被虐性を過激に誇張する怨念の旋律が奏でられ、著者も強調する『大坂夏の陣屏風』――その凄惨な描写は、よくピカソのゲルニカになぞらえられるという――とも通底するものがある。勝ちに乗じた徳川勢は敗兵の首を1万数千級切りまくり、略奪・婦女暴行はやりたい放題という地獄図絵を繰り広げた。

https://www.google.co.jp/search?q=大坂夏の陣屏風 より
(もちろん、この画面には良識の検閲フィルターが掛かっている。本当に酸鼻をきわめるシーンは、描かれなかった次の場面にあるだろう。)
このように歴史の巨大なローラーに轢き潰された人々の声なき怨嗟の叫び、無告の訴えは後世に届かないのか? もし正史がそれをよく伝えないのだったら、そも正史とは何ものぞ! ――著者高橋氏は、ここで一種の義憤・公憤につらぬかれて稗史の世界に目を向ける。正史の落丁に着眼することにより、いわば落丁の空白をニッチとして活用し、そこに稗史の胚芽を増殖させるのである。
第1章では、正史が「不当に姦悪な愚物」にしている大野治房像に、著者は新発見の史料――治房の軍令状――を対置し、「別れ別れとなって転変、伝えられたものが400年のタイムトンネルを抜けて、今ひとつに合体」させる。だが著者の主たる関心事は、正史には無視された治房の妻子・一類の探索・処断の顛末を、稗史の中に求め、やがてこうした「子孫の物語」に新たな稗史ロマンを敗退させる構想と見受けられる。果たして第2章以下では、「秀頼生存説」を軸とする一連の大坂落城後日譚シリーズがそれぞれに展開されることになる。正史ではもちろん落命、一子国松はとらえられて斬首されるが、稗史では、国松と秀頼の息女霊樹院は細川家に庇護されたという伝承になる。第3章では、塙団右衞門(ばんだんえもん)・薄田隼人(すすきだはやと)・真田幸村・後藤又兵衛などの慰霊の記録に言及される。これが次章における豊臣家再興幻想の伏線と位置づけられていることはいうまでもない。第4章で取り上げられる『厭蝕太平楽記』の登場で、文字通り「稗史が正史を喰う事態が起こった」のである。何しろこの架空の実録では、首を斬られた国松は実は替え玉であり、秀頼一類は薩摩に徳川政権への永遠のアンチテーゼとしてサバイバルするのだから。
高橋敏氏は、「大坂落城」の異聞の息の長い伝承を、「大阪の生んだ江戸の徳川の権威に対するアンチテーゼ」「大阪の原点を豊臣の時代に求め、徳川の支配を関東からの闖入者と揶揄する、大阪の地域住民の本音」と見ている。その通りであろう。しかし拙老としては、著者はやはり歴史学者なのだなあという感慨を禁じ得ない。氏は、芸の下地が何といっても式楽なのである。
高橋氏は「表の正史と裏の稗史が棲み分け状態で共存していた」といっている。表と裏とは、正と奇・陽と陰・明と暗といった一連の対概念と類似のカテゴリーであり、けっきょくは水平軸上にあるように思われる。これをいっそ垂直軸に置き換えることはできないものだろうか。正史と稗史は,うまくいえないが、意識と下意識の両界に分かれて「深さ」で対立するものではないのか。
何だか言いがかりを付けたようで気が引ける。スミマセン。ともかくも拙老は、歴史学者ではないのが勿怪(もっけ)の幸い、もし寿命が 許してくれるならば、稗史にもっとズカズカ踏み込み、これと一緒になって正史を踏み荒らす蛮勇を振ってみたいものだと思っている。
このホームページを開設してからかれこれ5ヶ月になります。週に1度の更新というペースで進めてきました。これからも、最低最初の1年くらいほこのペースを守ってゆくつもりです。
このあたりで一度、本欄がいったいどんな読者を想定しているかを確認しておこうと思います。そもそも筆者は誰に向かってものを言おうとしているのでしょうか。
ブログによっては読者の側の反応を受け取れる仕組みのものもあるようですが、拙生は高齢頑迷ならびにITリテラシイ皆無につき、それは遠慮させていただき、当分は勝手ながらモノクラシイ(monocracy)・システムでやらせてもらおうと思っているような次第です。このHPをどれだけの人が眼にしてくれているか。「アクセス数」なる項目を見ると、⒈ヶ月にだいたい2700ぐらいです。どういう人々なのでしょう?
拙生が意識している読者層にはだいたい3つのグループがあります。
第一に、拙生とほぼ同年齢の人々。60年安保を共にくぐりぬけ、20世紀後半から21世紀初頭へかけて発生した厄介千万な諸問題にぶつかって、立場はいろいろだったが、今になってみれば結局は一緒にジタバタしてきた世代的「同行(どうぎょう)」の皆さん。とはいえ、このグループは現在急速に人数が減りつつあります。つまり、多くの人がやがて「亡き数」に入ろうとしていることです。
第二に、かつて大学で教え――といっても、最後の卒業生がかれこれ20年前ですが――、今ではだいぶいい年になっているいわば年下の友人たちです。気心がわかるというか、拙生のクセも臭みも心得ていてくれ、清濁併せて受け入れてもらえるグループです。(甘いかな?)でも、拙生の言動のすべてを理解してくれているとは思いません。ナアナアの間柄で行くつもりはありません。たとえば、最近あまりにも桃色ではないかとの御懸念もあるようですが、別に御心配には及びません。
第三のグループは、本当をいうと、この人々がわがホームページが目途している真のターゲットなのですが、次のような仮想の読者です。あえてひとくちで形容するならネオ「読書人」のクラスです。
「読書人」という言葉には21世紀の昨今、どうも二十一世紀なりの新しい定義づけが必要じゃないかという気がします。
いちばん古い、というより古典的な意味では、この語は文字通り「書」を読み、科挙――清(シン)代までの官吏選抜試験――に応募した知識人を意味していました。 ほぼ難しい漢字が読める階級と同じ範囲の人間です。また最近の日本では『週刊読書人』という新聞が発行部数が減って悪戦苦闘しているようですが、このことがいみじくもわが国の読書文化の消長を物語っていると思います。日本で「読書人」といったら、専門書以外でもカタイ本を読む人のことでした。何をもってカタイとするかはいろいろでしょうが、読む人の側からいえば、自分の職業上・職務執行上必須の知識習得のため(いわゆる実用書)以外の「自己目的的な」時には「自己充足的な」――何なら「自己満足的」でもよい――興味を持つということが条件です。余計な好奇心といってもよい。昔は「物好き」という適切な言葉がありました。
近頃、若い人が本を読まなくなったそうです。従来、本から――それは活字からというのと同義語でしょうが――得ていた情報が電波とか電子文字とかの媒体を通じて、より手軽に迅速に頭に入るようになったらだと思います。ですが、それは結局得ようとするものが情報に過ぎないからではないのでしょうか。読書は情報を得るだけが能ではありません。たしかに実用書からは有用な情報が得られますが、普通、実用書を読むことを読書とは言いません。また、まさにその種類の情報こそインターネットの方が速いのです。読書がもたらすのは、控え目に申し上げますと、情報にプラスされた「なにか過剰なもの」です。つまり余計なものです。この過剰こそが本を読む楽しみでなくて何でしょう。
「畸」という漢字があります。「畸」とはまず、田をいくら何等分かしても割り切れず余る土地を意味しました。それが転じて余計とか過剰とか余剰とかいう語義が派生し、やがては常軌を逸脱した畏るべきものという意味にもなります。われわれが読書するたびに期待しているのはこの「畸」なるものではないでしょうか。読書人は独特の好奇心に満ちた人種です。好奇心とは好「畸」心に他なりません。
さて、ここでようやく先程わが「仮想の読者」と呼んだ新しいタイプの読書人のことに話を戻します。かりにネオ「読書人」と名づけましたが、実際にはこのクラスの人々はいつの時代にもいると思います。常に心の底で「畸」なる世界と遭遇したいと思っていながら、日常社会の慣性法則に従うのを余儀なくされているだけです。こういう人々は、たとえば「眼光紙背に徹す」という言い回しもあるように、読書がただの情報摂取であることだけにあきたらず、何か「畸」なるものを渇仰し続けるでしょう。
拙老は、これからいつもこのタイプの読書人を視野に置いてものを書き、またこれをわがHPの仮想読者として発信したいと存じますナンンチャッテ。