悲しいお知らせです。老妻芳子儀、去る9月25日に永眠致しました。生前のご友誼に深くお礼申し上げます。葬儀は、9月28日に家族およびごく親しい友人知己のみを集めて執り行いました。近々のうちに「偲ぶ会」を開こうと思っております。
拙老も故人もナマの感情を露呈することを好みみませんので、ここはむしろ淡々と御報告するにとどめます。
今から30年ほど前、ボードレールの”ma femmme est morte”(妻が死んだ)という詩句が妙に気になっていたことがあります。まさかそれが現実のことになろうとは思っていませんでした。今その語句は名状しがたい現実感をもって拙老に迫っています。
『悪の華』中に”Le Vin de l’Assassin”(鈴木信太郎訳では「人殺しの酒」)という詩編があり、冒頭の詩行は”Ma femme est morte, je suis libre!”です。「妻が死んだ。私は自由だ」とでも訳せましょうか。それにしてもlibreなる言葉は多義的です。「放縦」とも「解放された」とも「自由自在」とも「勝手次第」とも意味の幅が広いです。だから鈴木信太郎訳は「飲み放題」という訳語を補っています。
この詩人は言葉の多層性をたくみに生かしています。言葉の多義的な折り重なりが、詩中のje――歌主・句主のひそみにならって「詩主しぬし」と呼びましょう。詩的虚構の主人公です――が陥っている何とも言えぬ空白感・虚脱感・絶望感の複合を表現しているように思います。そして何よりもここでの”libre”は詩語ですから、表層の多義性よりも深層の音韻の響きに無意識のうちに支配されています。libre[リーブル]はivre[イーヴル](酔っ払った)と通い合うのです。libreは下層にivreを埋めています。この詩主は、妻を失った悲しみ(自由感の高い代償)を酩酊で紛らわしています。
拙老の回りには、拙老がまた飲み始めるのではないかと心配してくれる向きもいます。が、以上をお読み下さったら分かると思いますが、拙老は大丈夫です。これから一人で亡妻と二人分しっかり生きます。 了

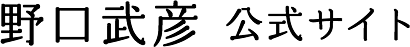
お悔みを申しあげます。なんとも言葉がありません。連句が滞って、なにかあったのではと心配しまておりましたが。
奥様には何十年か前に大変お世話になりました。気にしていた借りたものも返せず、お礼もいえぬままになりました。
これからが大変でしょうが、くれぐれも体には気をつけてください。