世が乱れると連歌・連句が盛んになります。歴史的事実です。天変地異人妖が世界に跋扈ばっこして、人心不安・社会物騒・経済低迷・気候不順・悪疫蔓延・手元不如意・お先真っ暗と不景気な類語ばかりが連なる昨今の時代が乱世でなくて何でありましょう。すなわち、連句の時代到来です。
こんな時代、人間関係は暗がりで見知らぬ奴とすれ違うようなものです。得体が知れない、気味が悪い、どんな害意を持っているか分かったものじゃない。そんな時、もし連句の応酬ができたらどんなにホッとするでしょうか。相手が自分と同じ文化を持っていることが確認できたのですから。すでに後三年の役ごさんねんのえき(1081〜1083)の時、二人の武人の間でこういう唱和がありました。衣館ころもだての戦に敗れて北へ落ちて行く安倍貞任さだとうに、追撃する源義家が「衣の館たてはほころびにけり」と下の句を詠みかけたところ、貞任はすかさず「年を経し糸の乱れのくるしさに」と上の句を返したという話が伝えられています。明らかに連歌になっています。
安倍貞任は先住アイヌ民族の血を引いているとされる北方の夷族だったのですが、義家はこの「異人種」と共通の文明を共有していることを感じたのです。つまり相手の気心がわかったのです。現代21世紀日本の乱世でも個々人同士がたがいに疎隔しあっている状況は歴史上の戦国乱世同然です。いや、ひょっとしたらもうそのサイクルに入っているのかもしれません。連句で共通言語を養うべき秋ときです。連句をやると相手の人となりがよく見えます。
さて、『囀りに』歌仙の初ウ7選評に取りかかりましょう。いつものように投ぜられた句案を紹介します。複数投句された場合は最終のものです。なお前句は「麒麟の兒らに刻まれる印」(里女)です。
⑴ 夏の月故宮の天を渡り行く 赤飯
⑵ 峰々をあますことなく夏の月 湖愚
⑶ サーカスの去って 残れる夏の月 三山
⑷ 月見草浮かべ飲み干す濁り酒 倉梅
連衆諸兄姉の狙いがだんだん定まって来ているので、座元はしごくご満悦です。みんな「夏」と「月」という基本的な条件はきれいにクリアーしています。ですが上には上があるものです。全体水準が 上がると、その条件をクリアーしただけでは不足だということになります。もう一つ注文が付きます。前句への付け筋をどれだけ意識しているかです。具体的には「麒麟きりん」をどう料理するかです。
難題です。皆さんだいぶ苦労されたようです。座元もハラハラしていました。でもこれが判断基準に加わった 結果、4句案のうち⑴と⑵をあまり悩まずに篩ふるいに掛けることができました。「麒麟」をあっさり無視しているように見えたからです。
⑶と⑷のどちらを取るべきか迷いました。まず⑶ですが、座元には或るカンが働いて三山子に「麒麟」を意識しているかとだけメールで問い合わせてみました。返事には「サーカスは熊象馬虎ライオンなど全てを連れ去ります。キリンはもともとサーカスにはいませんが、夏の月がキリンの幻影として空に残ります。無理ですか?」とありました。カンは正しかったようです。
⑷では倉梅子にえらく苦吟して貰いました。思案最中に野村克也さんの訃報が入って来たので、だいぶ目先が変わってしまいました。野村選手といえば「月見草」のボヤキで 有名ですが、実は句作の世界でも思わぬ広いものでした。「月見草」は夏の季語です。つまりこの言葉だけで「夏」と「月」がクリアーされますから、別に「夏の月」と吟じなくてもよいわけです。
「月見草浮かべ飲み干すにごり酒」の句案をメールで送ってくれた時のメモに「麒麟児=球児の路線を保持したくて苦戦しています。野球用語と月見草を両立しようとすると標語みたいになってしまう」「野村監督の現役時代は全然知らなくて、ぼやきのノムさんイメージが強いので、かつての麒麟児という事で…」と付言されていました。座元としては「麒麟児=球児」のアイデアが認知されているだけで大満足です。付け筋はちゃんと確保されました。しかし、ツキミソウを酒に入れて飲む場面には余りリアリティがありません。俳諧には俳諧なりのリアリティがなくてはなりません。だが言うは易く、実行は 難しい。座元にも「世を拗ねて日に背を向ける月見草」ぐらいの愚案しか思い浮かびません。ごめんなさい。
と、以上のような理由で『囀りに』歌仙初ウ7は、三山子の「サーカスの」と決定します。「囀りに」句順表12 次は初ウ8で夏の短句です。よろしく。 畢

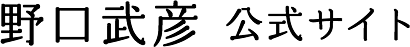
乱世、大変です。少し落ち着いたので投句。
打ち水するは人の手する熊 綺翁