歌仙36歩の歩みのうちには時々マジックワードのような語句が出現します。たまたま選んだ一つの言葉が、思いがけぬ普遍性を獲得してしまうようなことが現実に起きるのです。これも歌徳の一種かもしれません。
今われら一同は『囀りに』歌仙の興行中で、ようやく初ウ8に差し掛かったところ――前途遼遠――ですが、前句の「 サーカスの去って残れる夏の月」(三山)に倉梅子が「茅の輪くぐりて息ひとつ吐き」で応じました。句中の「茅の輪」が問題のマジックワードです。「茅の輪」というのは「夏越祓なごしのはらえの時、神社の参道に設ける、チガヤで作った輪」(ウイキペデァ)のことです。もちろん夏の季語です。
ここでいつものルール通り、この初ウ8候補に寄せられた投句を5つ紹介しておきましょう。
⑴ 今朝より蝉のこゑそらぞらし(碧村)
⑵ 夏草すがし深呼吸終ふ (湖愚)
⑶ 茅の輪くぐるは隣の和尚 (倉梅、初案)
⑷ 浴衣の帯を鞭にすおとと (赤飯)
⑸ アイスクリンをねだるひろめ屋 (里女)
いずれも前句の「サーカス」をそれが去った後の喪失感といったものを句想の公分母にしている、と思います。一々の褒貶にはわたりません。座元の関心は、今回は特に「茅の輪」の一語に集中しました。この語がどんなキッカケで倉梅子の念頭に上ったのか知りませんが、おそらくサーカスの一演目にある猛獣の輪くぐりからの連想じゃないかと思います。まさかお寺の和尚さんはサーカスに出演しません。作者にたずねたら、「見た目そのまま」という返事でした。どこかのお寺で「茅の輪くぐり」が催されたのでしょう。(たとえば京都大覚寺。)
実をいえば、この点が一句立ちの俳句(単俳)と俳諧連句(連俳)の重大な分かれ目なのです。単俳ではリアリティの根拠は自分の体験・実感に求められます。これを「嘱目即吟しょくもくそくぎん」といいます。現代俳句はおおむねこの方向です。しかし連俳の世界では、一つの語句はたんに人間の外部にある事物を指向する(外示する)のではなく、その語句に内在している意味のスペクトルの帯全体を想起させる(内示する)ことを重視します。「茅の輪」は、たんに特定の植物の葉っぱを編んだリングではなく、これに祈り篭められた民俗的・土俗的心情――災厄を祓う――がたっぷり沁み込んだ言語対象なのです。かっては疫病よけの呪具でした。
『囀りに』歌仙の初ウ8に「茅の輪くぐりて息ひとつ吐き」の句を得たのには、もしかしたら言霊ことだまのはたらきがあったのかもしれません。初案の「隣の和尚」を捨てて第五句を「息ひとつ吐き」に改めた推敲の背後には、ひょっとしたら、いま敷島のわが国に迫っている疫神のすさびを句主が無意識に感知したからかもしれません。「茅の輪」はやっぱりマジックワードでした。
というようなわけで、初ウ8は倉梅子に決定です。「囀りに」句順表12参照。
〽つくばねの峰に文待つ人もがな調べ合はせん世々の歌口
次は初ウ9,雑の長句です。ぜひ御投句下さい。 尾

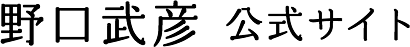
投句いたします。
押込の間に鍛えし大臀筋 里
家でつくねんとやることないし…的な。