『日本書紀』皇極天皇2年(643)10月のことですから、古い古い時代の話です。大化の改新(645)前夜の不安定な政情のさなか世上に奇妙な童謡わざうたが流行しました。「岩の上に 小猿米焼く 米だにも 食たげて通らせ 山羊やまじしの老翁をぢ」というものです。意味はチンプンカンプンですが、元は歌垣かがいの歌で、岩上に屯している若い女たちが、通りがかった白髪の老人をセメテ米グライ食ベニ寄ッテユキナヨとからかっているのだそうです。
だが実は、この歌には寓意があって「白髪の老人」というのは当時の権力闘争の渦中にいた皇族を指していて、その人物が政敵を恐れて山中に隠れた事実を諷しているということです。こういう風に、日本の古代史では何度も「童謡」が、権力者を憚って公然とは語りにくいこと、宮廷の醜聞、政治家の私行、闇に包まれた事の真相などを世に広める役割を果たして来ました。
古代社会だけはありません。それ以後の各時代も、それぞれに人々の気持を解放する手段や方法を作り出しています。中世の落書――応仁の乱時の「二条河原落書」など――が有名。江戸時代の狂歌・川柳。黄表紙に四方赤良よものあから作の『頭てん天口有あたまてんてんにくちあり」なんてお誂え向きの外題もあるくらいです。が、古代の童謡は特別ユニークです。子供になりすますというより、子供にしかない直覚的な洞見力がつらぬいているからでしょう。
もとより桃叟には少年の純真さなどありませんが、それでも陸游りくゆうの「老翁垂七十 其實似童兒ろうおうしちじゅうになんなんとし、そのじつどうじににたり」という詩句にはつくづく共感します。ましてや八十路をだいぶ過ぎたとなれば尚更です。以下の連作もそんな子供っぽさとしてお読み捨て下さい。
令和閑吟 〽なにともなやなう 人生七十古来稀 人生八十今はザラなり
耄耋ぼうてつ独吟 〽老い舌は今のわざうた心せよ亀に甲あり年に劫あり
弥生つごもり 〽明日こそはかけて聞きたし卯月鳥いつはりならぬ小夜の一声
卯月ついたち 〽嘘つくは天下御免の朝は来ぬコロナを飛ばす大法螺を吹け
三月三日紀念 〽宰相の首ぞ危ふき春の雪頃は万延コロナ蔓延 尾

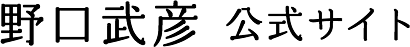
老謡いいですね。三月三日記念の記念がいい。
今の宰相の一世帯二枚のマスクは笑えます。
「口を封じる二枚のマスク」
というこでしょうか?