2021.01.14 木曜日
令三春吟半歌仙句順表.xlsx令三春吟半歌仙句順表
「野口武彦公式ブログ」が何とか復旧できましたので、歌仙興行も続行します。『令三春吟半歌仙句順表』を公示しますので、連衆諸兄姉のご応募をお願いします。
またそれに平行して、俳友グループの皆さんに『令三銘々精進会』へのご参加を呼びかけます。皆にレポートを提出してもらいたいのです:「芭蕉七部集の任意の巻から一組の付け合いを選んで自由に鑑賞し、100字前後にまとめよ。」
歌仙を何回か巻いてみて、諸君の作句方法に或る特定の傾向があるように感じた。自分の生活体験にある何らかのクライマックスを「私的=詩的瞬間」として切り取る発想をするのだ。それでは最短の詩形と考える「学校俳句」「秀才俳句」だ。連句 は違う。諸君もやってみて感じたと思うが、それは個々の付句を介して、或る集団的・伝統的な公共文化圏に加わることだ。連句は現代のような――時疫がいよいよその間を強めている――乱世に生きる人間の共通語なのだ。だから諸君の句作にも、たんなる生活体験のみでなく、すぐれた先人の製作に触れて得られる「詩的体験」を多く蓄積し、詞藻・詩嚢・歌袋・俳語目録をできるだけ豊富にしなければならない。
『芭蕉七部集』はその点でいい勉強になると思うよ。『日本の古本屋』などで検索すればいくらでも見つかるが、拙老は特に幸田露伴の評釈を勧める。注釈作業それ自体が 「文学」であることの好個の見本なり。また安東次男の評釈も面白い。クセが 強いが、それがまた魅力だ。この通知はブログでも公開します。「その望の日を」注釈

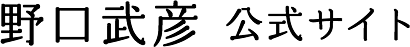
レポート提出いたします。
続猿簑より
笹の葉に小路埋みておもしろき
あたまうつなと門の書つき(書つけ)
こは付け「筋」の何たるかを知らず碧村師匠よりしごかれし頃に目を開かれし句にて打越より続ける大きなる景の突如卑近なる視点に引き込まれふと笑を催せる妙ありて所謂四句目振りの意やこの風ならんと合点し参らせそろ。