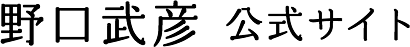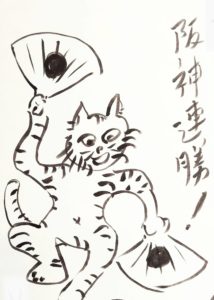[皆さんの声をお聞かせ下さい――コメント欄の見つけ方]
今度から『野口武彦公式サイト』は、皆さんの御意見が直接読めるようになりました。ブログごとに付いている「コメント欄」に書き込んでいただくわけですが、
同欄は次のような手順で出します。
トップページの「野口武彦公式サイト」という題字の下に並ぶ「ホーム、お知らせ、著作一覧、桃叟だより」の4カテゴリーのうち、「桃叟だより」を開き、右側サイドメニューの「最新記事」にある記事タイトルをどれでもダブルクリックすれば、その末尾に「コメント欄」が現れます。
そこへ御自由に書き込んでいただければ、読者が皆でシェアできることになっています。ただし、記入者のメールアドレス書き込みは必須ではありません。内容はその時々のブログ内容に関するものでなくても結構です。
ぼくとしては、どういう人々がわがブログを読んで下さっているのか、できるだけ知っておきたいので、よろしくお願いする次第です。以上
2024-04-13 |
日暦,
書窟,
桃叟だより⑴2026年4月日、大蔵八郎氏への私信(『彰義隊士の手紙』)の採録:
しばらくご無沙汰してしまいました。実は拙老このところ体調不順の気味あいで、やむなく病院の門を叩いたところ、年齢相応に座骨神経痛が出ていると言われました。やたら薬をのまされて閉口しています。何しろ眠くて叶わない。これまでなかったことですが、最近パソコンに向かいながら眠り込んでしまったらしい。情けないことです。
また此度は御貴著の御贈呈にあずかり、いつもながらのご熱意に感服すると共に大いに羨望の念を禁じ得ません。貴兄がお持ちの歴史への関心あるいは執心のご根底には、いわば徳川王党派固有の歴史弁償の意欲が感じられますが、それ以上に拙老が感じ入るのは貴兄が彰義隊の史実の顕彰をとば口として――単に僞史の混入・竄入の摘発にとどまらぬ「歴史の正丁」とでも言うべき界域ににじり寄ろうかとしているように見えるからです。
だいたい拙老は文芸評論バタケの人間です。それが柄にもなく、いや憶面もなくというべきか、歴史事象の方面に口を挟みたくなるのには、よくせき史学と文学の間に未知のまま取り残されている広大な空白が意識されているからかも知れません。幸いにも次の拙著の公告が許される秋口までの間、少し余裕があるようです。この貴兄とのやりとりをわがブログに転載するのをご許可願えるでしょうか。
⑵こころよく採録をご承認頂いたので、書簡文をその侭、ならびに新規返信を次に掲げます。
尊兄はまず、迂生が不用意に繰り出した「歴史の正丁」なる用語の曖昧さ(不適格さ)をズバリと指摘されます。たしかに、「歴史の正丁」という概念は存在しません。存在するのは「乱丁」「落丁」であり、そこに出現するのが歴史の空白です。よく「歴史の謎」ともいわれます。それは必ずしも歴史叙述につきまとう必要悪的な事実の朧化――史実の誤解・曲解・歪曲・中傷・誹謗・非難(いわゆる「ヘロドトスの悪意」など)、善意による隠蔽・掩護・黙諾・看過――だけでなく、およそ人が歴史を前にしたとき、どうしても認めざるを得ないような自生的な暗黒点との遭遇です。おおむねは人知を越えた、想定外の、夢にも思わなかった予想外の結末が訪れることがあります。人々が苦しまぎれに「歴史の偶然」なるカテゴリーに押し込んで満足するような種類の出来事群が厳存しています。
歴史にはその全貌に限りなく接近できる――理念にすぎないかもしれないが、いわば歴史記述の測度が100パーセントであるような――「頁」すなわち「丁」が想定されてよいのではないか。宇宙のどこかの図書館には、まだ誰の目にも触れていないそんな未読頁がひそかに蔵されているのではないか――というのが迂生の概念する「歴史の正丁」なのです。すみません。いかにも我田引水ですね。
事ほど左様に迂生には抜きがたい造語癖があります。自分でもそれと知りながら、造語群はたちまち僞手・偽足を伸ばしあって結び付き仮想の構造を作り上げてしまう。そこで話はだいぶ飛躍しますが、「相馬の金さん」のことになります。
貴兄もご自著『彰義隊士の手紙』p.552 以下で、「歴史のプロパガンダとフィクションを論ず」と副題して取り上げておいでのように、この人物は、岡本綺堂の彰義隊物の戯曲『相馬の金さん』(昭和2年)の主人公です。三田村鳶魚によれば、相馬金次郎にはモデルがあり、もともとは家禄百俵の御家人だったのだが、日頃から素行の悪い遊蕩児だったらしい。当時よくいた崩れた人間の一人だったようです。
綺堂の戯曲では、そんな崩れ御家人が「官軍」の兵士と口論になり、鉄扇で額を割られたとき、勃然として彰義隊に加わることを決意し、弟を連れて上野に入ってしまう。弟に告げたその理由は、「おれがこれから上野へ駈け込まうといふのは、主人の為でもねえ、忠義のためでもねえ、この金さんの腹の蟲が納まらねえ」なのである。そして上野戦争の敗亡の後、上野宮の御供をして東北に落ち延びようとするが、途中で突然何もかもいやになり、腹を掻き切ってしまうのです。「江戸っ子は思い切りが肝腎だ。おれはもう歩かれねえ。逃げらねえ。さあ、此ですっぱりとやってくれ。」――その言や佳し、です。
このいかにも性急せっかちな、あまりにも短絡的な、直情径行的な粗暴さ、オッチョコチョイ性の浅薄さと見えるものこそが、実をいえば金さんの身上で」なくて何でしょうか。自分の状況を「逃げられねえものを逃げたって仕様がねえ」と見切らせる眼力は、むしろ、戦場を一瞥するだけで勝敗を見抜くかの「戦局透視眼 クーデーユ」の発露だったのではないか。そしてこの時勢-地殻変動を全身的に感知する別製の能力は、徳川慶喜にも相馬の金さんにも分有されていた独特の歴史感覚ではなかったか。
ざっとこんな事柄が、迂生が「歴史の正丁」と名を付けてみたものの実体なのです。ごたごたしてすみません。いずれまたもっと問題を整理しようと存じます。今回はここまでで。
2024-04-01 |
お知らせ,
日暦,
桃叟だより
長いこと懸案だった近刊単行本の出版がやっと本決まりになりました。A5判の範型で、来たる読書の秋を期して一斉に店頭に並ぶ予定です。もっとくわしく体裁や内容を予告するつもりでしたが、版元の出版社の方から業界の慣わしについて釘を刺されましたので、その指示通りに事を運びます。版元と刊行月についてはしばらく伏せ、「2024年の秋めどで刊行予定」ぐらいに留めておいてほしいという注文でした。
桃叟には年甲斐もなく世間知らずなところがあり、従来の慣行には至って不案内ですが、まあ「郷に入らば郷に倣え」の原則に従います。現今の出版危機の情勢のもとで「紙の本」の不振のさなかに真正面からオーソドックスな編集方針を貫いて下さった版元さんのご英断には――本を出していただく立場からは、多少口幅ったい気持がしないでもないですが―御奉謝申し上げます。
本作中の芝居でいうなら、さしずめ『近江源氏先陣館』の「盛綱陣屋」の有名なセリフで、扇をぱっと開いて「褒めてやれ褒めてやれ」と絶賛するところです。
今はその出版社名も、刊行月も、版元のご要望に従って明らかにしません。一篇の表題についても箝口令が出ていますので公表することは差控えますがが、すでにこれまでいわば「問わず語り」風にだいたいの輪郭は漏らしてしまっていると思います。時代の舞台は幕末の大詰めで、「鳥羽伏見の戦」「歩兵」「旅役者」という三つのモチーフが三題噺の体ををなしている、とお考え下されば有難いです。
このような事情で、本作の出版はごく大雑把に「2024年の秋めどで刊行予定」としか公告できません。いずれ版元から発売日の発表が解禁され次第、天下晴れて公表しようと思っています。それから半ばは私事ですが、今年の9月25日は逝妻芳子の5回忌にあたります。これと本書の出版記念を兼ねた集まりを持とうとしております。スケジュールが定まりましたら、またお知らせ致します。以上。
これまでなかったことですが、ぼくの3o8枚の中編『旅役者歩兵隊』がいまだに出版元を見つけられずにいます。もちろん、作者の技量が編集者諸氏に認められなかったまでのことであり、その結論に文句を言える筋合いではありませんが、作者にとってはたいへん心外です。本作の企画が通らないことの背景には、最近の出版界の動向が大いに関係しているように見受けられるからです。
数ヶ月前の『産経ニュース』にこんな記事を見かけました。このところ出版業業界では、収益構造の急激な変化が著しいというのです:「顕著な例が講談社だ。2月に発表した通期決算(令和元年12月~2年11月)は売上高が前期比6・7%増の約1450億円で、当期純利益は50・4%増の約109億円だった。電子書籍は19・4%増の約532億円で、これにアニメ化などの権利ビジネスを合わせた収入は約714億円となり、初めて「紙」の売り上げ(約635億円)を上回った。「収益構造の変化がより一層明確になった」(野間省伸社長)格好だ。」
電子書籍の売り上げが「紙の本」を上回ったというのは、平たくいえば活字で印刷した本が読まれなくなった事実を示しています。世の中で、アニメつまり漫画・劇画が好まれる現状を反映しています。文字を読みたどる「文字言語」よりも直接目に訴えてくる「イメージ」の方が優先されるようになったのです。活字の本が売れなくなったのも道理です。
このように「絵の助けを借りずに言葉のみで理解し,想像の世界を広げることのできる読書行為の段階にあるはずの大人が読む」(紅野謙介「新聞小説と挿絵のインターフェイス」)ような現象は、わが国の文芸史上つねに間歇的に起きている事柄であり、嘆いてみても仕方がない。こんな御時世に生まれ合わせた運命を受け入れて、「文字言語」の法灯を点してゆくしかありません。
ぼくの『旅役者歩兵隊』もかりに劇画のノヴェライズの方式だったら――そういう才能の持ち合わせはございませんが――別に販売部の方から故障が出ることはなかったかも知れません。この一篇は、時期的には、慶応4年(1869,9月に改元して明治元年)1月6日、鳥羽伏見の戦に敗れた徳川慶喜が大坂城を脱出してから、同年5月15日、江戸上野山の彰義隊追討戦までの6ヶ月余り(䦌4月があったので)の期間を扱っています。主人公の江戸町人熊五郎とその仲間たちは、幕末の混乱期に歩兵隊に応募するが、あえなく敗戦。生まれつきの芝居好きから文字通り芸に身を助けられて旅役者の一座に化け、行く先々で芝居を上演しながらなつかしの江戸へ帰還するのです。
一篇は全6章で構成され、各章に作中で上演される歌舞伎芝居が一幕ずつ割り当てられています。一座が公演した都市と狂言通称と場面、および各章の枚数は以下の通りです。
旅役者歩兵隊章構成
発端『仮名手本忠臣蔵かなでほんちゅうしんぐら五段目』山崎街道40
二幕目 「伊勢音頭恋寝刃いせおんどこいのねたば」 桑名50
三幕目 「盛綱陣屋もりつなじんや」 名古屋52
四幕目 「弥作の鎌腹やさくのかまばら」 下田54
五幕目 「躄の仇討いざりのあだう5ち」 横浜8
大詰 上野山炎上58
本作の「発端」と「大詰」には二つの記念碑的な戦闘を描きます。鳥羽伏見の戦いと江戸上野の彰義隊殲滅作戦。どちらも江戸時代の終焉を実現した歴史上画期的な内戦です。二つながら有名な出来事であり、歴史的名辞としては周知の事項ですが、それぞれの実相はよくわかっていません。特に、260年間も維持された徳川幕府の政治権力が見る見る解体した決定的な6ヶ月のうちに何が起きていたかは、いまだに解明しつくされていない歴史の謎なのです。
この歴史上稀に見る一時期、政局の当事者たち――とりわけ旧幕府勢力側――が遭遇した政治密度の質量がどんなであったかは想像が付きますが、これまでの幕末戦史・戦記は、政治決断者たる慶喜が権力を放棄したことを述べるのみで、なぜ・いかなる算段をもってその結論に達したかまでは追及しないままです。ブラックボックスに入れられているのです。
『旅役者歩兵隊』の世界では、もちろんその領域は視野に入って来ません。熊五郎一座は政治的中央から遠く隔たった東海道筋――それも周辺の海路――をたどって幕末混乱期の日本をつぶさに味わいながら道筋を急ぎます。早く戻らないと住みなれたお江戸がなくなってしまう。そんな危惧がいつも念頭を去らないほど日本の変わり方は迅速でした。
一座は行く先々で当時の民衆に愛好された演目を次々と舞台に載せる。いずれもたっぷり敗者・弱者・不具者たちに与える苛烈な嗜虐の味わいで幕末頽唐の時代色を染め上げていた。そして江戸に帰り着いた熊五郎 一行は、幕末劇の記念碑的な最終幕――上野戦争にちょうど間に合うのです。この重要な政治史の一齣は、悲壮な儀式性さえ帯びて、江戸時代の掉尾を劇場的に飾っています。
ざっと眺め渡してみたところ、江戸時代から日本近代への時代交替は、それ以前の転換期に比べると、いまだにすっきりとは様式化されきっていないように思われます。様式化というのはこういうことです。古い時代の面影がしだいに薄れ 、新しい時代の建て付けが目鼻立ちを整える新旧入れ替えの手順が、型通りには進められていない。それまで日本史上の権力交替・時代の変わり目が生じたと、人々が認知する、万人が納得するに当たっては、そこに暗黙の了解があるものなのですが、その辺がどうも怪しいのです。
史実の優勝劣敗は人間学的には逆転する。政治的な勝者が文学的・美学的に敗北する・及びその逆という「定式」が出来上がる。たとえば「王朝」の世界では、全盛の藤原氏は天神(菅原道真)の摂理の前に滅び、「源平」の世界では義経に同情が集まって「判官びいき」の心情が生まれ、「太平記」の『忠臣蔵』では同じ言葉が塩冶判官(浅野内匠頭)に宛てられ、熊五郎が演じた『近江源氏先陣館おうみげんじせんじんやかた』も舞台を「源平」の世界に借りてはいるが、じつは 豊臣氏滅亡時に敵味方に分かれた真田一門の苦衷をテーマにしているといった具合である。そうした既判例に照らすと、近代日本史の総合的・最終的勝者の姿はいまだに確立されていない。きちんと「総括」されていないのです。
しかし日本の国情は、明治維新以後の150年を経るうちになし崩しに「近代」を実現してきたどころか、「超近代」へ突出しようという時勢にあることを示しています。日本社会は常には「前近代」「近代」「超近代」が」共存し、かつ互いにせめぎあう特徴がありますが、これら三つの位相を同一事象のうちに透視する視角は、将来に投じられる視線の中ばかりでなく、過去の歴史――たとえ幕府歩兵隊とか彰義隊とか――を視野に置いても働いているべきでしょう。これらの事象はどれもまだ歴史的過去に埋もれきっていず、将来にも何らかの布石たり得るポテンシャルを蔵しているからです。
――――編集者の皆様にお願い。ぼくの『旅役者歩兵隊』の刊行をお引き受け下さい。あまりくだくだしくは申しません。ただ首尾よく日の目を見た暁には、本作は「失われた環」にならずになるだろう、と多少胸を張らせて頂きます.妄言多謝。
御談話掲載の『時空旅人』を御恵送下さいまして有難うございました。御苦労なさったことと拝察しながら読ませて頂きました。拙生にも経験がありますが、あらかじめ成案を持っていて我の強い編集者を相手にするのは、なかなか気骨の折れるお仕事だったろうと存じます。学兄の言葉が「引用」あるいは「要約」されているカギカッコの部分にはいくつかかなり勝手な、編集者流の我田引水があるように見受けられます。
この雑誌の特集が「無惨絵」であることは、彰義隊に対する学兄と同誌編集部との微妙なスタンスのすれちがいを集約しているように思います。ことさらに異和をかきたてるつもりはありませんが、『時空旅人』誌がめざすところは歴史のスペクタクルの一画面、一齣、つきつめればヴィジュアル・グラフィックスであり、それが現今読書人の「歴史好き」志向と一致しているからのように感じられます。彰義隊は過去時制で完結した歴史場面にすぎないのです。その点、彰義隊はまだ歴史的過去に埋もれきってはおらず、将来に向かっても何らかの布石たり得るポテンシャルを蔵している――とおそらくはお考えの――学兄とは一線を画するのではないか。
ところで、本誌の誌面で、初めて御近影を拝見致しました。さすがは直参旗本の御末裔、みごとな「殿様顔」に感服することしきり。今後も何卒よしなに。謝妄言。
阪神タイガースの優勝で関西が沸き立っている。町を歩人々にもユニフォーム姿がまじり、商店では特別セールが始まり、ちょっとした祝典気分だ。大道をトラキチが闊歩し、ネコまでがトラにあやかっている。



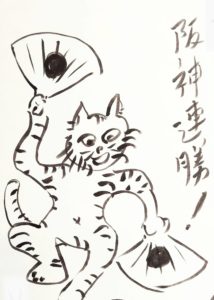
二つの世紀にまたがるこの38年間というもの、このチームはリーグの下位に甘んじ、人々の上から目線に耐えてきたわけだ。その屈従からいっぺんに解放されたのだから、嬉しさのあまり、道頓堀に次々と飛び込む若者たちの行列ができたのもわかる。
ところでこの低迷の38年間、主として阪神間の地域で、一つの都市伝説が広まったことを御存知だろうか: いつもテレビの野球中継の始まりを告げるテーマ音楽が鳴り響くや否や、そこらじゅうのネコが一斉に姿を消すのだそうだ。みな押入れやら縁の下やら物蔭にこそこそ隠れ、身を潜めていたというのである。タイガースが負ける度に飼い主が腹を立て、身近な飼い猫に当たり散らす――頭を叩く、尻尾を引っ張る、毛皮をこねくり回す、と散々な目に会うのを逃れるためなのだそうだ。とんだ災難である。
ではタイガースが勝ったらどうなるのか。同じことである。人間様は万々歳だろうが、ネコにとってはやっぱり受難の続きにすぎない。ネコはトラの仲間だと決めてかかり、戦勝をネコの身体で祝わせようとするのだ。いやがるネコに野球帽をかぶせる。猫背をまっすぐに引き伸ばしてバンザイをさせる。無理矢理握手を求める。祝祭と見えるが、じつは受難なのである。
それはさて置き、話は違うが、この度のタイガース優勝は、わが老宅には概して好ましい結果をもたらしている。わが老躯の介護に来てくれるヘルパーさん、トレイナーさんたちはいずれも?0年台の妙齢女性だが。土地柄でみなタイガースファンである。中には自称尼ヶ崎生まれという人もいる。
これらの人々がここ当分朗らかそうなのが有難い。来年はどうなるか、タイガース優勝がいつまで続くかどうかまでは分からないが、せめてわが天寿くらいの歳月は全盛期であってほしいところだ。 畢
2023-10-01 |
お知らせ,
口吟,
桃叟だより


〽許せかし名もなき草と呼びたれどほんとはわれが名を知らぬだけ
〽未練なと笑ひ召さるな八十路坂道に眼留むる花のいろいろ
〽老いらくの果てに迎えるトリレンマよだれと呂律紙おむつなり
〽煉獄の暑熱をくぐる曼珠沙華燃ゆる炎も涼しげに咲く
* * * *
今年の夏はいやに長く、また異様に暑かった。庭の小動物や植物たちにも異変が続々。蝉は鳴かず、蚊は飛ばず、バラは半ば枯れ、ほぼ全滅かと思っていたが、さすがにヒガンバナだけはその名に違わず、ちょうど秋分の日に地上に花芽を出しました。例年通りとはいきませんが、次々に花を開いてくれました。植物の生命力が気候変動に勝ったわけです。
そんなことがやたらに心嬉しく感じるのも、年齢のせいかも知れません。もうたいして寿命は残されていないから後はドウナトキャアナロタイでどうでもよいようなものの、やはり今の異常気象が一次的な変動にすぎないのか、それとも地球全体に生じている不可逆的な過程の始まりかは大いに気に掛かるところです。 了
2023-08-18 |
口吟,
日暦,
桃叟だより


今年の夏は異常に暑かった。小庭のユリも、連日の日照りに背丈だけがやたらにヒョロヒョロ伸び、おまけに台風7号の強風でポッキリ折れ伏すのじゃないかと心配したが、運良く無事に助かり、御覧の通り4輪も花を付けました。調べてみたら、これはどうやらタカサゴユリという品種が野生化したものらしいです。
このユリはもともと、球根を植えたものではなく、どこかから風が吹き運んできた種子が庭の土に居座って自然に成長したものです。ちょうど1年前のことでした(『芳子三回目のお盆に』参照)。だから桃叟には、これはただの花ではなく、亡妻のあの世での消息を伝えてくる年に1度の花信なのです。明るく花開いているという知らせです。
〽あの世から風がもてくる花だより今年もユリが安否知らせて
〽あの世からユリの便りは届きけりぼくも元気に生き延びてます
2023-07-30 |
口吟,
日暦,
書窟,
桃叟だより史論・史観・史眼
人間は誰でも各人各様の「歴史とは何か」を持っている。それぞれの歴史像にはもちろん個人差はあろうが、一つの時代社会は、よし画一的でなくてもだいたい統一された支配的枠組みで歴史を理解し、受容してきたといえる。近代日本の歴史思想は、概言すれば、明治以来の皇国史観が昭和のマルクス主義史観に押し退けられてゆく過程を大枠として進行した。対立軸をなしていたのは、わが国の歴史を縦貫する原理の源泉は何か――君主か平民か、という課問だ。近代日本の主要な歴史著述は、徳富蘇峯の『近世日本国民史』にしても、大佛次郎の『天皇の世紀』にしても、いずれもこの択一の近傍にあった。
現今のいわばポスト昭和期は、あれこれの歴史原理のどれかを選択するのでなく、そもそも「原理」というものをまるごと拒絶するのが特色である。いっそ「没・歴史原理」の時代と呼びたくなるような季節が到来している。極端にいえば「ゼロ史観」の時代なのである。謡曲『卒都婆小町そとばこまち』にある前仏は既に去り、後仏は未だ現れない「夢の中間ゆめのちゅうげん」という詞章がぴったりの状態だ。
およそ歴史というものに関心を持っている人々の間では、前世紀末葉の1990年代から一種のIT革命が展開した。世界的な冷戦構造の終焉と勢力の遠心化・分散化という大情況の進行とコンピューターの普及が相俟って、歴史学の「グランドセオリー」を退場させると共に、①大量な記録のデジタル化、②史料アクセスの簡単化、③史料の相互参照、④情報処理のスピードアップなどの諸作業が身近になったのだ。その結果、これまで歴史の《空白域》だった領域・部分が続々と埋められている。従来支配的だったイデオロギーや原理決定論の歴史への持ち込みが排除され、代わりに精密な実証研究が重んじられるようになり、歴史の見直しが行われた。原理的な思考は観念的な思い込みとして斥けられ、「史実」の掘り起こしが盛んになり、通俗的な歴史小説の世界でも「リアルな」という形容句が流行しているくらいだ。
だいたい以上が、『将軍の世紀』を山内昌之氏に構想させるに至った歴史思想の季節の概況なのではないか。根底に広がるのは、索漠たる歴史意識の《無主状態》である。いかなる歴史原理も《大文字の物語》として否認され――だから進歩史観も頽落史観もない――、そこにはただノッペラボウな時間の経過と小文字で記される事象の継起があるだけだ。――こんな精神風景に耐え抜くには、歴史家はよほどタフであるか、それともまったく新しく人心を賦活する歴史のヴィジョンを切り拓くかしなければならない。山内氏が果敢に引き受けたのは、こうした疲れ仕事であったと思われる。
慶長8年(1603)に樹立され、慶応3年(1867)に「大政奉還」の結果解体する徳川幕府は、徳川将軍を頂点とする国家支配を前後3世紀にわたって持続した長期政権であった。著者は、これを三つの世紀が一つの「束になった世紀」ととらえ、《将軍の世紀》と命名する。もともと「将軍」とは臨時に朝廷から任命され、戦地に派遣される武官職の名にすぎなかったが、徳川家康の就任以来、武士政権の主催者・軍事力の総覧者・事実上の国家元首などの地位を獲得するに至ったのだ。過去に面しては戦国時代の無政府状態を治めただけでなく将来に向いては 「グローバルな生存競争を生き抜く近代の基礎体力を準備した」という双方向性を具えていた。
しかしこの世界史にも稀な長期安定政権、いわゆるパクス・トクガワーナの世といえども、決して永久国家ではあり得ない。すべての有機組織が不可避的に蒙る「エントロピー増大の法則」――「物事は自然に乱雑・無秩序・複雑な方向に向かい、自発的には元に戻らない」という理法にしたがって衰退への回路をたどる。しかもこの場合、徳川国家に長期的な安寧と繁栄を保障するとして奨励された治策そのもの――たとえば商品生産の増大・貨幣流通の広域化etc.――が反対物に転化したことに起因する。家康の江戸開府はいわば天下の「大政」を受託したのだったが、その260年後、慶喜はそれを「奉還」して江戸国家に終焉をもたらしたのである。
初代家康から15代慶喜まで全63巻、上巻735頁・下巻760頁というこの大著を逐章的になぞることはできないので、以下ではトピックを各代将軍の諸事蹟中、徳川国家の《権力――維持――衰亡》という大筋のプロットに当て嵌まる問題点に限定して眺めてゆくことにしよう。
本書の特色として目立つのは、著者の史料博捜ぶり、広範囲にわたる文献への目配りである。第一に『オランダ商館日記』『風説書』など豊富な外国関係文書の活用。これら「外」からの目の導入は、ともすれば閉鎖的に自足しがちな国内の判断を相対化する思いがけない視角をもたらすことはいうまでもない。第二に、政治的要人たちの公生活の記録のみならず、側らで書き残された日常の記録・メモランダム、時にはゴシップめいた私事・小事・秘事のたぐいのあくなき繙読。たとえば『遠近橋をちこちばし』は、水戸藩の徳川斉昭が藩主になるまでの激しい政争の記録であるが、中に混じっている斉昭の乱淫ぶりや男色趣味を窺わせる記載も目敏くキャッチされ、大状況・小状況が一つに落ちかぶさる歴史の機微を浮かび出させる。そしてもう一つ、ちょっと見では遠く離れていて、いかにも無関係であると思われそうな大名家記・権臣の政務記録・手控え雑記その他の援用がたくみである。それらはいささか乱雑に列記すれば、『肥後藩国事史料』・『南紀徳川史なんきとくせんし』・『京都守始末始末』(旧会津藩老臣の手記)・『中山忠能履歴資料』(公卿日記)・『休明光記きゅうめいこうき』(松前奉行の記録)などと枚挙に暇がない。これらの個々の記述を読み合わせると、そこにはいわば補助線が引かれて、人物や出来事の関係が新たな遠近法のうちに現れ出る。事件や事象間相互の距離、内部のからくり、物事の噛み合い方など、これまで朧ろにしか見えなかった幕末日本の全体構図がくっきり見えて来るのである。
こうした広範囲にわたる博引旁証、慎重な文献批判、相互照合の結果、幕末日本の進路を左右した諸事件はいくつも異なる角度から照らし出され、以前には隠されていた相貌を晒すことになる。人物と事件とを結んでいた思いがけぬリンクが突然見えて来て、歴史がなぜあの時ああ急速に旋回したのか、「不思議の勝ち」あるいは「不思議の負け」といった番狂わせがなぜ生じたのか、が問い直される。こうした問いかけの事例は特にもろもろの情勢(=conditions 諸条件)が束状に寄り重なる「第十一章 家茂」から目立って多くなる。まだ十分探索され切っていない歴史の薄暗がりに潜む未解決の謎の結節点がいくつもあるのだが、それらは氏にあっては、そこから内部に分け入って複雑に絡んだ糸目を解きほぐすべき綻び口なのである。
それらのうちから特に、寺田屋事件と生麦事件の二つが注目される。そのどちらもが幕末の時勢を急展開させながらなお真相不明の部分が多いというばかりでなく、この二つの出来事には隠微な因果関係が想定されており、両者相つながって歴史を動かしたと目されるからである。このような動態の背景には、著者の卓抜な人物眼がある。山内氏は、町田昭広氏の『島津久光=幕末政治の焦点』など近年の研究動向を視野に収めつつ、これまで実像をよく知られず評価も低かった島津久光の周辺を発掘して動きを立体化するのである。
といっても、久光の隠れた野望――極論すれば、徳川幕府に替わる島津幕府の樹立というような権力意志――が幕末情勢に底流する動力源であったとする単線的な史論はこの著者の取る所ではない。今ここにあるのは、一つの権力意志が他者と衝突し、せめぎ合うダイナミックな「場」であり、その意欲は他者との摩擦のうちに少なからず妥協変形せざるを得ない現実である。久光とその股肱たち――寺田屋事件・生麦事件に共通する当事者――が、みな開国と攘夷の両極の間に揺れるのはそのためだ。著者の史眼が光るのは、これら外見では矛盾撞着でしかない屈折した心情の奥で蠢いている関係者の真情を複眼的に見通していることであろう。そして氏は、この両事件を合わせ鏡のようなレンズにして久光という人物の真姿に迫ったのと同じ方法を用いて、身分や立場こそ違え、同一の「場」に轡を並べていた何人かの有為の人物に論じ亘ろうとしていたかに見受けられる。名前だけ列挙しておけば、大久保一蔵、原市之進、小松帯刀。
人間の歴史の大きな節目をなす政治闘争は、最後には権力闘争に圧縮され、権力闘争はけっきょく人事抗争に帰着し、究極は個々人の人間性がナマでぶつかり合う。著者が好んで口にする「歴史への畏れ」とは、時として歴史の表面に発露する超人間的な意志・真情・決断などから発するオーラに対して発される畏怖の念だろう。「歴史の謎」といわれてきたものは、必ずしも歴史叙述につきまとう必要悪的な事実の朧化――史実の誤解・曲解・歪曲、史家の意図的な異論・中傷・誹謗・非難(いわゆる「ヘロドトスの悪意」など)、善意による隠蔽・掩護・黙諾――のことばかりではない。およそ人が歴史を前にしたとき、どうしても認めざるを得ない自生的な暗黒点との遭遇である。記念碑的な歴史事象といえども常に予期したように起こるとは限らない。おおむねは人知を越えた、想定外の、夢にも思わなかった結末が訪れるのだ。決定要因はよそからやってくる。当事者の急死とか体調悪化とかまったくの不運・災難とか。人々が苦しまぎれに「歴史の偶然」なるカテゴリーに押し込んで満足するような種類の出来事群が厳存しているのは確かであり、それを前にしては人間はただ戦おののくしかないのだ。
今から45年ほど昔に『江戸の歴史家』を書いた時、評者わたしは、その冒頭を中島敦の小説に紹介されているアッシリアの一歴史学者の言葉を引用することから始めたのを覚えている。――「歴史とは、昔、在った事柄をいうのであろうか? それとも、粘土板の文字をいうのだろうか。」たしかに歴史とは「過去の人間的事実の記述」である。だがその場合、「歴史」とは、事実の堆積をいうのか、それを記述することをいうのか。この曖昧な二義性は「史」の字義に終始付いて回っているようだ。一面から見れば、その曖昧さは語義の幅の広さでもあり、「史論」「史観」「史談」「史録」「史眼」など、意味は異なるが連続的で、境界もしかとは引きにくい幾多の熟語群が生まれたのもそのためだ。歴史学は《科学か文学か》という古くて新しい論争も、「歴史」の語義幅が広いことから発している。著者がそうである歴史家は、度合の違いこそあれ、いつもこの両極の間に引き裂かれる宿命の星の下にある種属である。せいぜい「史譚」ぐらいにしか興味をもたぬ評者のごときはもちろん論外である。 畢
* * *
蝉声3首
〽梅雨明けて夏空けざく広がりて耳朶にとよもす蝉の諸声
〽これでもか注ぐ日ざしにじりじりと身を焦がしをる油蝉かな
〽やがて来る焦熱の日をあらかじめ世に知らせんと蝉のもろごえ
2023-06-30 |
口吟,
日暦,
桃叟だより今年の6月28日をもって満86歳になりました。月並みな表現でお恥ずかしい仕儀ですが、よくもまあこんなに生き延びたものだと思います。桃叟と同年配の人々はどう感じていらっしゃる事でしょうか。
一つしくじりをしました。毎年この時期に開かれる都立某高校の1956年卒業生の学年クラス会から案内状を頂いているのですが、いつも出している欠席の通知を今年はうっかり間違って「出席」としてしまいました。ヤキが回ったのかも知れません。皆さん車椅子を用意してまで待ってくれていたそうです。悪いことをしました。ごめんなさい。旧友の小澤幹雄君から聞きました。
学年会は大層盛況で30数名が集まったとのことでした。一学年400人が定員でしたから、卒業後67年にして参集率は約8パーセントということになります。われらが世代の生存率もそんなところかも知れない。とにかく残存兵力はこの人数しかないわけです。
小沢幹雄君とは高校時代、演劇部で一緒でした。その後はいい加減な桃叟と違って本物の役者になられましたが、その頃は無邪気に付き合わせてもらいました。「自分には電車の中で突然歌い出すちょっと変わり者の兄がいる」という話を聞いたこともあります。それが後に天下の大指揮者小澤征爾氏になるとはもちろん知る由もありませんでした。
それから10数年、桃叟老人が北米マサチューセッツ州ケンブリッジで暮らした1970年頃には小澤征爾の名前は世界的になっていました。ボストン・シンフォニー・ホールのロビーですれ違ったアメリカの小母さんに
から、「アーユーオザーワ?、オア、エスキモー」と訊ねられて面食らったのを思い出します。エスキモーと一緒にするとは何だと憤慨していたら、周囲に「そりゃ人種差別というものだ」とたしなめられたものでした。なるほど、と感心しました。
* * *
梔子3首――
〽ひたむきに言葉なけれどわれに向き物問ひかくるクチナシの花
〽何ゆゑに機嫌悪きか知らねどもこちら振り向けクチナシの花
〽八十あまり六つの月日は幾昔白き花見る明け方の夢


人に勧められてわがラインに通話機能を取り付けました。ビデオ機能もあります。一両人と試験的に通話してみて、自分が今抱えている問題点に気付きました。久しぶりに自分自身の顔に対面してひどくゲンナリし、「こりゃとても人前に晒せる御面相ではない」と痛感したのはもとよりですが、それ以上に重大な事柄があったのです。――この数年間、あまり人と会う機会がなくなっているせいで、発声機構、ひらたくいえば「声」を出す筋肉がどんどん退化していたのです。
こっちの言葉がだいぶ聞き取りにくいと見えて、日頃接触するヘルパーさん・トレーナーさんの多くはあまり熱心に聞いてくれません。聞こえたふりで片付けられているというのが大半です。いけないことですが、こちらもつい面倒になってしまいます。悪循環です。
そんなわけで、ラインの通話機能は、しばらく自分自身を相手に話しかけ、会話をこころみるのに活用しようと思っています。言葉とは何よりも声なのです。これからは「声」の復権をめざして邁進します。

偶吟四首
ガクアジサイの盛りに
芦屋でも隅田の川の夕花火見る人なくてここに幾とせ
夜な夜なの夢は乗り物経めぐらん三千世界の一宇一宙
ニャーたちや御飯ですよと声がした猫もあるじも健在の日々
オークスG12023優勝
馬ながらわれ勝れりと得意顔高くいななく晴れの鼻面
* *