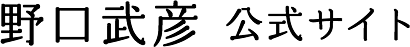[皆さんの声をお聞かせ下さい――コメント欄の見つけ方]
今度から『野口武彦公式サイト』は、皆さんの御意見が直接読めるようになりました。ブログごとに付いている「コメント欄」に書き込んでいただくわけですが、
同欄は次のような手順で出します。
トップページの「野口武彦公式サイト」という題字の下に並ぶ「ホーム、お知らせ、著作一覧、桃叟だより」の4カテゴリーのうち、「桃叟だより」を開き、右側サイドメニューの「最新記事」にある記事タイトルをどれでもダブルクリックすれば、その末尾に「コメント欄」が現れます。
そこへ御自由に書き込んでいただければ、読者が皆でシェアできることになっています。ただし、記入者のメールアドレス書き込みは必須ではありません。内容はその時々のブログ内容に関するものでなくても結構です。
ぼくとしては、どういう人々がわがブログを読んで下さっているのか、できるだけ知っておきたいので、よろしくお願いする次第です。以上

ノキノシノブ 『植物園へようこそ』より
「忍」の一字は何かと日本人には馴染みが深い。じっとガマンしたり、ならぬ堪忍をするのがほんとの堪忍だといったりするのは、長らくわが国では美徳だった。三島由紀夫は「忍ぶ恋」という『葉隠』の言葉をすっかり有名にしたし、時事ネタで恐縮だが、つい最近抗争中のある任侠集団の組長の通り名にも使われているくらいだ。
歌語の一つに「忍ぶ草」というのがある。今日でもノキノシノブといわれている羊歯(しだ)科の植物」のことである。「忘れ草」と同じように、決して想像上の草ではなかった。
「忘れ草」にはワスレグサという実在の植物(ヤブカンゾウの異名)がちゃんとあり、野辺の草むらにいくらでも咲いていたから、人々は見ようと思えばいつでも目にすることができたのである。しかし、万葉時代はともかく、平安時代の歌人ともなると、だんだん自然に触れる機会が減ったと思われる。それに引きかえ、ノキノシノブの方は家々の屋根とか築地塀の上に自生するから目に留まる機会も多かった。
そのせいで、歌人が「忘れ草」という言葉を詠み込む場合も、実物がどっちかを知らないで詠むようになった。「忘れ草」がヤブカンゾウなのか、ノキノシノブなのか区別が付かなくなったのである。歌を詠む現場に混乱が生じた。たとえば次の一首を見られたい。
わが宿の軒の忍ぶにことよせてやがても茂る忘れ草かな(後拾遺恋3-737,読人不知)
「私の家の軒に生えているシノブグサに事寄せて、前の男がまだ忍んでくるだろうという口実のもとに、あなたは私をお忘れになった。怨めしく思います。」
『後拾遺集(ごしゅういしゅう)』は応徳3年(1086)に撰進された第4の勅撰和歌集である。「読人不知」となっており、作者が、昔の男のことを言い立てて足が遠くなった今の恋人を怨む女になり替わって詠んだ歌である。シノブグサを「忍ぶ」(人目に隠れる)に懸けている。そのシノブを口実に御自分の心に私を忘れる「忘れ草」を茂らせていらっしゃると非難しているのだ。
ところが、この歌に詠まれている「軒の忍ぶ」という草はノキノシノブのことであるが、作者はそれを「忘れ草」と同一視しているようである。これが決して間違いでないことは、すでに『大和物語』――950年前後に成立――に「同じ草を忍ぶ草、忘れ草といへば」(162段)とあるように、相当古い時代から、二つの呼び名が同じ植物を指すとされていたのである。『後拾遺集』の歌では、明らかに、両方の名前でノキノシノブを表現している。
時代はかなり下るが、勅撰集の18番目にあたる『新千載集』――室町時代の延元4年(1359)撰進――でも、こんな歌が詠まれている。
忘草誰たねまきて茂るらん人を忍ぶの同じ軒端に (新千載恋5-1564、芬陀利花院前関白内大臣ふんだりかいんさきのかんぱくないだいじん一条経通)
「この忘れ草はいったい誰が種を蒔いて茂らせたのでしょうか。私をお忘れになったあなたしょう。私と同じように恋を忍んで下さっていると思っていましたのに。」
この歌では「忘れ草」の語がノキノシノブを意味していることは疑いない。しかし、もう一方のヤブカンゾウも、決して和歌の世界から消え失せてしまったわけではなく、『新古今集』――元久(げんきゅう)2年(1205)撰進――以後の勅撰歌集でも、相変わらず「住吉」「岸辺」といった言葉と一緒に詠まれている。「忘れ草」の語義はずっと二本立てで進んだようである。
亡き人を忍びかねては忘草多かる宿に宿りをぞする(新古今哀傷853、藤原兼輔)
「死んだ人への哀慕がつきないので、せめて『忘れ草』の多く茂る宿で過ごそうと思います。」
明け暮れは昔をのみぞ忍ぶ草葉末の露に袖濡らしつつ(新古今雑中1672、祝部成
中ほうりべのなりなか)
「年を取ると昔のことばかり思い出して『忍ぶ草』の葉末の露のように涙をこぼす今日この頃だ。」
これら2首の新古今歌には、それぞれ「忘れ草」「忍ぶ草」が詠まれており、いずれも意味としてはノキノシノブを指してはいるが、重要なポイントは、どちらも「忘れる」こと・「忍ぶ」ことの比喩として用いられ、実物を指示する意味作用をほとんど持っていないことである。特に後の例では「忍ぶ」が懸詞に生かされている。新古今歌人はここでも言葉から言葉を紡ぎ出しているのだ。
「しのぶ」という動詞には、もう一つ厄介な問題がある。
かつては「隠忍(じっとガマンする)」を意味する四段活用動詞と、「思慕(人目に隠れて想う)」を意味する上二段活用動詞の二つが存在したのである。『葉隠』の「忍ぶ恋」などはさしずめ「忍ぶる恋」とあるべきところだ。奈良時代までは、四段活用の方はシノフと発音されたので両者はきちんと区別できたが、平安時代になるとその発音は消滅し、シノブに一本化したので両者が混用されるようになった(岩波古語辞典)。
なお折口信夫は、奈良時代にあった言葉を「しぬぶ」というバ行動詞であるとして四段・上二段二通りの活用を認め、「偲」の漢字を充てている。つまり。「しのふ」の形を認めていない。活用の違いがそれぞれ何を意味するかにはあまり関心を示さず、むしろその語源を探ることに熱心である({万葉語辞典})。
折口によれば、「しぬぶ」は「しぬ」を語根、「ぶ」を語尾とする動詞で、「しぬ」に動く心の状態であるという。「しぬ」は「下(しも)」「萎(しぬ)」「死ぬ」などと関係のある語であって、「意気消沈」の意があるとされる。これだけでは非常に分かりにくいが、事柄はたんに一つの動詞の語源に留まらぬ折口の独創的な死生観と結び付くと考えれば多少理解できるように思う。それによれば、大意はこうである。
古代の日本人には「死ぬ」という観念がなかった。現代人が「死」と呼ぶ現象は、ただ魂が遊離して、「くたくたになって元気がなくなった状態」であるにすぎない(「上代葬儀の精神」)。「しぬ」は「死ぬ」とは違うのだ。その「しぬ」という語の音を含んだ語はたくさんあり、それらはみな共通の意味成分を持っているとするのが、折口の独自な言語感覚である。このように「しのぶ」は「恋ふ」と同じく我々の深層に埋もれている始原的語感に行き当たる。「恋ふ」にも「しのぶ」にも、本来その底には、人間の生き死にがらみのおそろしく真剣なものがあったはずなのだ。 了

ワスレグサ 『植物園にようこそ』より
忘れ貝に次いでよく知られる「恋忘れ」の呪物であり、歌によく詠まれる素材になっているのは忘れ草である。これは忘れ貝以上に具体的にどんな事物を指すかがはっきりしている。『万葉集』には「萱草」という漢字表記も見られる。ユリ科のヤブカンゾウの異名である。いつも目に付いた野の花だったのだろう。一日花であることが関係しているかもしれない。
忘れ草わが下紐(したひも)に付けたれど醜(しこ)の醜草言にしありけり(万葉集4-587)
「ワスレグサを下着の紐に付けたけれど、きみのことが忘れられない。バカな草だよ、忘れるなんてデタラメだよ。」
平安時代の『古今集』でも、初期の「読み人知らず」の時期には人々はまだ真剣に忘れ草の呪力で恋の苦しみを忘れようとしていたと見てよさそうだ。『古今集』はふつう①「読み人知らずの時代」②「六歌仙時代」③「撰者時代」の三期に区分されるが、このうち①は『万葉集』の末期から嘉祥(かしょう)3年(850)頃までの歌風の過渡期である。次の一首などはそういう古風さを感じさせる、
忘れ草たね取らましを逢ふことのいとかく難きことと知りせば(古今恋5-765,読人不知)
「ワスレグサの種子を取っておいて蒔けばよかった。あなたとまた逢うのがこんなに難しいと知っていたなら」という詠みぶりには、この植物の効能についてのまだ純朴な信仰の名残が残っている。しかし②の「六歌仙時代」(だいたい仁寿元年851~寛平2年890)になると、早くもちょっと感じが違ってくる。
忘れ草何をかたねと思ひしはつれなき人の心なりけり(同恋5―802、素性法師)
「ワスレグサの種子はいったい何だろうと思っていたが、やっと分かりましたよ。あなたのようなツメタイ人の心だったんですね」――素性法師は六歌仙ではないが、三十六歌仙の一人である。この歌も有名な寛平歌合(かんぴょううたあわせ)の時、入選して屏風に書かれた題詠の一首だ。技巧的に詠まれた歌であり、「つれなき人」は実在の女性ではない。作者の心の中に住む冷淡な情人である。忘れ草も現実の植物ではなく、むしろ言葉の綾の織物だろう。
このように、「忘れ草」がだんだん実物のワスレグサを詠むことから、たんに「忘草」という言葉としてだけ詠み込むことへの歌風の変化は、③の「撰者時代」になるといよいよ顕著になる。撰者時代は、寛平3年891)から延喜5年(905)、『古今集』撰進の頃まで。いわゆる国風文化の確立期である。
住吉と蜑(あま)は告ぐとも長居すな人忘草生(お)ふといふなり(古今恋5-917、壬生忠岑 みぶのただみね)
「早く帰って来ておくれよ。土地の人がいくらここ長居の浜は住みやすい所だといっても、そこは人を忘れさせる草が生えるそうだから」――この歌には「住吉参詣に出かけた恋人に送る」という詞書が付いている。ここでもまた「忘れ草」は住吉という土地の景物(たくさん自生したのだろう)だというが、作者は伝承を語るのみで実物を見ていない。それにしても住吉が「忘れ貝」「忘れ草」の双方に縁が深いのは興味深い。
平安和歌はその後300年の歳月を経ていろいろ発展を遂げるのであるが、その間ずっといくつもの勅撰集、私家集の標準であり、対抗すべき目標であり続けたのは『古今集』であった。和歌の流れはやがて平安から鎌倉への時代の変わり目に『新古今集』が編纂されて大きな転機を迎える。同集に詠まれた「忘草」の歌はすぐ後で見ることにして、まず八代集の5番目に位置する『金葉集』の一首を取り上げよう。
忘れ草しげれる宿を来て見れば思ひのきより生ふるなりけり(金葉恋下468、源俊頼 みなもとのとしより)
単純には口語訳しにくい歌である。「恋の歌をよみける所にてよめる(かつて恋の歌を詠んだ場所でこの歌を詠む)」という詞書がある。二重の仕掛けになっているのである。ここは。自分が昔、恋の歌を詠んだ場所だ。今来て見ればワスレグサがいっぱい生えている。「宿を来て見れば」――「宿に来て見れば」ではない――は、「宿」が「来」ではなく、「見る」の直接目的語であることを示す。戻って来て昔の場所をみれば。なのである。生い茂っているワスレグサはなんと自分が相手から身を引いた所から生えているのであった。「思ひ退く」という複合動詞を想定する、その連用形「おもひのき」の「のき(軒)」と懸詞になっている。しかしワスレグサが萱草つまりヤブカンゾウだとすると、果たして忍草(忘草の異名)のように軒端から生えるものだろうか。いずれにしても、「忘草」は実象(じっしょう)としてより心象として詠まれているといえよう。
折口信夫は ,「前代文学を融合」した歌人の一人として俊頼をかなり評価していたらしい。「既に固定した文学用語・枕ごと以外に、古典的な清純な感情を起す体言・用語・助辞なども、現代通用の粗雑な整頓せられない都鄙の口語文法などから」(「女房文学から隠者文学へ」)もどんどん取り上げて歌に用いたと言っている。その私家集に『散木奇歌集(さんぼくきかしゅう)』があるくらいで、自作を奇歌と見なされるのも厭わなかった。――さて、いよいよ『新古今集』の場合を見る番である。
住吉の恋忘草たね絶えてなき世に遭へるわれぞ悲しき(新古今恋5-1419,藤原元真 ふじわらのもとざね)
この歌には本歌がある。『古今集』の「道知らば摘みにも行かん住江の岸に生ふてふ恋忘草」(1111)。この紀貫之の歌では、「忘草」は伝聞ではあるが、少なくとも実物の草を意味している。ところが『新古今集』の方ではどうか。もう絶滅していて一本もないのである。「忘草」さえ生えない時代に生まれ合わせた自分は、もうつらい恋を忘れることもできないのが悲しい、というのだ。
歌に詠まれる「忘草」は、目に見える対象ではなく、ただ心象の中にしかない。イメージだけの存在である。このとき成立しているのは、言葉があれこれの事物をではなく、言葉それ自体を対象化するという非常に高度の言語技法なのである。わが愛する新古今調の名歌についてはいずれまた。

ワスレガイ 『貝類図鑑』より
平成28年(2016)1日、最高裁は、JRで事故死した徘徊老人の遺族に賠償責任なしという判決を出した。世論はいろいろあろうが、拙老は久々の名判決だと思うし、何よりも最高裁判事たちの老齢化が理解を進めたのだろうと推察している。
ところで、日本の古代人にもアルツハイマーはあったのだろうか。
百年(ももとせ)に老舌(おいじた)出でてよよむともわれは厭はじ恋は増すとも(『万葉集』巻4―464)
大伴家持の歌である。紀郎女(きのいらつめ)との相聞歌で「たとえあなたが百歳になって物いう声がレロレロになっても――「老い舌」なんて言葉があるんだ!――私はイヤになりませんよ、もっと好きになっても」というのであるが、などと「ホントカネ?」と思うほど調子がいい。こんな歌がシャアシャアとよめる間は、まず老耄する気遣いはあるまい。
「忘却とは忘れ去ることなり」というが、アルツハイマーとは「百年の恋」も忘れさせてしまうものなのだろうか。古い時代の詩歌を見ると、「恋」と「忘却」との間には深いつながりがあるように思われる。「忘却」とはたんなる物忘れではない。忘れるということは、当初もっぱら、恋を忘れることを意味していたようなのである。
「忘れる」ことと「忘れ去る」こととは違う。現代語の「忘れる」は古語の「忘る」の延長上にあり、現代語は下一段活用の動詞だが、これは古語の下二段活用を継承している。辞書的には「記憶からなくなる」を意味する自動詞とされる(日本国語大辞典)。「恋を忘れる」とは、「恋が記憶からなくなる」ことなのである。
しかし「恋を忘れる」という言い方が端なくも示しているように(目的語を助詞ヲで受けるのは他動詞だ)、現代語では自他の区別がはっきりしていない。現代語どころか、奈良時代頃からすでにそうだった。しかしもっと古い時代にはただ物事を自然に「忘れる」のと、何かを意図的に「忘れ去る」あるいは「忘れ果てる」のとは厳密に区別されていた。両者の差異は、ラ行下二段活用の「忘る」とラ行四段活用の「忘る」とに分担されていた、と日本語音韻の研究――特に上代特殊仮名遣いに関する「有坂の法則」――で知られる国語学者有坂秀世(ありさかひでよ)が「「『わする』の古活用について」で論じている。
以下の諸例は、特にことわらない限りいずれも『万葉集』の引用である。いちばんわかり安いのは、次のように、同じ一首の中に動詞「忘る」の四段活用と下二段活用との双方が使われている例であろう。
海原の根柔ら小菅(こすげ)数多(あまた)あれば君は忘らすわれ忘るれや(巻14-3498)
「あなたは(私ヲ)お忘れになるでしょうが、私ニハ忘れられません」の意だ。四段の方は未然形ラ+尊敬の助動詞スで、意味は他動詞的、下二段の方は已然形ルレで、意味は自動詞的である。
『万葉集』の東歌(あずまうた)には、形は下二段だが、意味内容はまるっきり他動詞だという実例がいくつもある。その一つはこういうものだ。
あが面(おも)の忘れむ時(しだ)は国放(はふ)り嶺(ね)に立つ雲を見つつ偲(しぬ)ばせ(巻14-3515)
「私の顔ヲ忘れたら、国を遠く離れて山の峰に立つ雲を見ながら思い出して下さいな」――予想の助動詞ムは動詞の未然形に接続するから、この「忘る」は明らかに下二段活用である。つまり、下二段の他動詞がここにはある。
かと思うと、
うち日さす宮のわが夫(せ)は倭女(やまとめ)の膝枕(ま)くごとに吾(あ)を忘らすな(巻14-3457)
「あなたはいくら都女の膝枕をしてもいいけど、私をお忘れにならないでね」というのであるが、この歌では尊敬の助動詞スが未然形に付いていることは明瞭だ。
しかしもっと古い時代には、東歌ではなく、京畿地方の言葉にも、自他の区別を活用の違いであらわす語法が存在した。その一例に『古事記』上巻および『日本書紀』神代下に見えるヒコホホデミノミコトの短歌がある。両歌はたがいに異本の関係にある。
沖つ鳥鴨着く嶋にわが率(い)寝し妹は忘れじ世のことごとに(古事記)
沖つ鳥鴨着く嶋にわが率寝し妹は忘らじ世のことごとも(日本書紀)
――両方とも「忘る」の未然形が否定推量の助動詞ジに接続する。『古事記』の方は下二段で、有坂によれば「妹のことは一生忘れられないであろう」、「妹は『忘れじ』に対する主格である」。『日本書紀』の方は四段の未然形+ジの形。おなじく有坂によれば「妹は『忘らじ』に対する賓格(目的格)である」とされる。「一生決して忘れはせぬぞ」という誓言だから、意志的なのである。
その後長い時間が経ち、四段活用の「忘る」は日本語の表面から消失し、現代語の「忘れる」にいたっている。何かを忘れるという意志的な意味もなくはないが、それも下一段の活用を通じて表現されるのである。だから、「忘る」という動詞には独特のダイナミズムがある。この動詞には、内心の激しい意志的な行為(忘れようと決意・努力する)を、うわべはさりげなく自発的に推移する心の流れ(忘れてしまう)に包摂させる感情の力学が蔵されている。
こういうダイナミズムは、前回取り上げた「恋ふ」の古形における下二段と四段の共存が、だんだん四段に吸収され固定したプロセスとよく似ている。「恋」とはもと、たんなる人間感情の激発ではなく、それと何か日常感情を超えた情念との積(せき)であった。一種の呪力であったといってもよい。呪力が人間離れした情念を呼び込むのである。その水位で恋をするには強力なエネルギーが必要である。そしてもし恋にエネルギーを発動するのに呪力の助けがいるなら。恋を忘れることにも呪力のエネルギーが要請されねばならない。「忘却」にも相当な労力がかかるのだ。
普通の努力では容易に恋を忘れることはできない。古人はこういう時、禊ぎをして神に祈るか、もっと平易に呪物の助けを借りようとした。呪物の中でポピュラーなのはまず「忘れ貝」であろう。
大伴の御津(みつ)の浜なる忘れ貝家なる妹を忘れて思へや(巻1ー68)
「大伴の」は「御津」にかかる枕詞。「御津の浜」は難波の住吉にある砂浜で、忘れ貝がたくさん取れるという。忘れ貝は人を忘れさせるというが、私は家で待つ妹を忘れたりするだろうか。この歌は慶雲(きょううん)三年(706)、藤原京時代の作だが、この頃にはすでに忘れ貝の伝承があったと知られて興味深い。
國學院デジタルミュージアムの『万葉神事語辞典』によれば、『万葉集』中に「忘れ貝」の用例は全部で5例あるそうだ。これらとは別に、「恋忘れ貝」という語句も5例あり、「これらはすべて恋人を忘れさせる貝として詠まれている」という。中でも次の一首は古伝承の形そのままだといえよう。
手に取るがからに忘ると磯人(あま)のいひし恋忘れ貝言(こと)にしありけり(巻7-1197)
「からに」は「だけで」の意。「手に取っただけで即座に恋を忘れられますよ」と海女は言ったけれども、いっこう忘れられないじゃないですか! ただ言葉だけだったんですねえ」というこの歌には、「古集中に出づ」と注がある。万葉の時代から忘れ貝のことは伝説にすぎないと幻滅されていたのだ。それでも恋に苦しむ人々はこの呪物にすがるのである。
恋せじと御手洗河にせしみそぎ 神はうけずぞなりにけらしも
『古今集』「恋」一(#501)にある有名な歌である。作者は読人不知とあるが、在原業平とされている。大意は、「もう恋はするまいと心に誓って御手洗川(みたらしがわ)で禊(みそぎ)をしたが、神はこの誓いを受けてくれなかったらしいよ。恋は募ってゆくばかりだ」というものだ。
もとは『伊勢物語』65段の話だ。業平が時の天皇に寵愛されている染殿の后に恋慕するが、この禁断の恋を続けていたら、身の破滅だと、賀茂の神に「恋を忘れさせて下さい」とミソギをして祈ったが無駄であった、という一篇の歌物語が下敷きにある。
折口信夫は、「恋」とは昔相手の「霊魂を迎え招く」ことだったと言っている(「恋及び恋歌)。「恋」とはもと「魂()ごひ」だったというのである。「恋う」はかつて「乞う」と同語源とする説(『大言海』など)があったが、現在では、両動詞には甲音・乙音の区別があり、二つの語はもともと別音だから、この説は成り立たないと否定されている(大野晋『岩波古語辞典』)。
折口がいうには、文語の「恋ふ」はふつう上二段に活用する動詞に使われるが、この言葉には、古来、四段に活用する「こふ」――漢字を宛てれば「乞ふ」に近い意味内容だ――が潜在していて、活用形式を越えて浸出していた。つまり、後に「恋ふ」「乞ふ」と別々の動詞になる以前の「*こふ」という古意を表す言葉が存在したのである。(*は言語学で「文献にはないが,こうだったろうと推定される語形」を示す記号。)折口は、奈良時代には主として助詞ニを受けていた「恋ふ」が平安時代からはヲに接続する語法に変わった、とする。以下はその例:
わが脊子に恋ふれば苦し暇(いとま)あらば拾(ひり)ひて行かむ恋忘れ貝(万葉集・巻六#964)
夕暮は雲のはたてに物ぞ思ふあまつ空なる人を恋ふとて(古今集・恋一#484)
『万葉集』の歌に出て来る「恋忘れ貝」とは「拾えば恋の苦しさを忘れさせるという伝承のあるワスレガイの別名である。こんなに苦しい恋をするよりは思い切って忘れるためにあのワスレガイを拾いに行こう、というのだ。折口信夫の『万葉集事典』はワスレガイの項で、「蛤(はまぐり)に似て、殻が深く、縦に深い筋があり、且(かつ)、茶褐色の斑(まだら)がある」と記し、「浪のひいた後に遺(のこ)っている処から、浪のわすれ貝の意」としている。「忘れ」という言葉については次回に後述。
恋とは、本来ただ異性が好きになるという意味ではなく、原義は「威霊あるものを迎える」意味だったと折口はいう。威霊を自分の方へ移させることなのである。思う相手の内部に何か威伏されるべき力を感じ取らなければ恋は始まらない。恋愛感情はしばしば対象を過度に美化したり、神格化したりするが、そうした心理の始原には相手の霊魂を招き寄せ、自分の物にしようとする呪力が働いている。万葉の「恋ふ」は近代の「こがれる」に近い語感だが、それではまだ言い尽くしていないと折口は留保を加え、「恋」の原義はもっと濃い密度のものだったろうと想像する。
古代人の「恋」を後世の恋情になぞらえて理解してはならない。たとえば、古来恋の名歌としてよく知られた仁徳天皇皇后、磐媛(いわのひめ)の一首も独特の解釈を与えられる。
かくばかり恋ひつつあらずは高山の岩根しまきて死なましものを(『万葉集』巻二#86)
この歌の現代語訳はふつう、「こんなに恋い焦がれているのに、待ち続けて苦しむくらいなら、険しい山の岩を枕にして死んでしまった方がましだわ」というふうになるのだが、折口によれば、それなどは「恋ふ」を後代の意味で「思い焦がれる」と誤解したものだと片付けられる。そもそもこの短歌が『万葉集』で「相聞(恋歌)」の部に分類されているのが間違いで、本来は「挽歌(哀悼歌)」だったのだ。(『万葉集』巻二は全巻が「相聞」に部立てされている。)奥山の墓所で山の巌を枕(ま)いて、死んだ人の「魂ごい」をする時の詞章がこの歌だった。それを「相聞」の部に入れたのは、すでに『万葉集』の編纂者、あるいはその材料になった「古歌集」の蒐集者の頃から「恋ふ」の原義が不明になっていたからだ、と折口はいうのである。
折口民俗学とは、先史学であり、古層言語学である。折口は、天性としかいいようのない言語感覚をもって、拙老がさきほど「*こふ」と表記した仮想の動詞が実在したことを探り当てる。「*こふ」とは、「恋」「乞」その他の始原的情感を含意した動詞である。「こふ」に「恋」と「乞」の両儀があるのではなく、つまり恋+乞という和ではなく、恋×乞という積があったことを復原して見せる。
次回は「恋」の逆数である「忘却」について考えたい。

『日本文学源流史』 青土社
藤井貞和氏は畸人である。奇人でも変人でもない。『荘子(そうじ)』大宗師(だいそうし)篇にいわく、「畸人は、人に畸なれども天に侔(ひと)し(肩を並べる)」と。畸人とは、普通の人間には偏倚と思われるが、本当は俗眼俗耳が見もせず聞きもしないことを感じ取り、天と対話している人だというのである。
五十年ほど前の学生時分、氏は日頃から伝説にくるまれていた。事の真偽は知らないが、たとえばこんな調子である。いつも電話に出る時、「もしもしもし」と三声で応じる。なぜかは誰も知らなかった。また、試験答案やレポートを提出した時、きまって独特な文章で教官諸氏を悩ませる。通常「~しただろう」とある所を「~ダロウデアッタ」と書いたそうなのだ。古代日本語では「断定」の助動詞は必ず「推量」の後に接続し、その順序が乱れることはない。きっと彼は頭の中では古代語で考えているに違いないと、友人たちは噂しあった。
氏の近著『日本文学源流史』は、この野心的なタイトルが暗示しているように、日本文学の成り立ちをその始原にまでさかのぼって再構築しようという雄大な構想をそなえた労作である。「始原」とはたんなる「過去」ではない。「現在」の瞬間をすっぱり断ち切っても、その断面にいつも伏在して、全過程を深層から規定し続ける初期条件である。たとえていうなら、かつて氏自身が古代日本語の「時の助動詞」の成立を論じた文章を借りて説明しよう。
かつて日本語の「時の助動詞」(き、けり、ぬ、つ、たり、り)には動詞・形容詞・動詞などの自立語だった独立時代があった、というのが藤井氏の立てた仮説というよりむしろ先天的な記憶である。たとえば「き」には「来(く)」の、「ぬ」には「往(い)ぬ」の、「つ」には「果つ」の残響があるといったように。それがやがて時制表現を死活的に必要とした古代人によって非自立語化されて助動詞になったとされるのだ。現代日本語には過去の助動詞としては「た」一語しかない。「た」は、現在言葉の表面には現れず、前言語的に複合し屈折している思考・感覚・色調・陰影等の表現をいわば兼業しているのである。(『日本語と時間』参照)
日本文学の源流を探ろうとする仕事を貫いているのは、右のように特異な思索の軌跡である。源流はただの上流ではないし、源泉でもない。水流は現在も流れ続けているのであり、氏が文学の過去にこだわることはそのまま現代の問題領域に分け入ることなのだ。こうして始点と現時点とをいつも同一視野に置く独特のパースペクティヴを見るために、独創的な《時代区分》に注目しよう。読者はまずその構想力に驚かされる。
1 神話紀 (ほぼ縄文時代)
2 昔話紀 (ほぼ弥生時代)
3 フルコト紀 (ほぼ古墳時代)
4 物語紀 (7,8世紀~13,14世紀)
5 ファンタジー紀orポスト物語紀 (14、15世紀~ほぼ現代)
これらの5紀はそれぞれ幾世紀かの質量をもってただ逐次的に累積するのでなく、重層しかつスペクトル的に連続している。幾十世紀もの間、水流が沈澱させることなく、ひたすら今日まで押し流して来たものが、現代において一挙に浮かび出るのだ。そうした一種の永久運動性が日本文学の歴史を特徴づける。氏が1972年に書いた文章を借りれば、「日本の神々が、変動の時代あるいは変革期になると生きてあらわれ、変動の時代あるいは変革期が過ぎると傷つくか、死ぬかしてゆくという特徴」(「物語のために」)なのである
拙老は、1~3紀までの記述が琉球語やアイヌ語の知見に視界を広げた口承文学の世界に踏み込んでいる部分に関しては、論評を敬遠する。また、5紀の近世(江戸時代)に関する記述については、氏の想像力の飛翔について行けるかどうか心もとないので評判にわたらない。ここで熟読の焦点とし、積極的に紹介したいと思うのは、物語文学論である。何をおいてもまず、以前に氏が下した《ものがたり》の定義に眼を向けよう。この定義はいわば氏の初心である。
《「ものがたり」とは、正史に属する語りに対立する、正史でない語りだったのではないかと思われる。語られるべきは正史なのだ。その語りであるという正史の限定を取り去ったとき、それが「ものがたり」ではなかったか(……)カミ(神霊)になることのできなかった、劣位の霊魂がモノであることは、大方の意見の一致するところであった。非正統の存在として、歴史の背面へ埋没させられてゆく運命を持つ、いわば二流の霊魂がモノと呼ばれる。》(「物語の発生する機制」)
今この『日本文学源流史』にあっても、この初心が揺らぐことはない。物語をモノのカタリとしてカミのカタリへの対抗軸に置き、それが「霊(モノ)ガタリ」として、どこまでも「劣位の」「二流の」モノによる語りであったとする物語起源論を基礎的な構図とする原理はいささかも変更されていない。この卑下に見えて実は確信に満ちた所論は、氏が民俗学者折口信夫(おりぐちしのぶ)の物語発生論を読み解き、読み破って血肉化したものに他ならない。この欄で1月23日に取り上げた『ゲンロン』創刊号で、福嶋亮大氏が「日本文学をいかに批評するか」で折口の『日本文学研究序説』を引用し、「今日のほとんどの批評家」は「参照すべき歴史的文脈の構築には無頓着であった」といているが、この場合藤井貞和氏の仕事を見落とすべきではなかった。
この『日本文学源流史』は、さすがにいつまでも、《カミガタリ vs. モノガタリ》の図式にこだわっていない。代わって提出されるのが《フルコトvs. モノガタリ》とでも公式化できそうな、新しい対立軸だ。フルコトが正史の「正統的な語り」であるのに対して、モノガタリは「非正統的で自由な語り」である。表現字句上の些細な違いに見えるかもしれない。しかし、この微妙な修正は大規模な比重の移動を伴っていると思う。たとえば「室町物語」というような境界例も見られるように、物語は「かならずしも完結しない物語性」あるいはポスト物語性を孕み始めるとされる。
本書のこのあたりの行文はまだ熟し切っているとは言い難く、文章の晦渋さが気になるが、それにしても、氏が「14,15世紀~ほぼ現代」とかなり長めに――つまり、全期間の等質性をいわなくてはならない――設定した一時期を「ファンタジー紀」あるいは「ポスト物語紀」と名づけ、そこに生起した文学的事件の当事者たちを一連の系譜で捉えようとした視界の深さ、膂力(りょりょく)の強さには驚かされる。氏の構想の中に強力な磁場が形成されたとでもいった具合に、その系譜に連なる人々を磁界に引き寄せるのである。芸能民、隠者、浪人、戯作者、遊民・・・ひいては文学者、と辿られる非定住者の系列だ。そして「次代を作るべきアーティストは人生のどこかで隠者であることを経験する」と氏が書く時、氏には自身がその系列に連なるという自覚がたっぷりある。そしてそうした確信は間違いなく、氏が自身の学問の「参考項目」とする折口学のあの周知の命題:「隠者は、古来、社会の制外者である」(「女房文学から隠者文学へ」)に励まされている。
しかし、使徒は常に師が知らなかった新しい時代に直面しなくてはならない。非定住の地点を文学者の居場所と見きわめるにしても、現代には神話や民俗伝承が積み残してきた幾多の問題が存続しているはずだ。ほんの一例を挙げれば、民俗学が人類の過去に存在したことを確認し、現代にも痕跡を留めている人身供犠の問題。なまの人間を犠牲にすることを止めて動物を犠牲にするようになったことが文明の進歩と見なされているが、果たしてそうか、現代人の魂の内部には民俗的暗がりに回帰する通路が見出されるのではないか。氏が「人身供犠」というテーマを手がかりにして「死刑」「戦争死」「差別」「いじめ」等々のホットな問題群ににじり寄り、民俗学の射程に引き込んで行く論調は鋭い。
1969年の藤井貞和氏は、文学者であることについて、「文学は徹頭徹尾、社会的には無効であること、無効でなければならないことを、いやおうなく知らされてきた」(「バリケードの中の源氏物語」)とぼやいていた。しかるに今、『日本文学源流史』を結ぶこんな一文には、何かもっと確信に満ちたトーンが感じ取れないか。原発事故の問題に多くの文学者が取り組んだことについて氏はいう「技術の暴走を文系が鎮めてまわるというようなことか、だれが知ろうか。」
タイトルになっている「神の水」という言葉は、昔、アメリカ中西部の乾燥した平原に入植した開拓民が天から降りそそぐ雨を呼んだ表現だそうである。
生活実感のこもった言葉だ。しかしこの表現からは、何かもっと切迫した、人間の根源的な渇きに発した「水」への祈念が響いてくる。作者のパオロ・パチガルピは1972年生まれのアメリカのSF作家 であり、この分野ではたいそう権威のあるローカス賞・ネビュラ賞・ヒューゴー賞などを続々と獲得している。拙老は、このテの作品はスティーヴン・キング以外にはあまり読んでいないが、今回その不案内にもかかわらず、この作品を私設書評欄に取り上げてみようと思い立ったのは、何よりもこの作品の底から、全編にみなぎる悪夢的に予言文学的な構図、疑似黙示録風の構造を突き抜けて、切実な祈念の声が聞き取れるような気がしたからである。
書評にはルールがあって、ストーリーの結末やプロットを暗示するキーワードのたぐいを語ってはならないことになっている。そういう制約があるので言葉を控えるが、本作の舞台はアメリカ南西部。カリフォルニア、ネバダ、ユタ、アリゾナ、ニューメキシコ、テキサスなどの諸州が隣接して広大な地域を占めており、その間にロサンジェルス・ラスベガス・フェニックスなどの大都会が散在している。各州・各都市はそれぞれ自立し、自主性を保っているが、じつのところ、この地域は一つの運命共同体的なきずなにつながれている。コロラド川である。北はロッキー山脈に水源を発し、南のメキシコ湾にそそいでいる。上記の諸州は多かれ少なかれ 潅漑事業・工業用水・砂漠の緑化といった恩恵を、上流から下流まで、この大河からの取水に仰いでいるのである。
もしコロラド川が涸渇したらどうなるか。
『神の水』一篇はこの必ずしも荒唐無稽ではない想定が現実になった日々の年代記である。諸州の利害官関係はたちまち険悪化し、水利権はおろか毎日の飲み水までが暴力的な争奪の対象になる。州兵による越境者の殺戮、住民同士の殺人が日常茶飯事化する。物語の核になる人物はネバダ州ラスベガスの「水工作員(ウオーターナイフ)」、水問題を取材しようとする女性ジャーナリスト、テキサス難民の少女。いずれも水不足にあえぐアリゾナ州フェニックスに来合わせて運命を交錯させる。この都市はすでに利権の独占を図る企業「ネバダ水資源公社」に水の供給を止められ、盗水(?)を防ぐために用水路は封鎖されている。富裕層は中国資本の「太陽国際公司(タイヤンインターナショナル)が経営する分離された区画「環境安全都市(アーコロジー)」――そこでは清潔な空気と水が豊富に提供される――という設定だ。中国インフラ資本の描き方には思わず笑ってしまう。
SF、ファンタジー、ホラーのたぐいは、江戸文学でいえばさしずめ稗史小説(はいししょうせつ)の部類だろう。語るところは驚天動地、波乱万丈を旨とし、架空虚誕(かくうきょたん)を決して嫌わない。写実ではなく真実を描く。たとえば曲亭馬琴の『八犬伝』。たとえ仁義礼智忠信孝悌を体した八犬士は絵空事でも、この世に仁義というものがあってほしいという人々の祈念が真実であることは読者の胸に強く響く。同様に、今、世界の人類を不安にしている水資源涸渇の真実は、時として エンターテインメントの方が生々しく心に伝わるのである。
現在世界中で水紛争が起きている地域はコロラド川流域にとどまらない。ちょっとインターネットを開くだけでも、アムール川、スエズ川、ドナウ川、ユーフラテス川、チチカカ湖周辺など各地で争いが絶えないことがわかる。イスラエルと周辺アラブ諸国の紛争には水資源の奪い合いがからんでいるし、中国が日本の水源地を買い占めにかかっているという噂もある。水不足の問題全部には地球温暖化の巨大な影が落ちているともいわれる。これらを取り上げる論調は、エンターテインメントが突きつける具体的な「不安」の存在感に比べると寒々しいほど抽象的に見えてしまうのだ。 (中原尚哉訳、早川書房)
16-02-07

米よこせ雀
テレビで最近「わかりやすい」ニュース解説者として高名な池上彰氏が対談集の本を出した。題して『池上彰が世界の知性に聞く どうなっている日本経済、世界の危機』。内容は、(1)著者自身のマエセツ、(2)「世界の知性に聞く」という章題のもとにトマ・ピケティ、エマニュエル・トッド、岩井克人(いわいかつひと)の3氏との対談、(3)第二次大戦後の日本経済の節目々々に大きな役割を演じた政府高官、企業経営者7人へのインタビューという3部構成になっている。
このうち第3部は拙老に歯が立つ世界ではないから敬遠して、ここではもっぱら、第1部と、第2部の対談相手がいずれも世界の現在情勢についてある程度マクロで長期的な展望を語っているダイアローグに関心を向けて感想を申し述べたい。
池上氏が大学時代にマルクス経済学を学んだといっているのは多少意外だった。その理由は次のようなものだったという。「実は私も数学は苦手でした。それで数学を駆使する近代経済学――今で言うマクロ経済学、ミクロ経済学はあきらめて、あまり数学を使わないマルクス経済学を学ぶことにしました」というのである。前世紀の60年代の末期、日本では全共闘の世代がマルクス主義との訣別に「死ぬような」思いをしたのを目の当たりにした拙老などの世代は、両経済学の違いが数学使用の度合で片付けられるのに多少心外な気持はなくもないが、まあこの場合あまり尖ったことはいわないとして、1950年生まれの池上氏と37年生まれの拙生との間にあるわずか13年の時差のうちに、あたかも違う大陸プレートが出現したかのような精神史的な地殻変動があったに違いないとだけコメントしておこう。
日本の思想風土には大正から昭和にかけて、どう否定しようもなく、それが好きか嫌いかに関係なく、マルクス主義が人々の基礎教養になった時代、そしてその時代の空気を吸って育った世代が存在する。それは明治にダーウィニズムが、江戸時代に朱子学の理気二元論が、支配的思想として一世を風靡したのと同じことだ。どれもたんなる個別学説ではなく、世界観思想だったのである。同じ社会の中にいくら反対や批判があっても、それはどこまでも反論としてだ。花田清輝という批評家の名言でいうなら「アンチテーゼはテーゼに規定される」のだ。
思い出す言葉がある。「下(しも)をわが苦世話(くぜわ)に致し候心御座なく、国家を治むる道を知り申さず候わば。何の益もこれ無き事に候(下々をわが事のように気苦労にかけ、国を治める道に責任を負わなければ何の用にも立ちません)」(『徂徠先生答問書(そらいせんせいとうもんしょ)』)という一文」である。もとより、徂徠学をマルクス主義に比定するつもりはない。また、既成マルクス主義の功罪を今更あげつらう気もない。ただ、一昔前の良質のマルクス主義の根底には「下をわが苦世話に致す」心があったということを思い出しておくまでだ。
氏が二つの経済学を特徴づけて、マルクス経済学は「もう今の資本主義社会は駄目だ、打ち壊すしかないんだという死亡宣告」の処方箋、ケインズ経済学は「いやそうではない、総需要をきちんとコントロールすれば、大恐慌にならずに済むんだ」という処方箋をそれぞれ書いていると要約して見せるのも、読者の理解のために必要な単純化としてわからないではない。しかし、経済学は果たして処方箋を書くだけでよいのかと疑問を投げかけたい気持は残るけれども。もっとも氏自身は現代では「深刻な不況はあるけれど、大恐慌にはならない」という社会常識に寄り添った 見方をしている。だから、今「世界で最も大きな問題のひとつ」として「経済格差の広がり」をクローズアップし、第2部の対談全部に底流させた時も、自然に、格差の問題はいずれコントロールできるだろうという楽観的なムードに包まれているように見える。
国際的なベストセラー『21世紀の資本』の著者T・ピケティは日本にも多くの読者がいる。ピケティ理論のエッセンスは「r>ɡ」(株や不動産など資産の収益率は経済成長率を上廻る)という不等式である。これまでずっとそうだったし、今後もそうだろう。ピケティはこの数字を「歴史的な証拠に基づいて」統計資料として提出し、マルクスのように直感と論理と推論のみでアプローチした不備を克服したと胸を張る。そのデータはオンラインで開示されている。このような不等式は、全社会的な富の偏在、アメリカの共和党大統領候補サンダースがいみじくもいった「グロテスクなまでに拡大した」経済格差が実在することの客観的裏付けとして今後広く引照されるだろう。
そしてピケティは問題の解決法として「所得税、相続税、年次の累進性のある資産税」を提案しているのだが、難はそれを誰が超高額所得者に強制できるかの問題にあり、最後には強制実行者として権力の問題に回帰せざるを得ない。権力の問題は、経済外的強制ではあるがいわば臨界領域としてマルクス経済学が内部にに導入せざるを得なかった項目である。事柄は再びマルクス経済学の問題圏内に戻ってしまうのである。池上氏は対談を「この本(『21世紀の資本』)が民主主義の本であることが確認できました」と如才なくまとめているが、果たしてどうなのであろうか。
二人目のE・トッドは、独創的な家族関係論を武器にマルクス主義に異論を唱える歴史人口学者であるが、これまた、別の角度から「経済格差の広がり」を指摘している。ヨーロッパの国際関係に見られる格差である。特に、ドイツとギリシャの間で顕著な経済的→政治的力関係の落差。トッドは「第1次大戦前の帝政ドイツ、1930‐40年代のナチス、そして21世紀のこれから」と三度にわたる実体験にもとづき、「合理的であまりに強すぎるドイツ」が「いずれ理性的な態度を逸脱していくだろう」とちょっと不吉な予言をしている。最近におけるその現れが、何あろう昨年日本でも大きな話題になったギリシャの財政危機である。ギリシャが債務減免や返済期限の猶予を求めたのに対して、ドイツは強く緊縮財政を主張して引かなかった。
今回のコラムの冒頭に「米よこせ雀」と題する写真を貼り付けたのは――だいぶ前の「デモクラ雀」もそうだが――拙老が庭にやって来るスズメたちの姿をギリシャの民衆に重ね合わせて見ているところがあるからだ。テレビの論調では働かずに要求ばかりしている、けしからんとかなり否定的だったようだが、拙老などはむしろ応援したい気分だった。ドイツはえらくギリシャを後進国扱いするけれども、考えて見りゃデモクラシーだってギリシャの方が大先輩ではないか。何てったって先様は西暦紀元前からデモクラティアの本場なのだ。民主主義の酸いも甘いも知り尽しているのではなかろうか。
[ギリシャ経済の再生のためには債務の減免が不可欠である」とトッドはいうが、その解決方は「昔からまるで変わらない」ドイツの強引な政策でついに実現することはなかった。自国フランスの隣に「強大すぎる」ドイツを持っているトッドは、対談の結びで池上氏に「あなた方日本の隣には、デカすぎる中国がある。そこがお互い悩ましい問題ですね(笑)」と話を振り、氏は苦笑して「冗談ではないですよ」と受け流すのだが、実はこのやりとりには、民主主義とデモクラシーをそう無邪気に等置してよいのかというかなり深刻な問いかけが孕まれている。
さて、三人目の対談相手の岩井克人氏については、日頃そのユニークな貨幣論から多くを学んでいる拙老としてはいずれ本格的に勉強するつもりである。残念ながら、主要な話題になっている「日本的経営」論にはあまり興味がないとしかここではいえないが、それでも一つ、池上氏との対話の中で、日本資本主義と中国経済との関わりに触れて発言したことが、おそらく偶然でなく、現今の中国株バブルが世界連続不況の引金になった事実を予見しているように思えるので、その点だけは記しておきたい。岩井氏はいう。
「今までなぜ大丈夫であったかといえば、中国経済が実践してきた資本主義というのは、要するに産業資本主義といわれている、古い形態の資本主義だからです。
これはカール・マルクスが前提としていた資本主義で、機械制工場で安い労働者を使って大量生産する。イギリスの産業革命後の資本主義がこれにあたります。
…… …… ……
共産党は投資ではなく消費による内需拡大政策に転換をはじめた。その政策のひとつが住宅振興だったんですけど、すぐ行きすぎて、住宅市場がバブル化しはじめる。習近平政権になって株式市場へと資金が流れるよう意図的に動かした。」
筋の通る説明である。そして、この間に生じた不良債権が溜りに溜ったマグマとしてはじける時、「リーマンショックと似たような衝撃」が周囲を襲うだろう。もちろん日本をも。そんな危機感を抱きつつ、氏はアベノミクスにも一言せざるを得ない。。今は「日本経済を内需中心に立て直して、中国バブル崩壊に備えるのが、アベノミクスの最大の存在理由であるとすら、私は思っています。しかし、いま安部さんはアベノミクスそっちのけで安保法案一辺倒なので、ちょっと心配になってきます。」
『池上彰世界の知性に聞くどうなっている日本経済、世界の危機』 文藝春秋刊
そろそろ『花の忠臣蔵』の書評が出揃う頃です。発行は去年の12月10日ですから今日で二月(ふたつき)近くなります。これまでの経験からいうと、毎回、刊行した本の世評――もちろん、たいがいは「売れない」という方向――が定まる時分なのです。たとえ一つでも新聞に書評が出れば、出版社は喜んでくれます。酷評でも悪口でも構いません。「悪名は無名に優る」という諺もあるそうです。
もとより人様に批評して頂いて、あれこれ文句をいえる立場ではございません。ですが、書かれるもののすべてが著者の気に染むかどうかはおのずから別問題だと存じます。いかにも逆さまながら、こちらから先方の読み方に注文を付けたくなります。歌舞伎のセリフで申すなら、「どなたもまっぴら御免なすって」というところです。といっても、拙老には今更『花の忠臣蔵』執筆の意図やら動機やらをむしかえすつもりはありません。また、既成書評家諸氏が書いて下さった文章を論評することも致しません。その代わりに、拙老が読んで「わが意を得たり」と快哉を叫び、「なるほど本書が言いたかったのはこういうことだった」と痛感させられた文章を以下に引用させて頂く所存です。多少我田引水に見えるかも知れませんが、引用元は、20年ほど前拙老の学生だった石原隆好氏の私信です。御本人は再録を快諾して下さいました。
なお同氏は現在インターネットにコラム「新・鯨飲馬食記」を連載中であり、時折、端倪(たんげい)すべからざる読書家ぶりを発揮して、犀利な書評を発表しておられます。本欄の読者諸賢もぜひ御一読を
⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘
『花の忠臣蔵』御恵投有り難うございました。
貧乏暇なしで仕事に追われておりましたが、昨日一気に読み上げました。
先生のブログ書評を拝読していても感じたことですが、具体的な歴史上の事象から超歴史的(汎歴史的?)な精神のアーキタイプを透視する視線が印象的でした。『花の詩学』の著者であればそれも当然の帰結と言えるのですけど。
法制度を越えた(法制度の地下に伏流する)ある倫理感覚を瀆されたと思った時に、誰いうともなく「コレハオカシイ」と呟き出すそのシンクロニシティがよく伝わってきました。とはいえ、この「空気感」が大勢を左右する体質、ちょっとやり切れないなあと思うのが半分の感想ですが(幕閣の「如何なものか」的官僚主義とそれは表裏一体をなすのではないか)。
もう半分は、あとがきで書いておられたような、《百万都市で、みんながワクワクしながら見てみないふりをするなか、集団で老人を切り刻むテロ行為》が、これはもう無条件にオモシロイと感じてしまうしかない、という無責任な劇場感覚です。言うまでもなく正義や忠義やといった徳目とは無縁のところで。民衆=the Great Beastとはよく言ったものです。野獣だけに端倪すべからざる直観も持ってるのでしょうが。
だからこそ余計に徂徠の透徹が光りますね。法理上の正義/不正では本来事切れない事象を、政治・社会的には穏やかに執り成し、法的には鮮やかに土俵に引きずり込んで決着を付けて見せたところ、さすがは随一の思想家とあらためて感心しました。
風太郎さんが言ってたことですが、忠臣蔵がなければ江戸はいかにのっぺらぼうの時代で終わっていたことか。いかにも日本的なエトスが産んだ事件=伝説がまた逆に日本人の感覚を規定形成していくという、まさに歴史の弁証法そのもののサイクルに一枝の花を捧げて下さいました。なんだか書評的な締めくくりになっちゃいました。
⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘

去年の暮(2015年12月)、批評雑誌『ゲンダイ』が創刊され、「特集 現代日本の批評」と銘打った「共同討議 昭和批評の諸問題 1975-1989」が載っている。主宰の東浩紀(あづまひろき)氏が司会をして、市川真人(いちかわまこと)・大沢聡(おおさわさとし)・福嶋亮大(ふくしまりょうた)の3氏が加わった4人の座談会である。主として1970年代生まれの新進批評家だ。80年代に生まれた人もいる。
この座談会は、かつて『季刊思潮』『批評空間』誌上で前世紀の80年代になされた共同討論「近代日本の批評」(柄谷行人・蓮見重彦・三浦雅士・浅田彰)が打ち出したパノラマ図を受け継ぎ、それをその通りにはやれないといわば否定的媒介にして、新世紀の問題状況に立ち向かおうとしている。その意図や壮。拙老はたいへん好意的に見る。が、現役世代の仕事をあれこれ論評するのは拙老のニンではない。ただ、何のはずみか、同座談会には一ヶ所だけ拙老の名前が出て来るところがあるので年甲斐もなく嬉しくなり、それを機会に物を言ってみようというわけだ。
共同討論の中で、大沢氏が発言したことを、東氏がこう引き取っている。
大沢 前田愛や野口武彦なんかは、研究者と批評家の中間に位置しましたが、近現代ではなく近世の専門家ですね。それが強みになっている。
東 いまの「カルチャー批評」に欠けているのは、まさにその距離感ですね。まさに「外部」。外国や過去から現代を見る視点。
へえ、そんな風に見えるのか、と拙老は感心する。買いかぶりもいいところだ。いつだったかももう思い出せないが、かれこれ35年ほど前のこと、突然柄谷氏から電話をもらって、「近代日本の批評」のシンポジウムにお呼びがかかったのである。参加したのは「大正篇」と「昭和篇」の一部だった。亡くなった前田愛氏の代役だったのだと思う。めちゃくちゃ緊張したのを覚えている。「外部」から見るどころではない。当時この業界では、「外部」という言葉――柄谷語だと思う――がやたらに流行していて、パソコンができなかった拙老などは「野口さんは江戸時代の人だから」とさんざんからかわれたくらいだ。江戸時代という日本の「内部」専門で、とても「外部」なんかお呼びではなかった。その後中央の動向からさっぱり縁が切れたのもそのせいだろう。
こういう新現役の進出によって、ほぼ10年ごとに交替する「新思潮」が小気味よく“相対化”されてゆく光景には、感嘆と詠嘆こもごもの複雑な感想を持つ。たとえば「柄谷さんは“勉強してないのに本質を突く”とか“海外の動向をぜんぜん知らないのに世界の最先端”みたいなことを言われすぎなんだよね。一種の神話がある」(東)といったような発言を見よ。先達をバッサリ斬る気魄に満ちているではないか。だがこれもけっきょくのところ、日本の思想界でこれまでずっと続いてきた“先進世代を相対化するゲーム”の継続版にすぎないのではあるまいか。拙老などほんの木っ端で結構であるが、前田愛氏は「プレニューアカ」(大沢)に位置づけられているから、10年新陳代謝論によれば80年代に消え去ったことになる。拙老も同断である。つまり、すでに「過去の人」の扱いだからいっそ気が楽だ。
80年代の「外部」はどこへ行ったのだろう。あれから無慮35年、拙老は「内部」にとどまりっぱなしで、いまだに忠臣蔵などに引っ掛かっている始末。その間、外界では輸入思想の新品入れ替えがどんどん進み、空回りして、一度見たような光景を繰り返しているような気がする。
今世紀はもう16年を数え、「昭和」の文物は今や回想と再評価の対象になった。昭和人にとっての「明治」のような存在と化したのである。拙老のようにもうだいぶ過去の人物になった者にも、まだ「現在地」を探すよすがはあるのかもしれない。 了
あてもなしに拙老の名を見出し語にしてネット・サーフィングをしていたら、幸いヒットしたまではよかったが、「ご存命のようです」と注記してあったのには苦笑させられた。なるほど、拙老もいつのまにか、世間からそう見られて当然の年齢に達しているわけか。古代ローマのキケロも「人生における老年は芝居における終幕のようなもの」(『老年について』、中務哲郎訳)と言っている。いずれ幕は下りる。いつまでも世間はスポットライトを浴びせ続けてはくれまい。
〽数ならぬ身にはあれども梓弓入りてまじらん世々の人数
この一首に篭めたギャグ(何が本歌か?)が通じない人はまだ若い証拠だと思ってどうかご安心下さい。拙老のひとりよがりなのも分かっている。年齢の証明書のようなつもりで口ずさんでみたわけなり。
拙老には世間から忘れ去られることよりも、もっと切実に身に迫る問題がある。他人が拙老を忘れるのは、自分が自分自身を忘れるよりまだはるかにマシなのである。
近頃、身近な人々の近況ニュースに「誰それさんがアルツハイマーの療養中です」といった知らせが多くなって淋しくなる。症状はいろいろあるようだが、記憶が壊れてゆくという点では共通している。「忘却とは忘れ去ることなり」というのは、この前の戦争が終わって間もない頃、一世を風靡した名高いラジオ・ドラマの言葉であるが、――まだ覚えている人はあまりいるまい――一種「忘却力」とでも呼べるような不思議な権能が老人たちに支配力を揮い始めている。拙老にとっては、どうもこちらの方が主敵であるらしい。
忘却は一見やさしい慰謝のかたちを取る。忘却は女身である。忘却の女神レテ。ギリシャ神話よれば、レテは死の神タナトスの姉妹であり、冥府に流れ込む大河の一つであり、よく「三途の川」と訳されるスティンクスの支流であるという。うっかりその流れに身を任せたら、いつしか冥府に運ばれかねない危険な水路である。これに対抗することはできないのだろうか。
ギリシャ神話には、なるほど記憶の女神ムネモシュネもいる。ヘシオドスの『神統記』によれば、ゼウスと交わって詩神ミューズを産む女神だ。しかし残念ながら「記憶」が「忘却」と抗争してこれに打ち克ったという伝承を聞かない。ヘシオドスも、ミューズがひとたび甘美な声で神々の讃歌を歌えば、たちまち人は「身の憂さを忘れ 切ないこともなにひとつ 思い出しはしない」(広川洋一訳)という状態になり、けっきょく、もう一つ種類の違う忘却に陥ってしまうからである。
ギリシャ神話に限らず――北欧神話でも記紀神話でもよい――神話的語彙がよく精神医学の用語に使われる――たとえばエディポス・コンプレックスとかナルシシズムとか――のは、神話に語られる原始的・野性的な、直情的な心性が人間精神の深層と通い合うところがあるからだ。語源(言語の深層)がしばしば人類の過去を明らかにするのと同じ構造である。このような用語圏を「神話的深層」の領域と呼ぶことにしよう。幼時だけが問題なのではない。老年期にさしかかった人間もまた、思考とか判断力とか精神の位相ばかりか、知能や本能をつかさどる脳髄のレベルで、数々の「神話的深層」でしかお目にかかれないような異象にめぐり会うのだ。
高齢化社会とは、老年という環境条件が普遍化した状況でいくつもの「神話的深層」がすれ違うことに他ならない。人は誰でもこうした各自にとって未曾有な、未踏の界域に踏み込んでゆくしかないのだ。今や、各人自前の個人的神話が活動期を迎える頃合だろう。
拙老もなりふり構っていられる年齢ではもうなくなった。若い頃にはその存在にさえ気付かなかった人や物と目を見交わしたり、声を掛けたりすることが多くなったとしても別に驚くには当たらない。最近、忘却の女神レテがたいへん親密に寄り添ってくるように感じられるのも決して嘘ではない。
◯ 水音も忍びがちなり夜の川太古ながらにレテは流るる
◯ われはしも忘れ形見ぞ人みなの思ひ出失せし後に残れる