[皆さんの声をお聞かせ下さい――コメント欄の見つけ方]
今度から『野口武彦公式サイト』は、皆さんの御意見が直接読めるようになりました。ブログごとに付いている「コメント欄」に書き込んでいただくわけですが、
同欄は次のような手順で出します。
トップページの「野口武彦公式サイト」という題字の下に並ぶ「ホーム、お知らせ、著作一覧、桃叟だより」の4カテゴリーのうち、「桃叟だより」を開き、右側サイドメニューの「最新記事」にある記事タイトルをどれでもダブルクリックすれば、その末尾に「コメント欄」が現れます。
そこへ御自由に書き込んでいただければ、読者が皆でシェアできることになっています。ただし、記入者のメールアドレス書き込みは必須ではありません。内容はその時々のブログ内容に関するものでなくても結構です。
ぼくとしては、どういう人々がわがブログを読んで下さっているのか、できるだけ知っておきたいので、よろしくお願いする次第です。以上
歌仙36歩の歩みのうちには時々マジックワードのような語句が出現します。たまたま選んだ一つの言葉が、思いがけぬ普遍性を獲得してしまうようなことが現実に起きるのです。これも歌徳の一種かもしれません。
今われら一同は『囀りに』歌仙の興行中で、ようやく初ウ8に差し掛かったところ――前途遼遠――ですが、前句の「 サーカスの去って残れる夏の月」(三山)に倉梅子が「茅の輪くぐりて息ひとつ吐き」で応じました。句中の「茅の輪」が問題のマジックワードです。「茅の輪」というのは「夏越祓なごしのはらえの時、神社の参道に設ける、チガヤで作った輪」(ウイキペデァ)のことです。もちろん夏の季語です。
ここでいつものルール通り、この初ウ8候補に寄せられた投句を5つ紹介しておきましょう。
⑴ 今朝より蝉のこゑそらぞらし(碧村)
⑵ 夏草すがし深呼吸終ふ (湖愚)
⑶ 茅の輪くぐるは隣の和尚 (倉梅、初案)
⑷ 浴衣の帯を鞭にすおとと (赤飯)
⑸ アイスクリンをねだるひろめ屋 (里女)
いずれも前句の「サーカス」をそれが去った後の喪失感といったものを句想の公分母にしている、と思います。一々の褒貶にはわたりません。座元の関心は、今回は特に「茅の輪」の一語に集中しました。この語がどんなキッカケで倉梅子の念頭に上ったのか知りませんが、おそらくサーカスの一演目にある猛獣の輪くぐりからの連想じゃないかと思います。まさかお寺の和尚さんはサーカスに出演しません。作者にたずねたら、「見た目そのまま」という返事でした。どこかのお寺で「茅の輪くぐり」が催されたのでしょう。(たとえば京都大覚寺。)
実をいえば、この点が一句立ちの俳句(単俳)と俳諧連句(連俳)の重大な分かれ目なのです。単俳ではリアリティの根拠は自分の体験・実感に求められます。これを「嘱目即吟しょくもくそくぎん」といいます。現代俳句はおおむねこの方向です。しかし連俳の世界では、一つの語句はたんに人間の外部にある事物を指向する(外示する)のではなく、その語句に内在している意味のスペクトルの帯全体を想起させる(内示する)ことを重視します。「茅の輪」は、たんに特定の植物の葉っぱを編んだリングではなく、これに祈り篭められた民俗的・土俗的心情――災厄を祓う――がたっぷり沁み込んだ言語対象なのです。かっては疫病よけの呪具でした。
『囀りに』歌仙の初ウ8に「茅の輪くぐりて息ひとつ吐き」の句を得たのには、もしかしたら言霊ことだまのはたらきがあったのかもしれません。初案の「隣の和尚」を捨てて第五句を「息ひとつ吐き」に改めた推敲の背後には、ひょっとしたら、いま敷島のわが国に迫っている疫神のすさびを句主が無意識に感知したからかもしれません。「茅の輪」はやっぱりマジックワードでした。
というようなわけで、初ウ8は倉梅子に決定です。「囀りに」句順表12参照。
〽つくばねの峰に文待つ人もがな調べ合はせん世々の歌口
次は初ウ9,雑の長句です。ぜひ御投句下さい。 尾
拙老の鰥宅を訪問看護してくれるヘルパーさんが、市中の公園で見かけたと早春の景物の写真を撮って来て下さいました。「梅に鶯」の構図です。よく見るとちょっとヘンです。画面で我が物顔をしている鳥がウグイスじゃないのです。これはメジロです。
この一葉だけじゃなく、世間に出回っている「梅に鶯」の写真には目白が代役をしているのが多いそうです。聞けば本物の鶯は、羽色が地味な上に目もパッチリせず、あまりインスタ栄えしないということです。
それにひきかえ、この一羽の鳥は如何にも恰幅かっぷくよく、写真に納まって悠然と構えています。〽東風こち吹きて匂ひおこせり梅の花国のえやみも知らず顔して
たしかに画中の目白は、憎らしいほどまるまると肥え、超然とドライな目をして、われ関せず焉えんと、足元の梅花の群などまるで眼中にない風情です。〽世はえやみ春もフェイクか梅鶯囀ばいおうでん、というところです。 尾
世が乱れると連歌・連句が盛んになります。歴史的事実です。天変地異人妖が世界に跋扈ばっこして、人心不安・社会物騒・経済低迷・気候不順・悪疫蔓延・手元不如意・お先真っ暗と不景気な類語ばかりが連なる昨今の時代が乱世でなくて何でありましょう。すなわち、連句の時代到来です。
こんな時代、人間関係は暗がりで見知らぬ奴とすれ違うようなものです。得体が知れない、気味が悪い、どんな害意を持っているか分かったものじゃない。そんな時、もし連句の応酬ができたらどんなにホッとするでしょうか。相手が自分と同じ文化を持っていることが確認できたのですから。すでに後三年の役ごさんねんのえき(1081〜1083)の時、二人の武人の間でこういう唱和がありました。衣館ころもだての戦に敗れて北へ落ちて行く安倍貞任さだとうに、追撃する源義家が「衣の館たてはほころびにけり」と下の句を詠みかけたところ、貞任はすかさず「年を経し糸の乱れのくるしさに」と上の句を返したという話が伝えられています。明らかに連歌になっています。
安倍貞任は先住アイヌ民族の血を引いているとされる北方の夷族だったのですが、義家はこの「異人種」と共通の文明を共有していることを感じたのです。つまり相手の気心がわかったのです。現代21世紀日本の乱世でも個々人同士がたがいに疎隔しあっている状況は歴史上の戦国乱世同然です。いや、ひょっとしたらもうそのサイクルに入っているのかもしれません。連句で共通言語を養うべき秋ときです。連句をやると相手の人となりがよく見えます。
さて、『囀りに』歌仙の初ウ7選評に取りかかりましょう。いつものように投ぜられた句案を紹介します。複数投句された場合は最終のものです。なお前句は「麒麟の兒らに刻まれる印」(里女)です。
⑴ 夏の月故宮の天を渡り行く 赤飯
⑵ 峰々をあますことなく夏の月 湖愚
⑶ サーカスの去って 残れる夏の月 三山
⑷ 月見草浮かべ飲み干す濁り酒 倉梅
連衆諸兄姉の狙いがだんだん定まって来ているので、座元はしごくご満悦です。みんな「夏」と「月」という基本的な条件はきれいにクリアーしています。ですが上には上があるものです。全体水準が 上がると、その条件をクリアーしただけでは不足だということになります。もう一つ注文が付きます。前句への付け筋をどれだけ意識しているかです。具体的には「麒麟きりん」をどう料理するかです。
難題です。皆さんだいぶ苦労されたようです。座元もハラハラしていました。でもこれが判断基準に加わった 結果、4句案のうち⑴と⑵をあまり悩まずに篩ふるいに掛けることができました。「麒麟」をあっさり無視しているように見えたからです。
⑶と⑷のどちらを取るべきか迷いました。まず⑶ですが、座元には或るカンが働いて三山子に「麒麟」を意識しているかとだけメールで問い合わせてみました。返事には「サーカスは熊象馬虎ライオンなど全てを連れ去ります。キリンはもともとサーカスにはいませんが、夏の月がキリンの幻影として空に残ります。無理ですか?」とありました。カンは正しかったようです。
⑷では倉梅子にえらく苦吟して貰いました。思案最中に野村克也さんの訃報が入って来たので、だいぶ目先が変わってしまいました。野村選手といえば「月見草」のボヤキで 有名ですが、実は句作の世界でも思わぬ広いものでした。「月見草」は夏の季語です。つまりこの言葉だけで「夏」と「月」がクリアーされますから、別に「夏の月」と吟じなくてもよいわけです。
「月見草浮かべ飲み干すにごり酒」の句案をメールで送ってくれた時のメモに「麒麟児=球児の路線を保持したくて苦戦しています。野球用語と月見草を両立しようとすると標語みたいになってしまう」「野村監督の現役時代は全然知らなくて、ぼやきのノムさんイメージが強いので、かつての麒麟児という事で…」と付言されていました。座元としては「麒麟児=球児」のアイデアが認知されているだけで大満足です。付け筋はちゃんと確保されました。しかし、ツキミソウを酒に入れて飲む場面には余りリアリティがありません。俳諧には俳諧なりのリアリティがなくてはなりません。だが言うは易く、実行は 難しい。座元にも「世を拗ねて日に背を向ける月見草」ぐらいの愚案しか思い浮かびません。ごめんなさい。
と、以上のような理由で『囀りに』歌仙初ウ7は、三山子の「サーカスの」と決定します。「囀りに」句順表12 次は初ウ8で夏の短句です。よろしく。 畢
連句は楽しくやらなきゃ嘘です。楽しくない人を無理にはお誘いしません。楽しみには色々ありましょうし、人によってさまざまでしょうが、一番楽しいのは自分の才覚で〈前句〉の鼻を明かすことでしょう。
連衆の句は必ず必ず誰かの〈前句〉に付ける〈後句〉であるわけで、その際〈後句〉の句主はかなりのフリーハンドを与えられます。たとえて言えば〈後句〉は〈前句〉を素材にして料理を作るようなものです。もちろん色々な工夫はされねばなりません。〈後句〉は〈前句〉の繰り返しを避けて、これを別世界に切り換えることが大切です。此れが「転じ」と呼ばれるものです。
さて今、初ウ6の場合はどうでしょうか。投句は4つありました。
1 娘横向き無言の化粧 湖愚
2 一人の時はマーラーを聴く 三山
3 不況のまちに鴉のおほき 碧村
4 麒麟の兒らに刻まれし印 里女
皆さんそれぞれによく「転じ」で下さいました。ただ転じ方に若干の精粗差が感じられます。今回の選考では、出来の良し悪しでなく、「付け筋」の適否が問題なのです。前句の「看板は年増マダムの十八番おはこネタ」で、この句からは《年増マダムがいつも閉店時間になるとオハコの芸をして見せる》とでもいった情景が目に浮かびます。この年増マダムの影が4投句それぞれの「付け筋」になっていると見受けられます。
まず2はあまりイメージが合いませんね。このマダムは、演歌ならともかく、マーラーを聴くとは思えません。3もちょっと視野がマクロすぎる。目に入るのはいいとこ「不景気」ぐらではないか。
1と4が残ります。ここでどんな句境でもそれなりに保持されていなければならないリアルさということを考えます。たとえ絵空事でもリアルで或る必要があります。古池の蛙はリアルに水に飛び込むし、大原の月夜にはほんとうに蝶が出て舞うのです。また、事実そのままも「ありのまま主義」というやつで、リアルということとはどこか違う。1は何だか家庭の実景の一齣のような気がします。きっと前句の年増マダムの所は母子家庭なんでしょう。
最後は4です。これは曖昧模糊あいまいもことしたよくワカラナイ句です。句主にも「麒麟」とはビールの広告に使われている霊獣のことか、動物園に入るジラフのことか判然としていないのだと思います。おそらくは[キリン]という音声表象が句主の頭の中で何かの観念と結び付き、何とも名状しがたい聴覚的実体に化してしまっているのではないか。句作の面では、この年増マダムが麒麟児を想像妊娠したというふうにでも解釈するこが可能でしょう。こうした荒唐無稽な感覚の方にむしろリアルさを感じます。
「囀りに」句順表12
以上のような理由から初ウ6の選考は、里女子の「麒麟の兒らに刻まれし印」に決定します。次は初ウ7の長句で、季は「夏」、「月」の座です。皆さん、どうか御投句下さい。 畢
お待たせしました。初ウ5が決定しましたのでお知らせします。4人から句案が寄せられています。前句は綺翁子の「ダイヤモンドで純情崩す」です。いつものように到着順に紹介します。
① 「おいそぎ」でくるくる回る槽の中 湖愚
② 三十路前かたき役にて返り咲き 里女
③ ガラス窓磨く心の透けるまで 三山
④ 看板は年増マダムの十八番(おはこ)ネタ 熊掌
執筆桃叟はずっと連句は単独行ではない、付句はいつも前句との――たとえどんなに気に入らず、肌合いが悪くても――共同作業なのだ、と言い続けて来ました。どんな場合でもどうにか付け筋を見つけて、強引に自分の世界に引き込めばよいのです。そこに後句の句主(作者)それぞれの持ち味が出ます。それが付け味です。前句の道具立てを生かした情景を作るのです。句主は時に情景中の人物にもなります。
そもそも今回の前句への付け筋はどんなものでしょうか? 桃叟の理解では(もちろん他の解釈もあり得ます):「誰か純情な女性がダイヤモンドの魅力に抗しきれず。ついに崩落する――物欲が色欲に優先する」というプロット(筋書)です。「恋」句には扱えますが、かなり冷たく突き放している所から「恋離れ」と見なせましょう。
さて、これを受ける4句の付け味はどうでしょうか? まず①です。洗濯機の水槽の写生と見えます。しかし前句とのつながりが不明です。連句として発想されているかどうかも疑問です。③は、「ガラス窓」を磨く動作を介して透けるようにする(1)心の持ち主は、もしかしたら、前句のダイヤモンドで崩された女性と同一人物かも知れませんが、三山子がそこまで深読みしているとは思えません。あるいは三山子はまったく別箇のシチュエーションを想定しているとも考えられますが、いずれにせよわがプロットからは外れるので採りません。悪しからず。
②と④ではどちらを採るべきか悩みます。②の「かたき役」として返り咲いた人物(女優?)は、一度ダイヤモンドによろめいた過去を持つ女だったという物語が影絵のように浮かんで来ます。しかし連想にワンクッション飛躍があるのが難のような気がします。④の方はもっと直叙的に落魄らくはくの女の情景をつかんでいます。昔手に入れたダイヤ もたぶん開店費用で使い果たし、今は老人客ばかりが常連になっているようなうらぶれたスナックバーのマダムの姿です。なれの果てといってもよろしい。あるいは別人かも知れません。前句と後句との間に介在する時間の隔たりが観音開きのリスクを救っています。
どちらにしようかと迷いますが、この歌仙では連衆の数を増やしたいというアドヴァンスを取って、熊掌子の④を採用しようと思います。これが捌きの決定です。
「囀りに」句順表 72ebf088e08b6530969491f8d01587ad 次は初ウ6の雑の短句です。熊掌子を加えて連衆の数は8人になりましたので、次回からは二度目の人のも採用します。「恋離れ」をしているので次句は雑という他には何の制約もありません。御投句をお待ちします。 畢
令和2年1月4日、拙老の鰥居かんきょに連句仲間の綺翁・熊掌・碧村三子来訪。歳旦開きの慣わしに従って 三つ物を作りましたので、ご披露します。干支は「庚子かのえね」にあたります。ネズミ年です。
鼠らが歯ア剥き祝ふ初日の出 桃叟
昆布巻模様裾割れの餅 綺翁
門々に萬歳まんざいの声広がりて 碧村
[評釈] 発句。現代日本語では「歯を剥く」と「牙を剥く」との区別が薄れているようですが、本当は大違いです。「牙を剥く」は、反抗する・反噬はんぜいする、刃向かう…といった意味ですが、「歯を剥く」とは、お世辞笑いをすることです。昔は、良家の子女は親から「女の子は人様に白い歯を見せちゃダメ」と教わったものでした。脇句はお正月によく見かける景物からイカガワシイ妄想を膨らませています。この作者はとかくバレ句――わからなかったらググるべし――に傾きがちですが、お正月のことですから。まあ大目に見ましょう。3句目はさすが若師匠の腕で、前句を品よくまとめています。「萬歳」は三河万歳のことで「バンザイ」ではありません。掛け合いの語句にはだいぶキワドイのがあるそうです。それが隠れた付け筋になっています。「て」止めにしているのも定石通りです。
[付つけたり] 桃叟自作。とにかく「カノトネ」が今回の戯詠の眼目ですので、この4音節の音声連続を三十一文字に読み込みます。できるだけ4つを分割せず、そっくりそのままにするのがコツです。いわば地口じぐちの原理です。
昔モテタ男に替りて 萎え侘びぬ干支一巡は夢のうちかのエネルギー今ぞ恋しき
男運の悪い女に替りて 今年こそ別れを告げんとにかくにかのエネロスの性悪な奴
[桃叟近況報告] 芳子が居なくなった後、桃叟の生活は若い友人たち――主として大学の教え子]――とご近所の方々の御助力で無事に維持されています。鰥居の日常の世話は、訪問介護センター、看護センターの皆さん(ヘルパーやトレーナー)が上手にローテーションを組んで、面倒を見てくれています。これも全部芳子が生前に用意しておいてくれたものだと思うと感無量です。
 現在桃叟が棲息している圏域は、トーテミズムとアニミズムが支配する時空です。それをマンダラ図のように絵解きしてみると、このページの写真のようになります。
現在桃叟が棲息している圏域は、トーテミズムとアニミズムが支配する時空です。それをマンダラ図のように絵解きしてみると、このページの写真のようになります。
まん中の信楽焼のタヌキは、最近運動不足気味になった拙老の自画像です。タヌキの右肩のあたりで諸他の人形たちを見下ろす位置にいる狐は故老妻のつもり。タヌキを囲んでいる左から大きなブタ・ヒヨコ・クマ・フクロウ・キツツキの順に並んでいるフィギュアたち(差し障りがあるといけないので人名と比定せず」)は、老人介護をして下さるチームの皆さん方です。
こんな調子でこれからのアディショナルタイムを生きてゆこうと思います。 了
お待たせしました。寄せられた句案が4つになりましたので選考にかかりました。候補になる投句は以下の4句です(順番は到着順)。なお前句は「押しボタン流し目に見る同じ階」(湖愚)です。
①特売場へとさっと駆け出す 三山
②屋根を伝ひて賊逃るらし 里女
③馴れ馴れしいと噂の主任 倉梅
④ダイヤモンドで純情倒す 綺翁
捌き主文:④の「ダイアモンドで」を初ウ4に治定します。
捌き理由:前句の句順は「恋」の3句目に当たっており、どう付けるか誰でも迷う所です。「囀りに」句順表
一応「雑恋」の扱いにできますが、前句とのつながりはちゃんと保ってなくてはなりません。恋句には いろいろな出し方がありましょうが、芭蕉による裁断の言葉が『去来抄』に記されています。「恋句出て付けよからん時は、二句から五句もすべし。付けがたからん時はしひて付けずとも一句にても捨てよ。」つまり恋句は付けやすければ五句まで続けてよいが、付けにくかったら一句だけでもいい、というのです。芭蕉だからといって、何もこれを金科玉条にする必要はありませんが、今はその権威に従いましょう。
4句とも目前の「恋」にいつまでも纏綿てんめんしていないのが特徴です。揃って「恋離れ」をめざしていると言えましょう。ちなみに「恋離れ」の句とは、「恋の前句に付けると恋になるが、一句独立しては恋の意をもたないもの」(東明雅『連句入門』)だそうです。
さて今の場合、「押しボタン」の前句に付けやすいか付けにくいかは初ウ4の句主の判断次第ですが、投句の4つを眺めると、①と②は付け筋の流れがよく見えない嫌いがあるように感じます。③は逆にいささか付き過ぎの所あり。前句のイヤラシイ手の触感がまだベッタリ残っていて、「恋離れ」をしようとするが振り払い切れていないという印象です。
④は一種の俤おもかげの付――『金色夜叉』を連想させます――で、恋が物欲に負けるというリアルな「恋離れ」になっています。これが本句を初ウ4に選考した理由ですが、他にもう一つ理由があります。それは綺翁子がこの歌仙の句主欄に名を連ねるのが最初だということです。句順表に明らかなように本歌仙の連衆はまだ6人しかいませんでした。この歌仙は「出勝でがち」方式でやっていますからあらじめ連衆は何人と決めませんし、こちらから指名もしません。もうしばらくこのシステムで進もうと思っています。皆さん、どうかダメモトぐらいの軽い気持で御投句下さい。
次は初ウ5「囀りに」句順表12、雑の長句です。
シラバス――参考資料。ユーチューブで『雑俳』を検索すること。動画がいくつもあるが、金馬のがいちばんよい。音声だけだがよく祖型を保っている。
◯歌仙連衆の一人に慫慂しょうようされてラインというものを始めてみました。ラインじゃないと拙生のブログが読めないなどとヌカスので太いフテエやつだと思いましたが、やてみると結構便利なものです。ただ妙なスタンプを貼ってくるのには閉口します。今の所は5人だけですが、あと少しは増やそうと思います。更新されたブログはグループには届くことになりますが、「ブログへの返信」はどうなるのですかねえ?
◯このたび三山子を「俳友グループ」にお迎えしようと思います。三山子はラインが苦手なので当分の間客分メンバーということになります。グループの皆さん、よろしくお願いします。
桃叟が三山子と接触するのは50年ぶりかと思います。東西にかけ違ってずいぶんになりますが、今でも最初に出会った頃のことを鮮明に思い出します。1958年の春でした。その頃、学生運動は低迷期にあり、W大学文学部の自治会室には誰も寄りつかず、閑古鳥が鳴いていました。そんな折、まだ細っこかった――彼がボクシングの猛者だったことは後で知りました――三山子と、仏文科に進んでマージャンの名人になったN君とのコンビがふらりと自治会室に現れてタテカン作りを手伝ってくれました。
それでゲンが付いてだんんだん人が増え、初めは2人だったのがでもが組めるまでの人数になり、ついに1960年の安保闘争の盛り上がり――大学だけで3000、神宮外苑で50000、国会デモに10万――という数に膨れ上がりました。鰻登りでした。それ以来、物事には波があるということに確信を持ちました。
それからざっと60年。桃叟は82歳になりました。三山子はちょっと若いくらいでしょう。この期間何をなさっていたのかよく知りませんが、俳句を修業されたと見えて、桃叟の連句グループに接触して来られました。下地は一句立ての俳句で、桃叟らとは多少流儀が違いますが、いい刺激になるでしょう。
ですが、同時に桃叟には60年前のゲンをかついでいる所があります。いくら「オイラあ年ア取らねえ」などと強がっていても、傍から見れば老翁に映るかも知れない。なるほど今の瞬間、まわりは人少なだけれども、このゲンにあやかって「夢よもう一度」ではないが、また再度の波の高まりが見込めるのではないか。
現実に戻りましょう。われらは60安保世代の、いや、60年に始まる20世紀思潮の空気を21世紀に持ち伝えられる生き残りです。北小路も唐牛も西部も死にました。黒羽もいなくなりました。井汲も高橋も亡き人になりました。生き残った面々にもそれぞれすることがあるでしょう。あいつは今何かしているらしい、と思うだけでも励みになりましょう。
生き残った個々人は「点」にすぎませんが、点と点を結べば「線」になります。たとえ「面」は無理でもこのくらいはお互いの助けになるのではないかな? 「俳友グループ」とは、決して等質な人間のアンサンブルでなく、何かと突っ張り合う、個性なんてものではない孤立した「点」どもが「線」でつながったものの集合なのです。
◯次のブログで、『囀りに』初ウ4を治定して次に進みます。 了
このたび日頃の連俳仲間を誘い合わせて「俳友グループ」という名称でラインを始めました。スタートは5人からです。追々ふやしてゆくつもりです。
これを機会に、くどいようですが、連俳と一句立ての俳句――これを「単俳」と名づけます――との違いをハッキリさせておこうと思います。というのは、なまじ俳句のうまい人ほど連俳への切り換えがダメなのです。失敗はしばしば得意芸をしている最中に訪れるものです。秀才根性は禁物です。
連俳は両性合意のもとでなされる行為であるのに対して、単俳は自己完結をめざします。あんまり上品なたとえじゃなくて恐縮ですが、悪くすると一人Hのようなものにもなる、と申せましょう。いいものでも自己セントラリズムなのです。客観性に偽装した主観性が発露するのです。
もちろんすべてがそうではありません。向井去来には「尾頭の心もとなき海鼠なまこかな」(『猿蓑』)のような秀作があります。これは発句として作られていますが、この後に脇句以下が続いた話を聞きません。単俳は言いっ放しの句なのです。(ちなみに『猿蓑』とは元禄年4年1691に出た蕉門の発句・連句集で、『芭蕉七部集』所収のものはその連句だけの部分です。)
偶然、拙老のもとへ三山子の近作俳句が送られて来ました。『二〇一九年』と題し、一月ひとつきに3句ずつ偶作を選び、全36句を集めたものです(『世代の杜』小説所収)。三山子はおそらく誰か師について本格的な修業をしたと見受けられ、句集にしてもよいほどこの道をたしなんでおいでです。たとえば12月の掉尾を飾る「年つまるいまだ参らぬ墓二つ」の一句は、拙老の心を打ちます。
この句は単俳ですから、必ずしも返句を要求してはいません。だから、これに連句で応じるのはたがいに他流試合になりましょうが――――
年つまるいまだ参らぬ墓二つ 三山
西風寒き富士の夕陽せきよう 桃叟
どなたかこれにもう一句付けて「三つ物」にしてくれませんか。

去る12月5日に亡妻芳子の『偲ぶ会』を開きました。芳子との別れを本当に悲しんでくれる友人知己二十六人の心のこもった集まりでした。
いくら余命はどのくらいか知らされてはいても、別れはあまりにも急だったので茫然自失の日々が続き、方々に訃報を伝えるのもひどく遅れました。故人はいろいろな方面にお友達も多かったのですが、住所氏名・メールアドレスなどがスマホの中に散らばっていて、親疎の度合などもわかりかねました。そんなわけで、決して多人数ではないが参加者の心が通いあう清楚な集会になりました。ご出席の方々に感謝すると共に、連絡の行き届かなかった方々にお詫び申し上げます。
会場では遺影に献花して下さった皆さんが一人一人、代わる代わる故人の追憶を語ってくれました。拙老の教え子たち、神戸高校同級生、アメリカ時代の旧友、英語教育関係の知己、マンション住人などいろいろの分野から人々が集まって下さいました。拙老は改めて、亡妻が立派に現実生活で活躍し、拙老に欠けている能力を発揮して拙老を守り立ててくれていたことに思い至りました。拙老は無力で何もしてやれなかったことに恥じ入るばかりです。最後に亡妻を『送る言葉』を――拙老に構音障害があるので――司会者に代読してもらいました。以下、その文章を採録させていただきます。
◇ ◇ ◇ ◇
芳子を偲ぶ言葉
芳子。
きみはぼくにとっては「過ぎた女房」でした。
今になって改めてしみじみ、きみがいかにぼくのことばかりを考えていてくれたかを感じています。
きみは大勢の人に親切でした。大勢の友人たちを持っていました。そんなきみがぼくを人生の伴侶に選んでくれたことは、思えば大変ラッキーなことでした。しかしぼくはそれにすっかり甘え、「ありのすさびに」かまけてワガママばかり言っていました。ごめんね。
ずっと苦しい副作用に耐え続けてくれた君を、もっともっと大切にしなかったことがつくづく悔やまれます。
きみとはここ神戸で五十年一緒に過ごしました。まるで特別な時間と空間が、二人のまわりに開けているかのようでした。空に雲が流れ、丘に風が吹き、日が照っていて、二人が永遠に暮らす幻の国土がそこにうち建てられたみたいでした。
きみは長い闘病のうちに人間を見る目が怖いほど澄んできて、うわべの同情や言葉だけの「友情」を鋭く見抜くようになっていたよね。お座なりの・口先だけの・世間智流の・処世的な応対や友達のふりを敏感に察知したっけ。ぼくも感化されて相手の人となりを感じ分けるようになったと思います。今日の『偲ぶ会』にも、きみをなつかしみ、心からきみとの別れを惜しんでくれる本当の友人知己の方々に来ていただきました。
芳子。現在ぼくはずっと共に生きてきた住居の一角できみの骨を守って暮らしています。どんな宗教にも社会慣習にも介入させません。寿命の続く限りこうして一緒に住み続けましょう。いつかそう遠くない将来は、富士山麓の『文学者の墓』で寄り添って眠りましょう。それまで待っていておくれ。
二〇一九年十二月七日 野口武彦
◇ ◇ ◇ ◇
また会場には、講談社の横山建城氏ならびに米国インディアナ大学名誉教授のスミエ・ジョーンズ氏から追悼文が寄せられました。併せて再録させていただきます。
◆ ◆ ◆ ◆
オトタチバナヒメ 横山建城
野口武彦先生の著作の刊行をお手伝いするようになったのは『慶喜のカリスマ』(二〇一三年)から。まだ十年にもならない。それでも『忠臣蔵まで』『花の忠臣蔵』『元禄六花撰』『元禄五芒星』と五冊を担当してきた。
最新作「崩し将棋」(『群像』二〇一九年十一月号)も単行本化を見据えて掲載した。「桃叟だより」をご覧の方ならご存じであろうが、すでに脱稿した短篇がほかにいくつかある。それらをまとめて一日も早く六冊目にしたいのだけれど、それを芳子夫人にお目にかけられなかったと思うと、ただただやるせない。
夫人は亡くなる二ヵ月半ほど前に、本の宣伝費の提供を申し出てこられた。それが既刊に対してのものなのか、遠からず出すべき新刊のためにということなのかはわかりかねたが、ちょっと驚く金額だった。私は「お話はまことに有難く存じますが、宣伝等につきましては版元の責任できちんとやりますのでご安心を」といった、じつに空疎な返信をした。
送信アイコンをクリックしたあと、強烈な自己嫌悪に襲われた。ご病気の芳子さんは、「どうかご立腹になられずお教えいただけないか」「私が野口の仕事の役に立てそうなことはもうこれくらいしかありません」と記してこられた。おそらく余命を悟っておられての、よくよくの言なのだ。それなのにこんな返事しかできないとは、なんと情けないことか……、と思った刹那、私には芳子さんとオトタチバナヒメとがオーバラップして見えた(あまりに唐突な連想だが、これは私が三浦半島の出身だからかもしれない)。
オトタチバナヒメが夫ヤマトタケルをどう思っていたかは、古事記中の絶唱に明らかである。野口先生と芳子さんのあいだにも、余人の知りがたいさまざまなことがあったろう。一方、海神の怒りを鎮めるとてヒメが走水の海に身を沈めたとき、それを呆然と見ていた愚かな従者がいたはずである。私は芳子さんの最期の一念にふれたのに、マヌケなことしか言えなかった。いまとなっては、武彦先生の「吾妻はや」の思いをかたちにして、一日も早く芳子さんのご霊前に捧げることがわが任だと期している。
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
野口芳子様に初めてお会いしたのは、1982年、アール・マイナーさんの音頭取りで、ワシントンDCで共同研究のセミナーがあった時でした。野口武彦夫人として同伴なさった芳子さんとはウマがあって、食事やレセプションの時間などにはお喋りしたものです。控えめなところがありながら話題に尽きず、爽やかな方という印象でした。それ以後は、太平洋を隔てていますから、時に電話を頂くというお付き合いでしたが、野口武彦さんの著書を頻繁に頂き、ご夫妻とは親友と決め込んでおりました。彼が肝臓の疾患で入退院を繰り返す間、芳子さんは看護に身を削る毎日だったと想像しておりました。阪神大地震のただ中で、彼を背負ってマンションの外の塀の上から押し出して救助したのも、失意のどん底にあった彼に生きていく決心をさせたのも、その後彼が禁酒して著作に専心するようになったのも、すべて彼女の献身的な愛によるものと思います。大震災以後の彼は、『安政江戸地震』を皮切りに、政治批判と歴史批判の名作をほぼ年間1作という驚愕的なテンポで上梓していますが、どれも彼と彼女の二人三脚のたまものに違いありません。最後にお会いしたのは、阪神大震災の2-3年後のことです。丁度日本に行っており、あまり記憶が定かではありませんが震災の爪痕はすっかり除かれ、書庫など立派に改造されていました。天井が落ちて潰れてしまったマンションの片付けや改築に芳子さんは随分苦労なさったことでしょう。マンション住民の間では、個々に改築して行くべきか、全体を取り壊して新築するかという議論が続いて、夜な夜な徹夜の会議があり、責任感が強くて働き者の芳子さんは睡眠不足の日々だったことでしょう。有能にして包容力のある、素晴らしい友人でした。愛する人を徹底的に守った女性でした。ご逝去をお悔やみ申し上げます。
◆ ◆ ◆ ◆
今回のブログはずいぶんと長くなりましたが、事柄の性質上どうか御海容下さい。桃叟識。

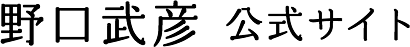


 現在桃叟が棲息している圏域は、トーテミズムとアニミズムが支配する時空です。それをマンダラ図のように絵解きしてみると、このページの写真のようになります。
現在桃叟が棲息している圏域は、トーテミズムとアニミズムが支配する時空です。それをマンダラ図のように絵解きしてみると、このページの写真のようになります。