どうも大変な時代に生き合わせてしまったみたいです。この3月24日現在で世界中のコロナヴィールス感染者は32万4000強、死者数は14000強。どう見てもパンデミック状態です。あれよあれよと言っているうちにイタリヤが世界一になりました。さすがデカメロンの本場です。
こんな時代には、人間の心は不思議に「先祖がえり」をするものです。誰もがたとえ半信半疑でもオハライやヤマイヨケ、ヤクヨケといった神事・仏式・両者混淆の効験に期待します。口では俗信だとか民俗的慣習だなどと言いながらも、それにあやかろうとするわけです。 現に京都の諸神社には疫病の退散を祈願する「茅の輪くぐり」が飾られています。人間はおのれの不安を吹き払うために輪をくぐり、そうすることによって古い伝承の底に眠っている無意識の記憶に安息のよすがを求めるのです。
現に京都の諸神社には疫病の退散を祈願する「茅の輪くぐり」が飾られています。人間はおのれの不安を吹き払うために輪をくぐり、そうすることによって古い伝承の底に眠っている無意識の記憶に安息のよすがを求めるのです。
こういう御時世だから「不要不急」のことはせぬようにというオカミのお達しです。さしずめ俳諧連句のように悠長なことは自粛せよということらしい。たしかに俳諧文芸は五七五を定形とする短小な詩形からいって、あまり複雑な思惟内容を盛り込むのに向いていないし、多くを十七文字に収めることは不可能だという制約があります。正岡子規も「時事雑詠の俳句をものせんとする」のは「文学以外の事に文学の皮を被きせたる者なり」(『俳諧大要』岩波文庫p.23――インターネットの青空文庫でも読めます)と一刀両断です。要するに、俳諧と時事はすこぶる相性が悪いのです。もちろん川柳の滑稽とは話が別です(p.75)。
果たしてそうでしょうか? 時事とは同時代の出来事(社会事象)の総体でしょうが、俳句のスペースではそお全貌を捉えることなどとても無理な相談です。が逆に、その短さを独鈷とっこに取って、同時代性を切り取る技法を活用することです。時代をズバリと裁断する劈開面を一語に凝縮して言い取ることです。それを一句立ての俳句(単俳方式)で実現するのは難しいでしょう。ですが、連句にならできます。何人もの連衆がすれぞれ独自の旋律・節奏・音調をもって同じ一つの時代相を発現するのです。ちょうど倉梅子の「茅の輪のイメージがたとえ無意識にでも「時疫」に対する同時代人の集合的不安を感じ当てていたように。
さて、『囀りに』歌仙初ウ9の選評にかかります。まずルール通り投句のご紹介から。
①人語して子に犬からむ垣根越し 湖愚
②御普請を仰せつかりし書状にて 碧村
③世やもろき戦火をあおる天狗風 里女
④丁寧に手洗い嗽うがい八十路入り 三山
座元としては、本歌仙のこの局面では「時疫」への不安という時事的なテーマが時代を越えて人々に共有される世界感覚に徹底的にこだわりました。それを基準にしていますから、4句に対してもしかしたら公平でないかも知れません。①は「人の話声がするので耳をそばだてたら、垣根の向こうで子供と犬がじゃれていた」という情景のようだ。まるで緊迫感なし。②は、この投句に「時疫に由来する緊迫感とはめられると窮屈なので、世界を切り替え」た旨の断りがありました。座元は「はめる」のが望みです。残念ながら意見不一致。③は、本当をいうと入選させるつもりでした。ところが「野ッ原に忘れられたる魔法瓶」などとトボケていた三山子が、突然閃いて④の「丁寧に手洗い嗽八十路入り」の一句が送られてきたので、順位が逆転してしまいました。
この句は、一見八十老人のボヤキというただの私感のごとくですが、流行り風邪を怖がる心境を言い取って、それなりに一時代の普遍的感覚を捉えているのではないか。意外に広い公共の「場」――いわば歌仙空間――に吹き抜けていると思われます。入選にします。参照「囀りに」句順表12
次は初ウ10で、雑の短句ですが、11句目および12句目が「11 花の定座(枝折しおりの花)12 折端(花の綴り目)」というふうに続きますので、この10句目はふつう「花前の句」と呼ばれ、次の連衆が花を吟よみやすいように作るのが習わしです。軽い調子で、後句の色彩を奪わないようなのがいいそうです。 尾

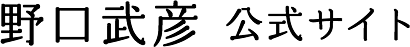
手は洗ったもの暗い夜道。まあ、川柳か狂歌ののりなのですが。
掲ぐる松明 吹き消す風神 熊掌