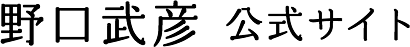2016-10-18
<
この「野口武彦公式サイト」もいよいよ2年目に入りました。昨年2015年10月3日に「初口上」を載せてから今年の10月8日の「夢の岡(続)」まで、全53回を週に1度のペースで書き続けました。辛抱強くお付き合い下さった読者の皆さんに心からお礼を申し上げます。ずいぶん勝手で独りよがりの記事もあったと思いますが、何とぞご容赦下さい。
お蔭様で、読者数――ヴィジター数というべきでしょうか――は安定しました。このところのアクセス数は1ヶ月で3143、1週で936,1日で141といった数字になります。また、検索エンジンのランクもこの4,5日グーグルでもヤフーでも「野口武彦」の見出しでは第2位に付けています。第1位はウィキペデイアで、これを抜くのはなかなか難物です。ちなみに、ウィキの拙老の人物評は気に入りません。
それはともかく、上記の数のヴィジターは、いったいどのような人々なのでしょうか。
第25回の「わが仮想読者」にも書いたのですが、拙老の想定する読者はだいたい下記の3種類に分類できました。①同年代者――いわゆる「60年安保世代」の党派を超えた戦友たち、②神戸大学の卒業生、世にいう「教え子」たち、③年令も閲歴も職業も立場も不明不詳の「読書人」たち。このうち、①は急速に老化・死滅しつつあります。拙老などは文字通りの「生き残り組」なのです。②もおっつけその後を追うでしょう。残るのは③だけです。
そこで上記の数字のことになるのですが、実をいうと拙老には3143という数の意味がまだよく読めないのです。①②のグループは総数でも100人ぐらいのものだと思います。すると、残る③のグループはおよそ3000人ほどいることになります。さあ、これらの人々がどんな顔つきをしているかがさっぱり掴めないのです。
現代はビッグ・データの時代だといわれます。データの大量作戦です。数量が 物を言います。しかしデータとは結局、特定の分布を持った数値であって、統計にすぎません。3143という数は 決して ビッグではありませんが、理屈は同じです。この数の塊りは今のところ「不特定多数」しか意味していません。ここでもあのアンビヴァレント・アンビギュアス・アモーフォス(ambivalent,am-biguous、amorphous――どっちつかず、あいまい、無定形)という不特定多数者に特有の3Aの原理がまた作用するのでしょうか。何にせよ、数字の上の多数が必ずしも多数派でなく、いつ離散するかも知れない無定形な集団であるのは心もとない限りです。
でも拙老が最後に頼みにするのは、やっぱり③のグループしかありません。「わが仮想読者」で、かりに「読書人」と呼んでみた今では少数派に属する人口集団です。
現代は記号と映像が 氾濫する時代です。文字は記号化 されて一種の音標文字になり、映像が文字を代行するようになっている世の中です。だから、むしろ「読字人」という新語を作った方がいいかもしれません。字が読めるということは普通考えられているより、はるかに大切な能力ではないかと思います。これはまだほんの直感というだけで、皆さんはじれったく感じられるでしょうが、今はこの程度のことしか言えません。追々このカンが指し示すものに肉付けを施しつつ、本コラムを書き続けてゆく所存です。(了)
[皆さんの声をお聞かせ下さい――コメント欄の見つけ方]
今度から『野口武彦公式サイト』は、皆さんの御意見が直接読めるようになりました。ブログごとに付いている「コメント欄」に書き込んでいただくわけですが、
同欄は次のような手順で出します。
トップページの「野口武彦公式サイト」という題字の下に並ぶ「ホーム、お知らせ、著作一覧、桃叟だより」の4カテゴリーのうち、「桃叟だより」を開き、右側サイドメニューの「最新記事」にある記事タイトルをどれでもダブルクリックすれば、その末尾に「コメント欄」が現れます。
そこへ御自由に書き込んでいただければ、読者が皆でシェアできることになっています。ただし、記入者のメールアドレス書き込みは必須ではありません。内容はその時々のブログ内容に関するものでなくても結構です。
ぼくとしては、どういう人々がわがブログを読んで下さっているのか、できるだけ知っておきたいので、よろしくお願いする次第です。以上
2年目に入る
夢の岡 (続)
(承前。江戸=東京プランの続き)
古本屋を兼ねた汁粉屋を後にしてなおも夢の散策は続きます。台地はその辺で尽きてそろそろ東側の低湿地に向って坂道が下って行きます。現実の地理では下りきった向こうの先には上野の山があるはずです。筆者不詳の古随筆『望海毎談(ぼうかいまいだん)には、上野・湯島、谷中(やなか)の3つの岡は「昔は芝浦の海の潮、この所まで入り来る入江の続き」とあります。つまり現在の埼玉県南部に浦和とか川口とかの地名が残っていることからも知られるように、6千年前の「縄文海進(じょうもんかいしん)」の頃、この辺には南北に長い入江が伸びていて、海進期が終わると共に、入江はどんどん後退して多くの沼沢を残した低地に姿を変えました。不忍池(しのばずのいけ)はその名残です
ですが、「夢の時空」を語るにあたっては、固有地名はあまり問題になりません。それは一種の抽象的構造体であり、そこでは高低・距離(遠近)・曲直などの要素が特定の組み合わせで基本的に繰り返され、夢を見るその都度一回的に具体的な時空(いつ・どこ)に当て嵌められて行くという塩梅です。
さて、汁粉屋を出た後、道筋は定かではありませんが、拙老の夢は下降過程に入ります。高台からずんずんずんずん下りて、ごみごみした町中へ入って行きます。角を曲がって横町へ。さらにまた曲がって袋小路と見まがう抜け裏に。店がいっぱい並んでいます。売っている物も飾り付けも俗悪で、あたりから陋巷(ろうこう)の匂いが漂ってきます。そこには貧困と悲惨と猥雑のすべてがありました。店に座って媚を売っている女たちの身なりも化粧もだんだんけばけばしくなり、赤い腰巻きも目に付きます。その一画を過ぎると、見世物小屋が2つありました。
とはいっても、どちらも間口が9尺、奥行き2間の長屋仕立てになっています。2つとも活人形(いきにんぎょう)の趣向でした。最初の部屋は『四谷怪談』の一場面で、お岩様がまだ毒を飲まされる前の美しい武士の妻の姿ですんなりと立っていました。次の部屋では、『桜姫東文章(さくらひめあずまぶんしょう)』の悪漢釣鐘権助(つりがねごんすけ)が土間にしゃがみ、褌を外し、紫色に膨れ上がった自分の逸物を取り出して見物人に誇示しているのでした。
(2)「芦屋―神戸コース」
初めに関西の地理を説明すると、芦屋と神戸の間は非常に短くて、六甲山麓と大阪湾の海岸線の間の細長いベルト地帯に住宅地が切れ目なしに続いています。3本の鉄道が平行して走っています。上から下に阪急・JR・阪神と並びます。芦屋から神戸大学のある六甲までの間には私鉄でもJRでも2つ3つしか駅がありません。岡本・御影などの地名で知られる割と高級な住宅街です。と、これが現実のマップなのですが、これが「夢の時空」ですと異様に変形・肥大するのです。地図にはない鉄道路線が南北に延びていて、六甲山系を突き抜けて中国山地のただなかにまで達しています。その終点に盆地があり、そこに明治時代に創建された地方貴族の子女が通う保守的な校風の女学校があるのです。今も古風な和装ハイカラな制服の生徒たちがトロッコ列車で通学しているのが見られるといいます。
(3)「地下道―刑場」コース。
夢がこの方位――東西南北のどちらでもなく、垂直の軸にぶれている――に進みかけている時は、あらかじめ意識下で警報が鳴り響きます。誰かが必死で、「あ、そっちへ行ってはいかん、いかん」と声を掛けてくれるような気がします。でも、いったん進み出したらもう引き返すことはできず、いったら怖いと知りながらも、おしまいまで歩かされてしまうのがこのコースです。いつか物の本で読んだ「反復恐怖」という言葉を思い出します。
たいがいは地下の坑道か地下水道のような暗く長く狭い空間をしゃにむに前進しています。その空間は進めば進むほど狭窄して暑苦しくなり、自分が腸管の中を経巡ってどこか盲管状態にある器官に押し込められ、圧縮されているように感じられます。何かが鼻孔・口腔・咽喉に詰まってイヤな味がしてきます。屍灰のようです。「おまえは今、刑場の地下にいるのだ」といつものナレーションが聞こえます。目を開くと、すぐ頭の上に異様にやさしい温顔をした巨大な石地蔵が立っていました。(了)
鳥のあれこれ
2016-09-18 |
リハビリのために屋上に出る日が多くなったせいで、この辺に棲息する鳥たちとおつきあいする機会が増えました。芦屋の町は六甲山麓と大阪湾岸の間の狭い平地に細長く東西に伸びた地形をしています。つまり海と山の距離がたいへん短いわけで、わがマンションの上空は鳥たちにとっては恰好(かっこう)の通り道になっているようです。代る代るいくつかの種類の鳥たちとお近づきになりました。
よく眺めていると、鳥たちはめいめいに適した高度でたくみに棲み分けているのがわかります。いちばん高く暮らしていのは、夏の間ずっと、何といってもツバメでしょう。スピードが違います。たまに空中で他の鳥とすれ違っても、俺たちはおまえらとはチガウンダとでも言いたげな態度で、スイスイ飛び抜けてゆきます。時々チュッチュッと囀るだけでだいたいあまり鳴きません。お高い鳥なのです。そんじょそこらの、特急の名前にされたこともないようなフツーの鳥と一緒にしないでほしいという気持が見え見えです。
しかしツバメは意外に低いところに巣を作ります。マンションのピロティ式駐車場の天井に作った巣に、毎年のように戻って来て、賑やかに雛を育てます。気さくだというより、まったく人間を怖れないのです。日頃人間からどう扱われているかが問題なのでしょう。たとえばハトなどはひところ高層階のバルコニーに住みついて、やたらに巣を作っては嫌われていましたが、すぐに追っ払われました。あまり人に好かれていない鳥です。
巣を作るといえば、今週の写真(左)に撮った鳥の巣には、雛だけが写っていて親鳥の姿がありません。実をいえば、何という鳥かもわからないのです。親鳥の留守中に内緒で盗み撮りしたのです。とても警戒心が強いので、もしいたら嘴でつつかれていたかもしれません。この巣も本当は2,3年前に作られた古巣――子供が取ろうとして管理人さんに叱られていたことが拙老の記憶にあります――でして、現在の親鳥が廃物利用したものと見えます。これは地上の、一階通路脇の植え込みの物蔭にある樹木に作られたものです。その鳥はたしかヒヨドリでした。写真には不在の親鳥もたぶんそうなのだろうと思います。ちなみに、写真を撮った後、この巣からは鳥の姿が親子ともども居なくなりました。きっと危険を感じて棲む場所を変えたに違いありません。
ヒヨドリの姿は屋上では見かけませんが、名前がちょっと異なるイソヒヨドリはここの常連メンバーです。エレベーターホールのいちばん高いスペースの見えない所に巣を作っているみたいで、親子で囀り交わす美しい声が屋上じゅうに響きわたります。時々雄か雌か知りませんが、綺麗な青い羽毛をした鳥があたりを飛び回りながらいい咽喉を聞かせてくれます。あぶなっかしく羽根をバタバタさせながら隣のマンションの屋根にたどり着くのは、ついこの間まで雛だった今年の若鳥でしょう。
頻度という点では、同じようによく見かけるのがセキレイです。うちの屋上に来るのは、残念ながら色の地味なセグロセキレイらしく、特徴のある仕草で長い尾羽をヒョコヒョコさせながら、せわしなく移動します。北の方にある谷川の川原に帰る途中、羽根休めに立ち寄るだけなのでしょうか。毎度、ご滞在になる時間が短くて、すぐに居なくなってしまいます。
しかし何といっても、いつも憎たらしいほど存在感があるのはカラスです。たとえ姿が見えない時でも、必ずどこかで睨みを利かせているみたいで、カラスが近くにいる時は、上に紹介したような鳥たちは姿を見せません。カラスに逆らわないように息をひそめて隠れている気配です。しばらく無人の、ならぬ無鳥の舞台が続いた後、どこかから一声カアと響きます。「来るぞ来るぞ」と思っているうちにまず一羽が視界に現れます。たいがいは隣マンションのテレビアンテナの上に止まって、四方に呼びかけるように啼き立てます。すると方々からそれに対する応答の啼き声が帰って来るではありませんか。たまには応答ナシの日もあります。カラスは辛抱強く何度も何度も啼き続けます。声も姿もひどく孤独そうで、やっと返事が返って来るとこっちがほっとするほどです。
でも多くの場合、カラスの群れは憎らしいことの方が目立ちます。いつかなどは4,5羽のグループが集団でスズメ(?)を追っかけているのを見たことがあります。必死で高空に逃れる小さな鳥を追ってカラスも日頃そこまでは上がらない高度を無理して飛び、やがて雲にまぎれて見えなくなってしまいました。可哀想な小鳥の運命はどうなったのでしょうか。気がかりでなりません。(了) [この項はもと2016/9/18に発表したものですが、何かの都合で消えてどまったので再録しましす]
夢の岡
いつもこれから夢の世界へ入ろうという時、拙老はきまってまず始発場所のようなところへ案内されます。かといって、別に待合室のような場所がるわけではありません。夢に出発する浮遊魂はたいがい拙老一人で他に人影は見えません。いたかも知れませんが、それらはけっきょくもとは単一体である浮遊魂の片割れたちでした。その場所に着いてから,その晩の行く先が決まるのです。
その場所は、繰り返し訪れるのでだんだんわかってきたのですが、なだらかな岡です。うとうと寝入ってからしばらくの間は闇雲に歩きますが、ふと気が付くといつも見慣れたなつかしい風景の中に立っています。それが岡なのです。なだらかな傾斜があり、拙老はその半ば――岡の中腹の小径――に立っており,行く手の視界は鞍状をした岡の稜線にさえぎられ、向うの高い空だけが見えます。このまま小径を登り続けて岡の上に達したら、どんな景観が目の前に広がっているだろうか。期待感に満ち満ちて、夢の中の拙老は足を速めます。……しかしながら、拙老はいまだかつてその景観を目にしたことはありません。そのいわば《究極の夢景》はついに抽象的な願望にとどまり、具象化されることはないのです。というより、いつもその辺で誰かが――白い手袋をした夢の「見えざる手」か、狂言回しか、それとも夢の水先案内人か――すばやく場面転換をして,浮遊魂を次の場景に送り込むからです。
拙老はこれまで、岡から新たに入って行く先の地理は夢を見る日によってまちまちだと思っていました。ところがそうではない、ということに最近気が付きました。もちろん、地名の固有名詞や風景の細部には小さな異動はありますが、大体において訪れる土地にはいくつかの基本的なパターンに分類されるようなのです。主なものは以下の3つです。
第1の部類は「東京―江戸コース」とでも名づけるべきプランです。周知のように、「プラン」という横文字語には地図・平面図・透視図といった原義が生きていますが、この紀行プランは文字通り、「江戸」とも呼ばれ、「東京」とも呼ばれたこの特定の界域を「透視」するのです。
浮遊魂はおおむね東京駅から「国電」――JRになる以前の名称です――に乗って、お茶の水か水道橋で下車します。昔の地形では両駅とも旧神田川の水路だった低湿地にあり、本郷台地へ上る勾配のきつい坂道が幾筋も連なっています。夢の浮遊魂も当然その一筋を上ります。あたりに建ち並ぶ家々はみな土塀に囲まれ、内側の様子は見ませんが、重そうな瓦屋根、格子窓など由緒正しい武家屋敷の作りです。その辺をしばらくぐるぐる歩き回った末に、ようやく横町が見つかって安心します。小路の奥に昔――いつの世とも知れぬ遠い昔――から懇意にしているなつかしい老夫婦が開いている古い汁粉屋があります。いつも甘いゼンザイを注文して小豆餡が黄金色にとろりと熟れているのに見とれて安心します。隣に古書肆があって、店に美しい装幀の本が並んでいます。まだ読んでいませんが、拙老はその内容をよく知っています。それには、拙老が今生に至るまでの全過去が記されているのです。
今回は充分字数を使ったので、この続きおよび第2、第3のプランについては来週に廻します。(続)
ヒガンバナ幻想
今年もうちの猫の額にヒガンバナが顔を出しました。この花にはえらく律儀なところがあって、毎年9月の下旬には必ず地面から花芽が伸びて来て、あっという間に花火のような、長すぎる蘂(しべ)に特徴のある花を開きます。なにしろ花がある時には葉がまったくなく、葉が出ている時には花がないというヒガンバナ科植物の通性にしたがって、いきなりひょろひょろした花茎(かけい)を伸ばすのですからこちらは不意打ちを食らうわけです。でも毎年、開花の時期は正確で、ああ秋の彼岸が来たのだなあとカレンダーを見直したりします。いったいどんな遺伝子の記憶をあの鱗茎は蓄えているのでしょうか。寒暑の変動で時期が早くなったり、遅れたりするサクラやモミジとは大違いです。ヒガンバナの狂い咲きなどついぞ見たことがありません。
ヒガンバナの写真はインターネットにいいのが沢山ありますので、今回はわざとわが庭の貧弱なやつで間に合わせます。それも一昨年のものです。今年のは、残念ながら、1,2輪花を付けたと思ったら台風くずれの風雨に吹き折られてしまいました。みごとなヒガンバナの名所なら日本各地にあるでしょうが、拙老が第一に思い出すのは皇居濠端のヒガンバナの群落です。もう一つは、今から50年も前のことですが、大学院生の頃、天理図書館で調べ物をした帰途、近鉄電車の窓から見た眺めです。奈良盆地の西山に落日が沈みかけ、最後の放光を浴びて沿線の田畑が黄金色に輝いていました。その時、畦道(あぜみち)に点々と散乱していたヒガンバナの赤い花叢は忘れられません
ヒガンバナという名称は、学名をLycoris radiataというヒガンバナ科ヒガンバナ属の多年草に与えられた和名の一つです。マンジュシャゲ(曼珠沙華)という仏語系の名前もよく知られています。♪赤い花なら、曼珠沙華。オランダ屋敷に雨が降る……なんて歌謡曲がありましたっけ。他にも実に多くの異名や方言がありますが、どれも揃って不吉な・凶々(まがまが)しい・縁起の悪いものであるのは決して偶然ではないでしょう。江戸時代の18世紀から19世紀への変わり目の頃に刊行された『重修本草綱目啓蒙』(ちょうしゅうほんぞうこうもくけいもう)に烈挙されているヒガンバナの名称はざっと次の通りです:シビトバナ、ジゴクバナ、ステゴノハナ、シビレバナ、ヤクビョウバナ、カラスノマクラ、キツネノシリヌグイ、カエンソウ、ノダイマツ、シタマガリ、ハミズハナミズ、それにハダカユリ。あまりにも語彙が豊かなので思わず笑ってしまいます。
こんな風に暗い感じの命名が多いのも、ヒガンバナが墓場に植えられていたり、路傍に植え捨てられていたり、野火を連想させたり、まあロクなことが思い浮かばないからでしょう。たしかにお仲間にはアマリリスという西洋種のものがあり、これも葉がないうちに花だけが出るというヒガンバナ科の特徴を見せていますがこれとてもあの妖艶さの裏にはどこか悪女めいた陰翳があるようです。そういう印象を与えるのは、やっぱりヒガンバナが毒草だからでしょう。ヒガンバナ科の植物はすべて一種宿命的にうっすら微毒を帯びているのです。そのたたずまいは全身で、ワタクシッテ有毒ナ女ヨというメッセージを発しています。(www.shuminoengei.jpより)
ヒガンバナは江戸時代に備荒植物とされていました。含有されているのはリコリンというアルカロイドは毒性がそれほど猛烈でなく、水に晒して毒を抜き、飢饉時には澱粉質として食べたそうです。もちろん、あまりお勧めできませんが、ともかくそんなことができるのも、ヒガンバナの毒性がそれだけ稀薄だからでしょう。同じアルカロイドでもトリカブトのアコニチンとなると猛毒で、実際に殺人事件も起きています。2種類のアルカロイドの違いは、双方の化学式のカメノコを比べれば一目瞭然です。無論、拙老はバケガクの門外漢ですが、亀甲模様のデザインを見るだけでも、アコニチンの獰猛さが露呈されているような気がしてなりません。
ともにWikipediaより
甲山に異変
今住んでいるマンションの屋上がちょうど手頃な運動場になっていて、足のリハビリに役に立つので、週に3,4回は歩行器か杖を使って屋上を一周することにしています。いつも途中で適当な場所にしつらえてあるベンチで一休みします。ここからだいたい3時の方向に甲山が見えます。写真の通り、ここ芦屋からはごく小さくしか見えませんが、それでもその特徴のある山容は、標高309.2mの割にはよく目立ち、時々それを眺めるのは拙老の生活の時間にアクセントを与える天然のランドマークになっています。
甲山は大昔の火山の痕跡です。1200万年前に噴火していたそうです。200万年頃始った「六甲変動」という地殻変動で隆起してできた六甲山系とは生成が違います。だから甲山は六甲の連山から離れてぽつんと孤立しています。背丈も六甲の山々が900mクラスなのに比べると小柄で、こぢんまりとしているのも魅力です。しかしそうした自然地形の上に人間の目はまた別箇の図柄を描き出すものです。あたかも夜空の星々の無秩序な散乱の上に、人間の創造力がいくつも架空の補助線を引き、さまざまな星座や星宿の絵面を浮き出させるのと同じ寸法です。
屋上から目を少し南に転じると、ほぼ5時の方角に大手前大学を裾野に控えた独特の形の丘陵が横に長く見えます。四足歩行をする恐竜が地面にうずくまる、というより、まるで伏せて攻撃態勢を取っているように見受けられますので、拙老はひそかにこれを「イグアノドンの岡」と名付けて楽しんでおりました。いつか時が来たら、この恐竜はジャンプして甲山に襲いかかるのではないかと空想が膨らみます。地上に奪われた海底の宝珠を取り返そうとする伝説の竜王のように、「イグアノドンの岡」は甲山の宝珠状の山頂部に飛びかかって噛み付くに違いありません。その「時」とはいつでしょうか。もちろん、甲山が再度噴火する日です。
甲山が火山だったことを知らない人は多いようです。リハビリでお世話になっているセラピストさんもその一人でした。彼女は大阪南部育ちでこの屋上から、空がよく晴れてアベノハルカスが「まる見えに」なる日はたいへん上機嫌で歩行トレーニングも優しくなります。そうそう、アベノハルカスはここから6時の方向に見えます。それはさておき、甲山の噴火の噴火が近いという話は、折しも桜島や阿蘇、それから箱根に立て続けに火口変動があった頃なのでだいぶ信じられたようです。うっかり冗談をいうものではありません。
つい最近、甲山にまた異変が生じました。山の色が何だか変になったのです。遠景写真では目立ちませんが、近景で芦屋市内の六甲支脈の中腹を写したのを見ると、起きていることがはっきりします。緑に混じって赤みを帯びた梢が多くなっているのに気付きます。9月にしては早すぎる紅葉ではありません。枯れかけているのです。
この現象にいちばん最初に目を付けたのは例のセラピストでした。「今年はモミジがいやに早い」というので気を付けて見ていたら、赤いシミはどんどんシラクモのように広がって行きます。インターネットで調べてみたら、これは「ナラ枯れ」といってカシナガキクイムシ(略称カシナガ)という害虫の媒介によるナラ菌の繁殖の結果、ミズナラ・コナラ等の樹木が枯死したものだそうです。被害が今後どの程度広がるかはわかりませんが、目下全国で予防措置が取られて いるとのこと。参考のために、かつて甲山が禿山(?)だった時の写真を掲げておきます。古いものなので、やはりインターネットの『西宮ブログ』「明治以降の甲山の姿」http://nishinomiya.areablog.jp/bungakusanpoから拝借しました。
最近の御時世では何が起きても不思議はない世の中ですが、せめて六甲や甲山の眺めは永遠に緑をとどめていてもらいたいものです。写真のオヤジの禿頭みたいに見える箇所は裸山なのか、背の低い灌木に被われているのか、これだけではわかりませんが、どっちにしろあまり見てくれのよいものではありません。そういえば昔『わが谷は緑なりき』という映画がありましたっけ。(了)
サルスベリ慕情
 サルスベリの花を見るたびに夏の連日の陽射しを思い出します。それも昭和20年(1945)の戦争最中の真夏です。もしかしたら、枝から一斉に紅桃色の炎か噴き上げるように花群を咲き開かせるサルスベリの形状と、同年の東京大空襲の時、くっきり眼に焼き付いた米軍の焼夷弾の炎の色とが一つの心象風景の中で融合しているせいかもしれません。はるか後年、メキシコで街路樹のカエンジュ初めてを見た時、「この花は昔見たことがある」という錯覚に襲われたことがあります。
サルスベリの花を見るたびに夏の連日の陽射しを思い出します。それも昭和20年(1945)の戦争最中の真夏です。もしかしたら、枝から一斉に紅桃色の炎か噴き上げるように花群を咲き開かせるサルスベリの形状と、同年の東京大空襲の時、くっきり眼に焼き付いた米軍の焼夷弾の炎の色とが一つの心象風景の中で融合しているせいかもしれません。はるか後年、メキシコで街路樹のカエンジュ初めてを見た時、「この花は昔見たことがある」という錯覚に襲われたことがあります。
それらの日々、小学校――もとへ! 国民学校であります――の一年生だった拙老は山梨県甲府へ疎開していました。それも昭和20年4月13日の城北大空襲で淀橋区(現新宿区)柏木の家を焼き払われた後、急遽、甲府の親戚の家へ転がり込むという間抜けな疎開でした。甲府上空は、東京をめざすB29の編隊がすぐ南に聳える富士山を目印に飛来し、東旋回して方角を転じる飛行ルートだったにも拘わらず、人々はすこぶる呑気(のんき)で「かつて武田信玄を守った自然の山岳地形が敵機爆撃に対する強い味方だ」(山梨日日新聞)といって悠然と構えていたそうです。しかし甲府の町は同年7月6日の深夜、絨毯爆撃を食らって炎上しました。
拙老一家は甲府空襲の直前に東京へ帰っていたので、その様子は知りません。甲府は盆地の町です。そこへ絨毯爆撃ですから人々は逃げ場を失い、火災によるフェーン現象も起きて現場はかなりの惨状だったようです。後になって苦労話をいろいろ聞かされましたが、そうなる以前の、甲府がまだ空襲を知らなかった時分には、拙老は何しろまだ数え年9歳の、東京で空襲の炎火をくぐり抜けてきた少年でしたから、珍しがられ、周囲から何となく畏敬の眼差しを注がれていました。一種「語り部」的な少年だったのです。『戦災の思ひ出』という作文を書いて先生にも褒められました。
疎開先の家には小さな庭があり、その片隅にサルスベリの木が植わっていました。花が咲くまで拙老は何という木か知りませんでした。初めは、何だか幹のツルツルした妙な木が生えていて、それが盛夏になったら急に花を付けて存在感を主張しはじめたのが目に留まったのです。ピンクの炎がにわかに燃え立ったような花の梢の下に一人の女性がしゃがんでいたのが印象的でした。その情景はそれから70年経った今でも鮮明に記憶に残っています。
その女性は何をしていたのでしょうか。一人で泣いているのを見たような気がします。でも当時9歳だった拙老には、それは覗いて見ることを許されない、遠い世界の出来事のようでした。その甲府の家は、郊外に持っている広い土地で牧畜をやっているとかの旧家で、町中の家にも使用人が何人かいました。その女性もそうした使用人の一人でした。因習的な当家の主(あるじ)との間に、いろいろ男女のことなどがあったのかも知れません。その頃の拙老は、何しろ天使のように純潔でしたから、その辺の事情とはまったく風馬牛だったのです。ほんとです。
拙老の記憶はその情景でふと途切れてしまい、そこで記録映画のフィルムがふっつりと中断したように、それから先はありません。その女性は程なく実家へ帰って、空襲で死んだと戦後になってから聞きました。
戦後の東京は見渡す限り焼野が原でしたが、植物の中でも強靱なものはしぶとく生き残りました。サルスベリもその種類だったのでしょう。戦後の東京に訪れた猛暑の夏、炎天と瓦礫にむしろお似合いの風情で一緒懸命咲いて見せている花があり、あれがサルスベリだと人に教えられたのが、この花の名をきちんと覚えた最初だったと思います。つまり、この花に関する知識はいくつかの段階で拙老の頭に入ったわけです。最初はいやに官能的な幹の形と肌の色で、二度目は鮮やかな紅色の色調で、三度目に、形と色が女人のイメージに複合して。
サルスベリは、その花と樹形の全姿から、いつでも独特な波長のエロティシズムの磁波を発散しています。(了)
スティーヴン・キング著 『ジョイランド』
ジョイランドというのは遊園地のことです。21世紀の遊園地はテーマパークなどと呼ばれ、やたらに規模が大きく、スペクタキュラーで、設備にもテクノロジーを駆使した豪華なものばかりが目立ちますが、作中に出て来るサウス・カロライナのジョイランドは、語り手にして主人公デヴィンがいうように、「ディズニーワールドの足もとにもおよばないがそれなりに目立つ広さ」があるくあいの、こぢんまりした適正スケールの、まだどこか牧歌的なところが残ったものなつかしい場所です。ここが一つの青春精神劇の舞台になります。
もっときちんといえば、その遊園地のアミューズメント施設の一つである「幽霊屋敷」で事件は起きます。日本にもよくある「お化け屋敷」みたいなものでしょう。仕掛けだったと思っていた幽霊が本物だったのです。
時は1973年。同じキングが『アトランティスのこころ』で描いたように大学キャンパスで反ヴェトナム戦争運動の波がうねり、また、アメリカン・ドリームが破れて人々が多元的な価値観に分裂して、思い思いの目標を追求し始めていた時代です。ですが、主人公はそうした大問題には関わりを持たず、むしろ平凡に、アルバイトをして学費を稼いだり、手頃な女子学生と恋愛・失恋をしたりと、まあごく普通の学生生活を送ります。この「普通さ」の中に、主人公が目撃し、かつ解決するホラーじみた殺人事件が起こるのです。物語は、40年後の回想という形でなされます。
この小説は一応ミステリーですから、書評にもルールが適用されます。犯人が誰であるかを言ってはならないのです。その点に留意して話題から外し、ここではちょっと意想外かもしれませんが、キングのホラー小説から透けて見える無意識の宗教観いついて考えてみようと思います。
何かのエッセイで、キングがぽつんと洩らした言葉があります:自分が書くホラー物の根源には、どうも、幼少年時に教会や家庭で無意識に刷り込まれた悪人が死後行く地獄の恐怖がひそんでいるようだ、と。この「教会」が、どんな宗派、どんな教団に属しているかは、拙老が忘れたのか、そもそもキングが言及していないのか判然としませんが、まあありきたりのメソジスト監督派とか福音派とかだったような気がします。つまり、その下地は意外に「常識的」だったようなのです。そういえば、題は忘れましたが、SF系の作品群には、作中人物が気に入らない奴を超能力で宇宙の外に追放する話がいくつか出て来ました。この宇宙の外というイメージは、そこに光も音も時間もないただの空無の広がりがあるという《絶対外部》の直覚像になっています。その辺地へたったひとりで放り出されるのですから、その徹底性においてこれは地獄の原層です。
また近作『アンダー・ザ・ドーム』では、人間が蟻をレンズで集めた光で焼き殺すように、人類をほしいままに生殺与奪して別に残酷とも感じない超知能を持った高度の宇宙知性体が想像されています。これなども子供の頃さんざん聞かされた神の全知全能がいかにもSF的に造型されているといえます。
しかし幸いにキングの宗教的下地は現在世界中で――もちろんアメリカでも――抬頭しているファンダメンタリズム(原理主義)とは無縁なようです。最近,アメリカの「聖書根本主義派」のうち、「天啓的史観」を標榜(ひょうぼう)するグループの間では「キリストの再臨は世界核戦争というハルマゲドンを経てこそ実現する」という信念が強固に形成されていると言います。同じ主張をしているわけではありませんが、トランプさんなどの言動を思い合わせるとちょっぴり心配になります。
話を『ジョイランド』に戻しましょう。作中には、主人公デヴィンを失恋の痛手を癒やし、命を助け、性的救済まで施して主人公を青春彷徨から抜け出させるアニーという年上の女が登場します。この女性の暴君的な父親が、ゴリゴリの原理主義者のテレビ説教師に設定されていることに、拙老はキングという作家が現今の宗教問題に対して取っている絶妙なスタンスを感じます。「悪魔だって聖書を引用できますから」という作中主人公の言葉には、作者キングならではのアイロニーが篭められていると感じます。(了)
狸のカツレツ
これも昔の夢です。昭和45年(1970)6月のある夜のことでした。神戸市青谷の下宿で、泣きながら目を覚ましたのを覚えています。6月27日(土)と古いノートにありますから、拙老が満33歳になるちょうど前夜にあたります。
小ダヌキが生きながらカツレツになって、皿に載って運ばれてきます。パン粉の衣の下に。油で揚げられて白くなった肉が見えています。小ダヌキはまだ生きていて、手足をバタバタ動かして皿の上でウクルクル回ります。目に涙をいっぱい溜めてこういうのでした。「みんな雄々しく戦ったのに、ぼくだけは何もできなかったんです。だからこうなれって皆にいわれて、。カツレツにされたんです」。夢の中で、拙老は連れの老教授に大声で叫んでいました。「もうこんな料理はイヤだ!」
カツレツになったのはタヌキであって、拙老自身ではありませんでした。拙老はミゼラブルなタヌキを見ている第三者です。もっと正確には、タヌキの災難の目撃者です。ただ、この第三者はいささか過剰な感情移入をしています。その点を除くならば、この夢の場面運びは、いわゆる《夢の文法》における「転移」の原理を定石通りに踏まえているといえます。ここに前回少し申し上げた「夢人称」の問題が微妙にからんできます。つまり、夢では――以下これを夢空間あるいは夢界と称します――、一人称が直接現れることはなく、たいがいは三人称に仮想して登場します。今の場合、カツレツになった狸がそうです。このタヌキにはかなりの度合で拙老の一人称が「転移」していると見て間違いないでしょう。
思い返してみると、拙老は1970年代をずっと故知れぬ罪障感と共に生きていたような気がします。自分が生まれつき、それこそ先天的。先験的に深い罪業を背負っているような感じでした。理由のない自責の念とでもいったらよいでしょうか。傍目にはずいぶんお調子者のように思われていたかもしれません。しかし、飲んでいても冗談ばかり言っていても、いつも心中どこかでは自己懲罰への欲求がありました。罰は誰が受けるのでしょうか・
無意識は嘘を吐きません。意識の防御網が利かないところで、その網の目が破れたところで、ホンネは夢界の前舞台に躍り出ようとします。カツレツになった狸などは好例です。はとはいえ、油で挙揚げられるのは夢空間でも拙老の「私」ではなく狸なのです。してみると、夢は相当強力な防衛機構であるともいえそうです。(了)
夢占
「夜さまざま物思いにふけり、いつ寝入るともなく眠りに入って自然に夢をみている」と、江戸時代中頃の文人柳沢淇園が随筆『ひとりね』に書いています。淇園はあの柳沢吉保から苗字を許された一族に生まれながら、武士=治者の生き方を嫌い、文人画家としてディレッタント的一生を選んだ変わり種です。少年時から英才教育を受けて育ち、えらく早熟で、十代から遊里に入り浸り、女体鑑賞にかけては一流の鑑識眼をもっていました。そんな淇園ですから、夢でもさぞや「夜ごとの美女」を堪能したと思うのですが、当人は不満げにこう書いています。
「たまたま恋しい人に会っても、相手はいっこう嬉しそうな顔をせず、自分があちらを向くと相手はこちらを向くという風に拗ねた姿を見せる、そしてその姿が男に変わったり、ひょいと硯箱みたいになったりして、いやはや何とも取り留めのないものだ」(92条)。
しかし、たとえそんな風に取り留めないものであり、「夢幻」という言葉があるように夢はまとまりがなく、定めないことのたとえにされるようなものであっても、昔はそれほど怪しいものだとは考えていなかったようだと淇園はいい、『周礼(しゅらい)』に見える「六夢」を引いています。①正夢②霊夢③思夢④窹夢(ごむ)⑤喜夢⑥懼夢(くむ)の6つです。それらを解釈して、未來を予測する夢占(ゆめうら)の材料にしたそうです。一々注釈することはしませんが、「喜夢」は「喜悦して夢みるなり」としているのが面白いところです。淇園にいわせれば、古代の聖人は「夢のようなものをさえ自分の心から出た物だとして、決して軽視されなかった」(『柳淇園先生一筆』)のですから、その夢を見たとき自分が喜悦している状態だったことはすこぶる大切なのです。
さて、これからお話する拙老の夢などは、さしずめ間違いなく「喜夢」に分類されるでありましょう。古い夢です。神戸に来て間もない1968年の頃のものです。青谷という場所にあった下宿の一部屋で見た夢です。拙老はまだ30歳そこそこの年齢でした。
不思議なことに、この夢の話者はI教授でした。拙老を神戸の大学に呼んで下さり、たいへんお世話になった人物です。夢中の出来事の一切は、教授の語りとして進行します。語られたことがすべて夢者、夢見人(ゆめみにん)たる拙老の目の前で起こるのです。それどころか、空気の揺らぎや水の波動の感覚もそっくり残っています。言い替えれば、I教授の話の中に拙老の五官がそのまま復原されていたのかも知れません。
青谷の下宿はいつのまにか浴室になっていました。まん中に置かれた大きな浴槽には硫酸銅の色をした湯が湛えられ、その中にI教授がゆったり漬かっていました。浴室の戸が開き、女子学生が一人、一糸まとわぬ姿で近づいて来ます。誰も入っていないと思っているようで、浴槽のへりをまたいで湯に漬かろうとします。が、すぐにI教授に気づき、キャアと羞恥の嬌声を発すると、両手で乳首と恥毛を蔽い、あわてて全身を湯に沈め、頭から水に潜って泡のように溶けてしまいました。
続いて2人目の女性が現れ、同じような仕草をして水に溶けました。その後も3人目、4人目、5人目と同じ情景が続きました。その一部始終を拙老は夢の中で眺めていました。
それから今日(2016年8月20日)までこの奇妙な夢を人に話したことはありません。I教授にも、あの夜夢に出現した往年の女子学生たちにも、です。固有名詞は差し控えますが、すでに他界した人もいますし、その後かなり体形の変わった方々もおあれます。しかし今からほぼ半世紀前には、皆さん、剥きたての水蜜桃のような肌をなさっていました。その実物は時間の風化作用によって見る影もなくなっているかもしれませんが、イメージは夢像の記憶に永遠に滅びることなく保存されています。
この夢はいろいろな概念を思い起こさせます。まず「夢の話法」、それに関連して「夢の人称」。拙老にはいまだに、この夢の主人公はI教授であるのに、I教授が登場する場面を見ていたのが拙老だったというカラクリが腑に落ちません。拙老はいったいどこにいたのでしょうか。能楽用語でいう「見所」という言葉を思い出します。普通、観客席を意味するとされますが、実際には夢幻能を見る人――ワキの見る夢をさらに一回り外から見る――という意味の超越的視座のようなものであり、ことによったら拙老はそんな視座にいたのではないでしょうか。(了)