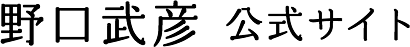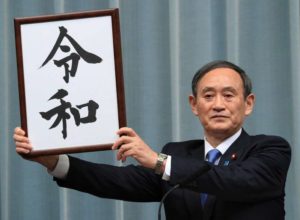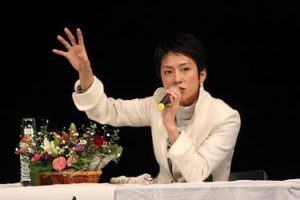[皆さんの声をお聞かせ下さい――コメント欄の見つけ方]
今度から『野口武彦公式サイト』は、皆さんの御意見が直接読めるようになりました。ブログごとに付いている「コメント欄」に書き込んでいただくわけですが、
同欄は次のような手順で出します。
トップページの「野口武彦公式サイト」という題字の下に並ぶ「ホーム、お知らせ、著作一覧、桃叟だより」の4カテゴリーのうち、「桃叟だより」を開き、右側サイドメニューの「最新記事」にある記事タイトルをどれでもダブルクリックすれば、その末尾に「コメント欄」が現れます。
そこへ御自由に書き込んでいただければ、読者が皆でシェアできることになっています。ただし、記入者のメールアドレス書き込みは必須ではありません。内容はその時々のブログ内容に関するものでなくても結構です。
ぼくとしては、どういう人々がわがブログを読んで下さっているのか、できるだけ知っておきたいので、よろしくお願いする次第です。以上
連俳初学ういまなびの栞
われらが「囀りに」歌仙もどうにか初折の裏を迎えました。初ウ6を公募中のところ現在3句の投稿が寄せられています。いずれも力作ですが、どこかアチャムケホイの印象を否めません。どうにかしなくちゃと思います。とはいっても、かく申す桃叟自身が筑波嶺つくばねの道にはとんと不案内、皆目かいもくドシロウトと来ていますので処置なしなのですが、むしろこれを勉学の機会として、先人の踏み分けた後をたどって歩きにくい道を進んでみようじゃないですか。
誰が作ったのか「歌仙季題配置表」なるものがあり、当「囀りに」歌仙もそれに従って36句のそれぞれに季を配当しています(「囀りに」句順表参照)。しかし参考のため連俳史に残るような名歌仙のいくつかをひもといてみると、みな必ずしも格にとらわれず、自由にのびのびとやってるようです。「春秋は同季五句去りで句数は三〜五句。夏冬は同季二句去りで句数は二〜五句。恋句は三句去りで句数は一〜三句。定座なし。ウとナオの内に各一箇所」といった細かな決まりが運用にも柔軟な幅があります。思うに、季語の配当はおおまかな目安であり、動かぬ準縄規墨ではないのです。句に季があるのは、俳語を無制限な数の語群から絶対フリーハンドで選ぶのではなく、季語の枠組みに絞り込むためだと心得ればよいでしょう。語句は限定された方が作りやすいのです。
理屈をいうより、実作に徴してみましょう。芭蕉が元禄2年に奥の細道紀行の途次に巻いた「秣まぐさ負ふ」歌仙というのがあります(岩波文庫『芭蕉連句集』、柳田国男『俳諧注釈』所収)。全36句を見る必要はありませんが、初学びの糧としてその最初の7句を掲げます。
1 秣負ふ人を枝折しおりの夏野かな 芭蕉 夏
2 青き覆盆子いちごをこぼす椎の葉 翠桃 夏
3 村雨に市の仮屋を吹とりて 曽良 夏
4 町中を行く川音に月 芭蕉 月
5 はし鷹を手に据えながら夕涼み 桃隣 秋
6 秋草ゑがく帷子かたびらは誰たぞ 曽良 秋・恋
7 もの言へば扇に顔を隠されて 芭蕉 雑・恋
今、われらの「囀りに」歌仙で連衆諸兄姉が苦吟されているのは7句目・8句目であります。7句目の「恋」には『秋」のシバリがあり、「恋」を必須とはしないが、恋を扱うなら秋の気配・気分、気色を漂わせたいものです。8句目の恋には何の制約もありません。純愛でも色情でも何でも構いません。御存分にどうぞ。
ところが、6句目倉梅子、7句目里女子はどちらも早くも「恋の呼び出し」の予感を漲みなぎらせているように感じられます。里女子に至ってはモウスンジャッタ印象です。次の8句目はタップリ秋っぽくお願いする次第です。9句目はノビノビとやれるのだから、一句ぐらいはお澄ましでいったらどうでしょうか。 了
いやあ、有難いことです。
この『囀りに』歌仙も、諸兄姉のおかげで、いよいよ初折の裏に入ることになりました。第二ステージ入りです。句順はその1句目、いわゆる「折立」になります。今回も付け勝ちの形になるよう公募方式を呼びかけたところ、嬉しいことにたいへん盛況で、なんと全部で5句の投稿がありました。紹介します。配列は到着順です。
① 酒盡きてさても夜長のプルースト 碧村
② 秋風の吹き抜けてゆく不破の関 三山
③ 野分晴れわがたましひもタブララサ 里女
④ 銃声に獣等(ケモノラ)逝きし秋の山 綺翁
⑤ 闇騒ぐ野分の朝髪梳きぬ 湖愚
うーん。捌きする身としては嬉しい悲鳴です。どれを見ても個性タップリ。兄たりがたく弟たりがたし。玉々混淆(「玉石混淆」なんて恐れ多くて言えません)、いずれがアヤメカキツバタとはこのことです。でもこの中から1句だけ選び出さなければなりません。それぞれに方法的難癖、修辞的イチャモンによって選評に変えることにしようと思います。
①読書の秋ですね。右手に酒杯、左手に詩書という構図は一幅の文人画を連想させますが、読むのがプルーストとはねえ。句中の酒はワインぐらいでないとしっくりこない。ちなみに「葡萄」は秋の季語。オヤマア、これは若師匠に対して釈迦に説法でしたネ。
②端正ですが、あまりに古典的・格調主義的で、舞台の書き割りみたいです。三山子はお仕込みが正統派なのでしょう。
③台風一過の空のすがすがしさが感じられます。「タブララサ」は若干トカゲを食べた後殊勝な顔をしている猫の顔を思い起こさせますが、まあいいでしょう。ケロリとした魂の外景をよく言い取っています。。
④綺翁子の血脈中にはいい年をしてまだ殺伐に騒ぐものが流れているようです。紅葉を見れば射たれたケモノの流血を連想し、秋風の音を聞いても、そこに轟音一発を幻聴してしまう等々です。俳句を作って魂鎮めをしましょうね。
⑤戸外で夜じゅう風が吹きすさんでいた宿で、翌朝、この句主はもつれた髪を梳いてやっているわけです。前夜、何をしていたんでしょうね。それにしても、出番がワンテンポ早いよ。句順表に見られるように、次の初ウ2から「恋句」が二句つづくよ。恋の座は別に位置が決まっているわけじゃないから、いいといえばいいのだが、こういうのを普通「待ちかねし恋」と言いますね。
さて、これら5句の中からどれを選ぶかですが、折立は「追っ立て」とも言うくらいで、初裏12句の、歌仙第二象限といえる連続の新出発の節目ですから、ここで気分一新、連衆一同を清新の気分に追い込みたいものです。里女子の作が漂わせるアッケラカンとした空気感がこの際ピッタリしていると思います。採用しましょう。
折立の句からは、表6句の「神祇・釈教・恋・無常・述懐・旅体」の禁制はもうありません。皆さん、どうぞのびのびと初ウ2(通しで8句目)を競って御投句ください。「恋」の短句ですぞ。 了
この初折表6句目(初ォ6)は特に句主(作者)を指定せず、連俳用語で「出放題」という方式の一変種の扱いで、いくつかの候補作を連衆に投句していただき、その中から一句を、僭越ながら拙老 桃叟が勝手に選び出すという風に進めようと思います。7月28日のブログで呼び掛けてから、ほぼ2週間です。寄せられた句は今回3句きりでしたが、歌仙はともかく一歩一歩進むのが身上しんしょうですから、3句だけで見切り発車することにしました。以下は各句の紹介と簡単な選評です。
① 丈の短き陸奥おくの稲刈る 三山
② 異国語通じ鰯雲見る 湖愚
③ 同封されし紅葉葉ひとつ 倉梅
三山子は拙老の早稲田時代以来の老友です。半世紀の時空を越えて馳せ参じていただきました。感謝の気持ちを込めて狂歌を一首〽老い武者は相身たがひのレアメタルこがねしろがね玉もものかは。「稲刈る」ときちんと秋の季語をいれていて文句の付けようがないのだが、難をいえば「陸奥」だ。表六句には地名を嫌うという式目を小楯に取ってこの句を落とさざるを得ず。
湖愚子は70年代の卒業生。昔から少々風狂の癖へきあり。時々ワケが分からなくなる。今回もその口で、季語を入れるのに一所懸命になりすぎ、「鰯雲」まではよかったが、句主がそれでどうするのか意味不明。Oh,oil sardin とでも秋空に叫ぶのかね?
倉梅子の「紅葉葉」は、封筒に閉じ込んだ女心の色が見えてゆかしい。そういえば拙老も昔、オルグに来ていた京都から高雄のモミジを封書に入れて東京へ送ったことがあります。この句を選ぶことにします。以下のような順序で進行します:
1 オ 発句 春 長 桃叟 囀りにわが耳籍さん老の春
2 脇 春 短 桃叟 ぬくもる潮に芽ぐむ葦牙
3 第三 春 長 桃叟 遠干潟貝掘る人はまばらにて
4 四句目 雑 短 碧村 カーブのたびに変はる字あざの名
5 月 秋 長 三山 旅せんか下の弓弦はる月つれて
6 折端 秋 短 倉梅 同封されし紅葉葉ひとつ
7 ウ 折立 秋 長
8 二句目 恋 短
9 三句目 恋 長
10 四句目 雑 短
次の公募は初ウ1(折立 )です。秋の長句です。皆さんのご投句をお待ちします。 桃叟敬白。
お待たせしました。「囀りに」歌仙の初オ5公募の候補作が揃いましたので、選句をさせていただきます。応募作は全部で3句ありました。次の通りです。
いつのまに稲穂ゆらめくよひの月 湖愚
家々につひに月見ぬ芙蓉かな 花丁
旅せんか下つ弓弦はる月つれて 三山
このうちから、捌き手(桃叟)の独断と偏見で、三山子の「旅せんか」を選びます。日々細くなってゆく「下弦の月」(もちろん秋の季語)を旅路の友とするなんて、さすが老境ならではです。さっそく「囀りに」句順表xlsx.の初オ5の欄に書き加えて置きました。御参看ください。「囀りに」句順表。
なお、三山子は桃叟の早稲田時代からの旧友です。このたび久闊を叙して御投句下さいました。この年までおたがいに「散々」な目に遭ったなというのが「三山」の由来らしい。西国の連衆諸兄姉にお披露目致します。
次の公募は初オ6の「折端」、秋の短句です。ご投句をお待ちします。 桃叟敬白。
わが畏友野山嘉正氏が亡くなりました。1937年生まれの同い年でした。心から哀傷の意を表します。
最近はかけ違うことが多く、あまり会うこともなくなりましたが、昔、大学院で机を並べていた頃、友達づきあいをさせてもらった親愛の気分がいつまでも脱けません。思えば50余年も前の初対面の日、会ってすぐは礼儀正しく「野山さん」と呼んでいたのに、一日の終わりには「ノヤ公」になっていたのを思い出します。心安だてにずいぶん失礼をしたものです。遅蒔きながらごめんなさい。
その頃よくこんなことを言い合いました:文学者には「文」の「学者」と「文学」の「者」という二つの種類がある。きみは「文学」の「者」の方で 大成するだろう。ぼくはどうなるか分からないが、好き勝手に「文」の「学者」の途をめざさせてもらう、と。それからおよそ半世紀。誰の目から見ても大きな差が付いています。何といっても野山氏には学界の責任あるポストに就いて、それを難なくこなす力量、そしてそれにふさわしい貫禄が ありました。拙老 などが逆立ちしても及びも付かない資質です。
拙老の「文」の「学者」の方は怪しいもので、82歳になっても海の物とも山の物とも付かない有様です。「同じ字をあめさめだれとぐれて読み」という有名な川柳があります。野山さんは終始正統派の埒を守って、「あめ」「さめ」の正格を崩しませんでしたが、拙老はダレたりグレたりを繰り返しています。性もと不埒者なのです。
『日本近代詩歌史』の著者である故人に向かっては身の程知らずだとお叱りを受けるかもしれませんが、つたない哀悼歌を捧げることをお許し下さい。
見果てんか性根ゆるがぬ一筋の野にも山にも芳躅ほうしょくの跡
友ありき連れ立ち探しもとほりぬ野山に清すがし大和撫子
《以上》
宗教思想家の笠原芳光さんが逝去されました。「偲ぶ会」にはもちろん駆け付けたかったのですが、両脚が動かず、言葉もロレツが怪しい有様なので、残念ながら欠礼させていただきました。代わりに追悼の文章を捧げます。
* * * * *
笠原さんにお目に掛かった回数はそう多くはありませんでしたが、忘れがたい記憶がいろいろ残っています。こちらは確信犯的な無信仰者であり、先方はまだ信仰固き牧師さんでしたから、ぼくなどは処置なしの口だったでしょうが、不思議にウマが合いました。ぼくだけでなく、御自分の人格を慕って寄って来る人々を拒まぬ柔らかな包容力をお持ちでした。周囲に集まった友人たちも多彩でしたが、中でもはっきり記憶に留まっているのは、歌人の塚本邦雄氏を引き合わせて下さったことです。笠原さんにはつとに『逆信仰の歌』(1974)という塚本邦雄論の名著があります。無信仰でも反信仰でも異端でもない逆信仰こそ、この端倪たんげいすべからざる現代歌人を解読するキーワードであるととらえ、それを「現代の魂のアリバイ」(『眩暈祈祷書』)とすることに共感しておられます。当時のぼくはそこまで理解は進まず、ただご紹介いただいた心嬉しさを表したくて、塚本氏への賛辞をへたな狂詩に托したのを思い出します。若気のナマイキでした。前世紀のこととて字面はさほど定かではありませんが、たしかこんな風のものでした。
涼風緑陰一里塚。古来先人道程本。文名馥郁満万邦。二唱三嘆想雄渾。(りょうふうりょくいんいちりづか、こらいせんじんどうていのもと、ぶんめいふくいくたりばんほうにみつ、にしょうさんたんそうゆうこん)
平仄ひょうそくはおろか、辛うじて韻も踏ませただけのお粗末な濫造品です。よくも臆面もなく差し上げられたものです。が、それよりも深くぼくが恥じ入ったのは、先方がぼくの無礼を咎め立てせず――臆面のなさを一喝されて当然でした――返歌として、次の一首を贈って下さったことです。
われ凌しのぐ千草の庭の萩のたけ彦星を招おぐ庭の露の白玉
グウの音も出ないとはこのことでした。さっそく賢しらにも返歌のつもりで、「仄ほの見つかもとこれ夢にあらざるかただかにかくに愛をしむたまゆら」。一顆の珠玉に酬いるに瓦礫を以てす、とはこのことでした。
それ以来、敬愛・親愛・親近を感じる相手には、及ばずながら、「人名歌ひとのなうた」とて先様の姓と名を読み込んだ一首をお贈りするのが習癖になりました。笠原芳光さんももちろんその一人です。いつか「按手」についてお聞きした時、たわむれに額に置かれた手のあたたかさを思い出します。哀悼の短歌を三首、いかにも腰折れですが、贈らせていただきます。
おだやかさ原に群れ伏す羊らはうらら眉目みめよし満つる光に
まつろわぬ黒き子羊エホバには顔をそむけてひとり歩みき
ちち慕ふはぐれ子羊毛を刈りてはだへに匂ふ霊の官能
新しいブログで どんなことができるか、いろいろやってます。現ページ(今開いているこのページ)からなら画像も添付ファイルも送信できますが、(画像は『先賢名言集』でテスト済みですし、添付ファイルは下欄に出ています)が、「コメント欄」を通じてはどちらもできないようです。どなたかご存じでしたらお教え下さい。
さて懸案の「囀りに」歌仙の四句目のことですが、投句が4首あり、思わぬコンペになりました。はなはだ僭越ながら桃叟老人、多少トップダウンになりますが勝手に選考させていただきました。年に免じてお許し下さい。公正を期して競作を次に全首掲げます。到着順。
1 滋味深き椀夜の円居に 赤飯
2 つれ求めてや蓑笠の翁 湖愚(愚林改め)
3 カーブのたびに変はる字あざの名 碧村
4『主戦場』には並ぶ老若 熊掌
誰がどう見ても3が入選作することは一目瞭然でしょう。前句の海岸を海岸線に延長して 句景があざやかに開けます。動線を導入したことで決まりです。ついでに落選作にダメを出しておくと、1はおそらく貝に、3は孤独な老翁のイメージに纏綿てんめんしすぎで、発展性に乏しい。4は「老」字が重出しているから論外です。言い過ぎたらゴメンネ。
添付した句順表のしかるべき欄に治定じじょうした句を各自書き加えてゆきましょう。添付ファイルは下欄に出ています)「囀りに」エクセル句順表
そんなわけで「囀りに」歌仙の次の進行は五句目の競吟ということになります。皆さん、奮って御投句下さい。
『野口武彦公式サイト』は連俳――――こりゃ俳諧ではなく徘徊だとワルクチをいう人もいます――――だけではなく、いろんな話題を取り上げます。ご投稿をお寄せ下さい。ワルクチも歓迎です。良質の悪口は文化のメルクマールです。蒙御免。
昔の人には先見の明があったのでしょうか。それとも歴史は繰り返すのでしょうか。何百年どころか、何千年も前の古い言葉には、今の事が言われているような気がします。

鞠躬如也、如不勝。(論語・郷党きょうとう編)
きくきゅうじょたり、たえざるがごとし――――鞠まりのように身をかがめて恐れ入り、センセンキョウキョウとしている様子をいう言葉です。

憎まれっ子世に憚る。(江戸いろはかるた)――――特にコメントの必要なし。
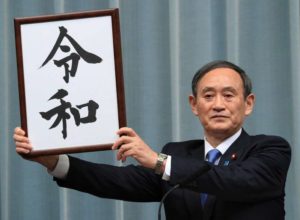
敵は本能寺にあり。(明智軍記)――――その瞬間、男の胸には自分も天下を狙えるという野望が兆したのでした。

非復呉下阿蒙。(三国志・呉志)
またごかのあもうにあらず。――――もういつまでも田舎のオッサンじゃないよ。

巧言令色鮮仁。(論語・学而篇)
こうげんれいしょく、すくなしじん――――故タカジンが菊人形にしたい顔だと言っていたのを思い出します。
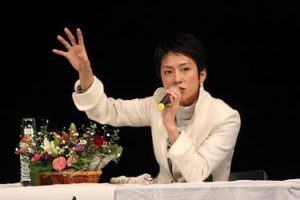
上下交征利而國危矣。(孟子・梁惠 王りょうのけいおう)
しょうかこもごもりをとりてくにあやうし――――誰も彼もが利得に目の色を変えるばかりだったら、国は亡びますわよ。
* * * *
みんな古言古辞です。文責先賢。桃叟妄語。 完
オープンページを開いたら、右側サイドメニューの一番新しい(一番上にある)タイトル――現在は〈『野口武彦公式サイト』の画面一新!〉がそうです――をダブルクリックして下さい。そうすると自由に投稿できる「コメント欄」がページの末に出ます。
そこへ何でも気楽に書き入れて下さい。お名前は仮名(俳号、狂号、戯号、芸名etc.何でもOK)。高校・大学の同級生の皆さん(まだ生きていたら)ヒヤカシをどうぞ。ナントカの冷や水同士です。わが教え子たちよ。呼び水になってくれ。お願いします。
決意というと大袈裟ですが、ちょっと改まった心持ちを述べようという時、昔は特定形式の文章で書き表しました。その形式を「文体」といいます。陶淵明の「帰去来の辞」、蘇軾 (そしょく) の「赤壁の賦」、諸葛孔明の「出師の表すいしのひょう」などがそうで、「辞」「賦」「表」はそれぞれ文体のジャンルです。拙老にとっては今がその時に当たります。どの体を選んだらよいでしょうか。「表」は、「君主への上奏文」と定義されます。拙老は別にアルジモチではありませんが、このブログを読んで下さる皆さんへのきちんとした意思表白という意味では「上奏文」といえますから、「表」の形式を借りることにし、『老春の表』と題することにしました。題に篭めた心は次の3首のごとし。腰折れは御容赦
老波はいづこの岸に寄るやらん目路に文あやなす水脈みをの跡先
夜をこめて沖の波風荒くともいざいで立たん文の防人さきもり
時こそあれ深山みやまに花を尋とめ行かんこぞの枝折をたどりたどりて
気が付いたら80歳になっていました。日本人男性の平均寿命は81.09歳とのことですから、拙老ももうあんまり悠長にしてはいられないわけです。そろそろ残り時間のうちにやっておこうと思う仕事に、あらかじめ目星を付けることにしました。今のうちにやっておきたいことは、わが国の書きことばを保存し21世紀後半にまで持ち伝えることです。前世紀末から今世紀にかけて進行している、すさまじいばかりの言語破壊現象 言葉の無機的記号化・標識化・符牒化、洒落ならぬダジャレの濫用、微妙な言い回しの衰滅、ツイッターと称する電子的オシャベリの盛況、etc. ――が起きた原因はいろいろあるでしょうが、煎じつめれば聞きことばの氾濫に帰一すると私見では愚考致します。コトバをただの音声連続として聴取するだけ、「外声がいせい」としてしか聞こえなくなっている 「内声」がない ことが弊害を生んでいるのです。(このことは長くなりますから、いずれ席を改めて申し上げます。)
今回このホームページを双方向にしたのは、最近、奇特にも本ブログを寓目して下さる読者 それとも訪問者というのでしょうか がどんな人たちなのか掴んでおきたい気持がつのって来たからです。話が通じているのでしょうか。拙老としては、おおまかに言って、3つのグループに分けて把握しているつもりです。
①拙老と世代を共にしている人々。いってみれば「六〇年安保」組です。本当をいうと、語りかけるのがちょっと遅すぎたかも知れません。しだいに幽冥所を変えた人々が多くなって、拙老などは「生き残り」の仲間に属します。この年代層だけが体感できた時代の合わせ目のようなものを、もっと語り明かすことができるのではないか、という気がしています。唐牛健太郎は早死しました。北小路敏も世を去りました。青木昌彦も西部邁も亡くなりました。生き残った面々が、このまま黙って埋もれてしまういわれはありません。
②次に考えているのは、思い切って射程を広げ、まだこの世に生まれていない読者に呼び掛けることです。いわば未生の知己へ発信しておくことです。現代日本の《言語衰退》 文運隆盛の反対概念のつもりです ぶりは当分の間ずっと下降線をたどり、やがてスッテンテンになるでしょうが、その索然砂を噛む時代をみずからも粘菌の胞子のように渇いた原形質と化してひたすら時世に耐え、今はどこかに飛び去っているコトダマが戻って来るのを待ちかねていることを拙老は確信しています。いや、そういう「見ぬ世の友」がどこかにいると直感できます。
思えば、文学の相場が下がった時代 雑書の多量販売とおおむね反比例します は何度もありました。江戸時代だけに話をかぎっても、天明のピークの後、文化文政・天保・幕末と尻下がりが続きますが、やがて明治の文芸興隆期を迎え、戦争の時代に低迷し、また戦後文学の開花期を迎えました。逆説的になりますが、文学が「丈高く」なるには、前世代の人々が浸っている文化的現状に絶望し、呆れ果て、コリャイカンと気を引き締めるのが前提であるような気がします。してみれば、近い将来のスッテンテンにも、あたかもある種の貝殻成分のうちに真珠が育まれ、地底の岩層のすさまじい重圧がダイヤの原石を結晶させるかのように、環境整備の意味があるのかも知れません。
③最後に、拙老が大学勤務時代に接し、その後も何かとつきあいのある、いわゆる「教え子」たちのグループがいます。前後35年間一つの大学にいたわけですが、今振り返ってみると拙老はあまりいい先生ではなかったように思います。そもそも拙老は学問を教えるのが苦手でした。本を読めば覚えられることをワザワザ教室で習う必要はあるまい、というのが拙老のスタンスでした。当ての外れた昔の学生さんたち、ゴメンナサイ。そのかわり拙老はおよそあらゆる文学の根底にある「情感」を力の及ぶ限り伝えて来たつもりです。「情感」とはすぐれた文学を読んだ時、心の底から駈け上がって全身を揺さぶる、ナマモノの感動のことです。文字通り「動かされる」のです。幸福感・達成感・満足感のきわみにふと兆す「かなしさ」だといっても構いません。(「かなし」という日本語を語根的底層にさかのぼってみると、たんに悲哀を意味するだけでなく、親愛・愛惜・感慨といった領域まで幅広い意味成分を持っています。民俗学者によれば、稀少・珍奇の語義もあるそうです。)
もちろん拙老は「教え子」の皆さんに一緒に「文の防人」をやろうよ、とお誘いしているのではありません。八十面下げて「小説」をめざそうというクレージーな老翁につきあういわれは誰にもないことはよく分かっています。ですが少なくとも、旧師はかなりホンキデ現在の言語状況に危機意識を持ち、なんとか貧者の一灯を献じたいと心願を立てた八十翁であると御承知おき下さい。
終わりに、謙遜が足りないかも知れませんが、恥ずかしながら「己亥改元三つ物」をお目に掛けて、わが心意を披瀝しておこうと思います。
発 囀りにわが耳籍さん老の春
脇 ぬくもる潮に芽ぐむ葦牙
三 遠干潟貝掘る人はまばらにて
どなたか第四を付けてくれませんか。場合によったら新しい歌仙に繰り込みます。しかしこれもまるで心得のない人に強制はできません。本ブログを御覧になって、老いの心意気を少しでもお感じになられるようでしたら、新設ブログ欄にどうぞ御鶴声くだされば幸甚です。桃叟敬白。